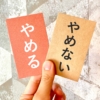斎藤知事のパワハラは研修を受けたら治るのか?
令和6年3月12日の元県民局長の公益通報によって、斎藤知事のパワハラが知られるようになりました。
目次
百条委員会のアンケート結果
兵庫県議会文書問題調査特別委員会
「兵庫県職員アンケート調査」郵送回答分報告
百条委員会の「知事のパワーハラスメントについて」
当該文書記載事項
知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくる。 執
務室、出張先に関係なく、自分の気に入らないことがあれば関係職員を怒鳴り
つける。
例えば、出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止のため、20m程手
前で公用車を降りて歩かされただけで、出迎えた職員・関係者を怒鳴り散らし、
その後は一言も口を利かなかったという。
自分が知らないことがテレビで取り上げられ評判になったら、「聞いていない」
と担当者を呼びつけて執拗に責めたてる。
知事レクの際に 気に入らないことがあると机を叩いて激怒するなど、枚挙に
いとまがない。
また、幹部に対するチャットによる夜中、休日など時間おかまいなしの指示
が矢のようにやってくる。日頃から気に入らない職員の場合、対応が遅れると
「やる気がないのか」と非難され、一方では、すぐにレスすると「こんなことで
僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」と文句を言う。
人事異動も生意気だとか気に入らないというだけで左遷された職員が大勢い
る。これから、ますます病む職員が出てくると思われる。 ○(職員からの訴えがあれば)暴行罪、傷害罪
委員会としての判断
認められる事実
知事のパワーハラスメントについて
㋐ 齋藤知事は、令和3年9月頃、朝刊に載っていた尼崎のフェニックス用地に
万博資材の運搬拠点を設ける方針を固めたという記事について、「こんな話
は聞いていない」と机を叩きながら声を荒げて怒った。
㋑ 令和5年5月、施設の開設について、齋藤知事に説明したところ、「こんな
話聞いていない」と叱責があり、令和5年度当初予算の記者発表資料を見せ
たところ、「これで知事が知っていると思うなよ」という強い叱責が再びあ
り、開所式のスケジュールを変更せざるを得なくなった。
㋒ 齋藤知事は、令和4年 10 月のイベントで、更衣室に見知らぬ男性がいたた
め驚いて、事前に確認して更衣室を用意しておくべきだったのではないかと
職員に注意した。
㋓ 齋藤知事は、令和5年 11 月の東播磨地域づくり懇話会において、エントラ
ンスにつながる通路の車止めの手前で知事公用車が停車して車から降りて
きた時に、「なんでこんなところに車止めを置いたままにしているんや」と県
幹部職員に対し怒鳴った。当該職員は、非常に強い叱責のため頭の中が真っ
白になった状態で車止めを移動させた。知事は、職員が車止めを移動させた
後も非常に強い叱責をした。職員は、社会通念上、業務に必要な範囲の指導
とは思わず、理不尽な叱責を受けたと感じた。その後、知事が会場を後にす
る際、職員に対し、謝罪やねぎらいはなかった。
㋔ 齋藤知事は、片山氏に対し、令和6年3月上旬頃、県立大学の無償化の国会
議員等への根回しに、すぐ動くようにと指示したことを片山氏が忘れていた
ことに怒り、アクリル板に向けて付箋を投げた。
21
㋕ 齋藤知事は、所管課長に対し、令和5年1月の知事協議の際に、政務調査会
資料に記載のあった所管事業が朝刊に載っていた記事を見て、「大阪府と連
携すると書いている。これ聞いてへん。この事業は知事直轄なんだから勝手
にやるな」と、かなり厳しい口調で叱責し、「やり直し」と所管課長を知事室
から退室させた。所管課長は再度、知事に説明しようと何度も秘書課に伝え
たが、説明の機会がなかった。所管課長は1年で異動した。
㋖ 齋藤知事は、令和5年度、複数の幹部職員との間で、全部で 4,885 件のチャ
ットのやり取りをし、そのうち約 44%の 2,165 件が夜間や休日に送られた。
事実に対する評価
齋藤知事が、執務室や出張先で職員に強い叱責をしたことは事実と評価でき、
文書内容は概ね事実であったと言える。
齋藤知事の「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との証言に対して、叱
責を受けた側の証言では、事情を確認されることなく「社会通念上必要な範囲
とは思わなかった」「指導として必要のない行為」「理不尽な𠮟責だった」、「県
職員になってこれまでないというぐらいの叱責を受けた」や、「県庁での職員生
活の中で、机をたたいて怒鳴られたというようなことが初めてだった」、他の職
員がいる前で「頭が真っ白になるほどの叱責」、さらに「異動させられるという
予感のもと実際に1年で異動させられ理不尽と感じた」「トータルに見てパワ
ーハラスメントと評価できる事案かなと思った」等の証言があったことを踏ま
えると、「パワハラを受けた」との証言は無かったものの、パワハラ防止指針が
定めるパワハラの定義である「①優越的な関係を背景とした言動であって、②
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害され
るものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」に該当する可能性があ
り、不適切な叱責があったと言わざるを得ない。
県事業がテレビで取り上げられた件であるが、県の事業は膨大にあるため、
テレビで知事の知らないことが取り上げられることもあり、「聞いていない」こ
とを理由に職員を叱責することは妥当性を欠いた行為である。仮に叱責するこ
とがあるとすれば、テレビでの県職員の説明に大きな過失があり、県に損害を
生じさせる恐れがあった場合などが考えられるが、証言等で明らかになったケ
ースは、そのような場合にあたらない。
知事協議の際の叱責であるが、部局の説明をよく聞いていない、あるいは聞
いていても失念していると思われる事業に対して、全く知らないということで、
説明する機会も与えずに「聞いていない」と叱責するとの証言が複数あったこ
とから、事業への関心の度合によって、認識の深さに差が生じていると思われ
る。また、部局の説明時に齋藤知事は別のことをしているなど、説明を真剣に
聞いていないと感じたとの証言があったことも踏まえ、どの事業も同じ目線で
担当課の説明を聞くという姿勢が欠けており、知事としての対応に疑問が残る。
考古博物館で 20m 歩かされた件に関連して、齋藤知事の発言から行程管理を
重要視していることは理解できる一方で、知事自身が朝の予定時間によく遅れ
てくる、また、その際に謝らないこともあるとの証言もあることから、部下に
は高い水準を課しながら、自分はその基準を守らず特別扱いとする態度は、公
平性と信頼を損なう言動であり、本来は模範となるべき知事の取る言動ではな
い。また、齋藤知事は車から降りるなり、対応した職員に対し、車止めをして
いる理由を聞くこともなく、大声で叱責をしている。職員からすれば、車止め
を入り口から 20m離れたところに設置したことは会場施設のルール上やむを得
ないものであり、車止めを認識した後も強い叱責することは不合理であり、極
めて理不尽な叱責であると言える。
叱責の際に付箋を投げる行為は、知事という立場に鑑みると、投げたものの
形状にかかわらず、その行為自体威圧的なものであり、副知事その他職員を萎
縮させるものである。
齋藤知事の非常に強い叱責や理不尽な言動によって、職員が齋藤知事に忖度
せざるを得ず、救護室・授乳室を知事の控室にしたり、車両が通行できない範囲
に知事公用車を通行させたりする等、ルールに則った県民本位の職務遂行が叶
わなくなっている面があり、極めて深刻な事態が確認できた。
また、強い叱責を受けた当事者本人の就業環境に明らかな影響がなくとも、
実際に見聞きしている同僚への心理的負担や組織の閉塞感につながり、適切な
職場環境を構築するべき組織のトップの言動としては極めて不適切である。
さらに、職員の証言や提出資料によると、齋藤知事から幹部職員へのチャッ
トの数は膨大なもので時間外や休日問わず頻繁に送られていた。1年間に複数
の幹部職員との間で夜間、休日などの業務時間外のチャット数は 2,165 件と多
く、その内容については業務上必要性が認められるものもあるが、夜間や休日
に送信しなくても問題ないと思われるものもあった。もっとも、夜間、休日の
送信頻度や「返信不要」などの配慮がないこと、チャットでの反応がない時に
関係職員に業務時間外に電話をかける行為もあり、緊急性を要しないにもかか
わらず、夜間や休日にクイックレスポンスを求めることは働き方改革が求めら
れる今日において、前時代的な仕事のやり方であると言わざるを得ず、業務の
適正な範囲を超えたものであり、就業環境を害されているといえる。また、チ
ャットのグループ内で叱責するなど一部の内容については、職員らの過度な精
神的負担になっていたと考えられる。
以上のように、齋藤知事の言動、行動については、パワハラ行為と言っても
過言ではない不適切なものだった。
提言
証言にもあるように、明らかに業務上必要な叱責ではなかったことも認められ
るが、齋藤知事は「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との認識を変えてい
ない。業務上必要な範囲ではない、不適切な指導が複数あったということをまず
は知事自身が認めることが重要であり、言動を真に改める姿勢を持たなければな
らない。
一方で、昨年4月4日付けの職員公益通報事案の調査結果及び公益通報委員会
の審議等を踏まえ、12 月 11 日に「県民の信頼確保に向けた改善策の実施」の中
でハラスメント研修の充実として組織マネジメント力向上特別研修の実施が是
正措置として記者発表され、一定の措置が講じられており、是正する必要がある
との認識が示されていると考えられる。
知事当局に以下のことを求める。
・知事、副知事などの特別職を含め管理職等のアンガーマネジメント研修などを
行い、風通しの良い職場環境が確立できているか定期的に検証する仕組みを取り
入れること。
・チャットやメールについては、特に夜間や休日に指示をする際には、緊急性を
要する用件のものに限るか、緊急性がないチャットやメールには即時の返信を必
要としない、あるいは返信を求めないなど取り扱いを定めること。
・齋藤知事は、組織のトップとして、自身の言動が組織に及ぼす影響を常に意識
するとともに、多様な意見に耳を傾けることで率先して働きやすい職場づくりに
努めること。
パワハラ体質は研修を受ければ治るのか?
パワハラ体質は、研修を受けたからといってすぐに「治る」と断言できるものではありませんが、研修はパワハラ防止に有効であり、行為者の意識改善や組織風土の醸成に貢献します。研修によってパワハラに対する正しい知識や共通認識を持つことは、行為者自身の行動を改めるきっかけになり、また、周囲の従業員の意識を高めることでハラスメントを許さない環境づくりにもつながります。ただし、行為者の性格や背景、そして研修内容の質や継続性によって効果は異なり、場合によっては専門機関への相談や配置転換、あるいはハラスメントをさせないための仕組みづくりが別途必要になることもあります。
対人関係の基本は幼児期に親を思い通りの承認を得ることで学習する(人生の立場)
対人関係の基本は、幼児期に親とのコミュニケーションで確立されます。
人間は1年早く生まれる生き物と言われています。他の哺乳類が生まれてすぐに、自力で母親の母乳を飲むことが出来ますが、人間の赤ちゃんは母親に抱きかかえられて、自分の口を乳房に近づけてもらえないと、母乳を飲むことが出来ません。
つまり母親に無視されると、人間の赤ちゃんは死んでしまうことを本能的に知っていて、無視されることを最も恐れています。
生まれて間もない赤ちゃんにとって、母親との関係が全世界なので、母親との関係で、対人関係の基本を身に着けます。
母親との関係で身に着けた人生の立場を、父親や他の人との関係でも確認しながらリハーサルを続けて12~13歳頃に、「自分はこうやって生きて行こう」と言う幼児決断をします。
【第1の立場】 私もあなたもOK
赤ちゃんは泣き叫んだり手足をバタバタさせたりして、必死に自身の欲求をお母さんに伝えます。赤ちゃんが伝えたことに対して、お母さんが適切に対応してくれれば、「私は存在価値のある人間だ、そして、私を大切にしてくれるあなたも大切な存在だ!」と思うようになります。このような対人関係の姿勢を身に着けると、自分も他人も尊重した、理想的な対人関係を作って行きます。
【第2の立場】 私はOKでない、あなたはOK
しかし、お母さんが必ずしも適切に対応してくれるとは限らず、あまり欲求が満たされないと「あなたには存在価値があるけれど、自分には存在価値が無い」と感じるようになります。このような対人関係の姿勢を身に着けると、自分の存在価値を低く見てしまうので、他人の目を気にして生きるようになります。
【第3の立場】 私はOK、あなたはOKでない
さらにお母さんの対応が悪く、ほとんど欲求が満たされないと、「これだけ泣き叫んでも自分の欲求を満たしてくれないのは、自分が悪いのではなく、あなたが悪い」と考えるようになり「私は存在価値があり、あなたは存在価値が無い」と考えるようになります。このような対人関係の姿勢を身に着けると、自分が正しく、他人を見下すような対人関係になります。しかし、この場合の「私は存在価値がある」には、強い劣等感があり、その劣等感を隠すために、他者を支配しようとします。他者を支配することで、自分の存在価値を確認するのです。
【第4の立場】 私もあなたもOKでない
もっと酷く、ネグレクトのような状態になると、「自分も、あなたも存在価値は無い」と考えるようになり、破滅的な人生を送って行きます。
15分で分かるはじめての交流分析2~人生の立場編~(厚生労働省)
斎藤知事は第3の立場
斎藤知事に限らず、パワハラをする人は、第3の立場であることが多いというか、ほとんどです。
人は、相手や状況によって、立場を変えることはありますが、基本的な立場は大きく変わりません。
「三つ子の魂百まで」と言われるように、子どもの頃に身に付いた習慣や考えは、一生変わらないのが普通です。
パワハラ体質を治すには、まず、自分自身がパワハラしている状況に気付くことです。パワハラしている「今ここ」の自分に気付き、「今ここ」で出来る選択を自発的に変えることです。
選択を変えることで、パワハラでは無い方法での問題解決が出来るようになります。それが習慣化すれば、パワハラ体質は改善されます。
しかし、幼い頃から身についてる心の習慣を変えることは非常に難しいものです。
総務省時代の出向先では「好青年」と評価されていたのは、良い子を演じていた
斎藤知事の人生の基本的立場は、「【第3の立場】 私はOK、あなたはOKでない」ですが、総務省時代の出向先では「好青年」と評価されていたのは、周囲の状況を見て演じていたものだと思います。
自分が働く環境により強い立場の人がいる場合には、「順応の子ども」の自我常態で、良い子を演じていたものと思います。
人間のパーソナリティーは「批判的親」「保護的親」「成人」「自然な子ども」「順応の子ども」の5つのバランスで成り立っていて、人によって、どれかが強かったり、複数の自我常態が強い場合もありますが、状況によって、どれかが強く出てきます。
批判的親(父親的)
支配的で権威的な言動:
親の価値観を取り入れ、他者に対して指導的・批判的な態度をとります。
厳格な規範意識:
「~すべき」「~してはならない」といった厳しい規則や道徳観念を重視します。
批判・非難:
他者の行動や考え方を良心や理想に基づいて批判したり、非難したりします。
自己への内的な規範:
他人に対する批判だけでなく、自分自身に対しても良心や道徳、規範を厳しく適用します。
保護的親(母親的)
思いやりと共感:
相手の気持ちを理解し、共感する姿勢を持ちます。
励ましと勇気づけ:
子どもが困難に直面しても、励まし、挑戦する勇気を与えます。
サポートと配慮:
子どもが必要とする時に、精神的・物理的なサポートを適切に提供します。
豊かな人間関係の構築:
このような養護的な自我状態は、良好な人間関係を築く上で非常に効果的です。
成人
状況を客観的に判断し、現実的に考える状態。
自然な子ども(天真爛漫な子ども)
感情・欲求の自由な表現:本能的な欲求や感情をストレートに表現します。
天真爛漫な行動:束縛されずに、自由で明るい振る舞いをします。
創造性・想像力の源:幸福感、想像力、好奇心、創造性の源泉となることもあります。
楽しさ・明るさの源:人間関係に活き活きとした楽しさをもたらし、場の空気を明るくする力があります。
自己中心的な側面:感情や欲求を優先するため、自己中心的で幼稚な振る舞いになることもあります。
順応の子ども(良い子を演じる子ども)
他者の期待に応える:
大人や周囲の顔色をうかがい、相手がしてほしいと思うことを察して行動する。
協調性・柔軟性:
集団のルールや他者の感情に合わせ、社会生活を円滑に進めるための能力。
消極性・依存性:
自分の意見を主張せず、消極的になったり、他者に依存したりすることが増える。
自己否定的な傾向:
自分の本当の感情や欲求を抑え込み、自己否定的な自我が育つことがある。
ストレスの蓄積:
本来の「自分」を押し殺すことによるストレスが蓄積し、後に大きな不満として表出する危険性もはらむ。