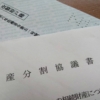公益通報者保護法の解釈で揺れる兵庫県 ― 消費者庁は放置するのか
公益通報者を守るために制定された「公益通報者保護法」をめぐり、兵庫県の斎藤元彦知事が繰り返し「当時の対応は適切」と強調している発言が、同法を所管する消費者庁の公式見解と整合していない疑いが浮上しています。さらに、消費者庁と兵庫県の説明も食い違い、行政の信頼を揺るがす深刻な事態となっています。
目次
知事の独善的な「適切適法」発言
斎藤知事は、公益通報者保護法に照らして「当時の対応は適切適法」と断言しました。しかし、その裏付けとなる根拠は示されていません。法の所管官庁が疑義を示しているにもかかわらず、知事が独自解釈を繰り返す姿勢は、行政トップとしてあまりに軽率で独善的です。
公益通報制度は、不正を告発する勇気を持つ職員を守る最後の砦です。その解釈を都合よくねじ曲げて「問題なし」と言い張ることは、制度の存在意義を空洞化させる暴挙に等しいといえます。
国と県で食い違う「齟齬」発言
2025年5月16日の閣議後、伊東良孝消費者担当相は「兵庫県から返答があり、法解釈と齟齬はないと確認した」と述べました。ところが、兵庫県の担当者は「齟齬がないとは伝えていない」と真っ向から否定。
一国の所管官庁と自治体の公式見解が食い違うなど、極めて異常です。県民から見れば「どちらかが虚偽を言っている」構図であり、行政への信頼を根本から損なう深刻な問題です。
消費者庁の責任放棄
問題は、消費者庁の姿勢にもあります。「齟齬はない」と発表した以上、その根拠を明確に示す義務があります。もし本当に齟齬がなかったのなら、なぜ兵庫県はそれを否定するのか。逆に齟齬があったのなら、消費者庁が事実を矮小化して県を擁護したことになり、制度の信頼性を自ら損なったことになります。
公益通報者保護制度は、弱い立場の通報者を守るために存在します。その制度の番人たる消費者庁が、地方自治体の知事の独自解釈を容認するような姿勢を取るなら、全国の自治体で「独自解釈の正当化」がまかり通り、通報者保護は絵に描いた餅となりかねません。
放置すれば制度は死ぬ
この問題を放置すれば、次の深刻な影響が広がります。
- 行政の信頼失墜
国と県が矛盾する説明を続ければ、県民は「行政は嘘をついても構わない」と感じ、統治の正当性が揺らぎます。 - 公益通報者の萎縮
知事の「適切適法」発言がまかり通れば、職員は「どうせ守られない」と萎縮し、不正が隠され続けます。 - 全国への悪影響
所管官庁が是正に動かず放置すれば、他の自治体も「解釈は首長次第」と誤解し、制度の全国的な形骸化を招きます。
伊東大臣記者会見(令和7年5月9日)
(問)兵庫県の内部告発文書の問題についてお聞きします。
消費者庁は4月に兵庫県に対し通報者の保護の対象に外部通報を含めるかどうかについて、「県と消費者庁の公式見解が異なると指摘していた」という報道があります。消費者庁から県へ指摘をされた意図について、まずお伺いしたいです。
また、兵庫県の斎藤知事は昨日の会見で、消費者庁の指摘に対して「重く受け止めたい」というふうに御発言されていますけれども、知事のこれまでの対応についてどのように認識されているのかというところと、再度消費者庁から県に対して何か指摘であったりなどされる考えはあるのかという点も併せて伺いたいと思います。
(答)消費者庁は、兵庫県に対しまして、4月8日に、法定指針に定める、「公益通報者を保護する体制の整備」として事業者が取るべき措置について、公益通報者には2号通報者・3号通報者も含まれる旨、伝達をいたしております。
これは本年3月26日の兵庫県知事会見で「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります」との発言を踏まえたものでありまして、消費者庁といたしましてもしっかり対応をしてきたところであります。
なお、兵庫県知事のこれまでの対応につきまして、消費者担当大臣としてコメントする立場にはないところでありまして、今後消費者庁からの対応につきましては、必要に応じまして適切に対応してまいりたいと考えているところであります。
(問)今の質問に関連して、斎藤知事は昨日の会見で、「重く受け止める」という一方で、「県の対応は適切だ」と。「消費者庁の見解に従う」とは最後まで言わなかったと。これは正に斎藤兵庫王国が無法状態に化して、所管省庁の消費者庁の見解を受け入れないと、解釈を受け入れないという発言に等しいと思うんですが、こういう無法状態を放置して、大臣としてよろしいんでしょうか。
コメントしないとおっしゃいましたが、何らかの措置、コメントを発するべきではないとお考えではないんでしょうか。
(答)先ほど申し上げましたとおり、消費者庁としては、法定指針に定める「公益通報者を保護する体制の整備」として事業者が取るべき措置について、これは消費者庁の一般的な解釈を兵庫県に伝達をしているところであります。
また一方、消費者庁は、兵庫県が行った個別の通報への対応等については、これはコメントする立場にはないということでありまして、兵庫県知事のこれまでの対応については、消費者担当大臣としてコメントすることは差し控えたいと、こう思っております。
(問)今の御回答だと、所管省庁の消費者庁の解釈に従わずに、斎藤知事が勝手に独自の法解釈で県の対応を適切だと言い放つと。昨日の会見でも出たんですけれど、今後同じような件が、外部通報があったときに兵庫県はどう対応するのかという質問に対して、はっきり知事は答えなかったと。
今、大臣が斎藤知事に何らかコメント、批判しないと、法の趣旨、法が守られないという無法状態が続いてしまうと、兵庫県では外部通報した告発者が守られないということになるのではないんでしょうか。
(答) これは国会の議論の中でも出てきたお話でありますけれども、公益通報者保護法において、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されている。この大原則がここにあるわけであります。
また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていることを踏まえ、消費者庁の行政措置は適用しないこととされております。
今後、兵庫県において、地域の住民からの信頼が得られるよう、これまた努めてもらいたいと、こう考えております。
(問)(この質問で)最後にしますが、大原則が守られないので何らかのコメントを大臣が発するべきではないかと思っているのですが、正にこのままだと兵庫県民、兵庫県庁で内部告発外部にした場合は、斎藤知事の独自の見解が押し通されてしまう恐れがあると、こういう状態を放置していいのかということをお聞きしているんですが、大臣のお考えを是非お聞かせください。
(答)記者のおっしゃっていることはよく分かります。分かりますけれども、消費者庁においては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体向けに、通報対応に関するガイドラインを策定している。あるいはそのほか、地方公共団体に限らず、民間事業者、労働者等に対しましても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応等、様々なやり取りを日常的に行っているところでもあります。
引き続きこうした対応を適切に実施していかなければならいと、こう思っております。
いずれにしても消費者庁、こうした法的な立場の中での限界があるところでもありますので御理解いただきたいというふうに思います。
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202505/video-296703.html(出典:伊東大臣記者会見(令和7年5月9日))
結論 ― 消費者庁と兵庫県は説明責任を果たせ
公益通報者保護法を所管する消費者庁は、直ちにこの問題を正面から説明し、県民に対して透明性を持って事実を明らかにすべきです。兵庫県もまた、知事の「適切適法」発言がどのような根拠に基づくのか、はっきりと説明責任を果たさなければなりません。
このまま消費者庁と兵庫県が互いに食い違う発言を放置し続けるなら、制度の信頼は死に、公益通報者は守られず、県政そのものが崩壊の危機に陥るでしょう。
私たちが出来ること
私たちが、この異常事態に対して出来ることは、斎藤知事が消費者庁の見解とは違う答弁を続けていることを消費者庁に伝え続けることです。
そして、消費者庁自ら、公益通報者保護法を形骸化させるのかを問わなければいけません。
消費者庁の対応に限界があることは十分に理解していますが、不正を告発した人が守られない見解を公に示している斎藤知事を消費者庁が放置することは、不正を分かっていても告発すると、徹底的に叩かれることを容認することになり、優越的な立場の人間が不正し放題の社会を容認することに繋がります。