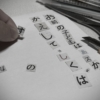公益通報者保護法違反に対する斎藤信者の言い分とその反論
兵庫県の公益通報者保護法違反問題(内部告発者の不利益取扱い・情報漏洩など)に関して、「斎藤知事を擁護する人(いわゆる斎藤信者)」がよく示す言い分は、事実関係よりも「感情的擁護」や「政治的防衛」に基づくものが多いです。
SNSやコメント欄、県政関連投稿の分析から整理すると、次のような主張パターンに分類できます。
目次
「違法ではない/法の解釈が曖昧」論
主な言い分:
- 「公益通報者保護法は曖昧だから、違法とは言い切れない」
- 「消費者庁の見解はあくまで“技術的助言”であって、拘束力はない」
- 「知事の判断が間違いとは限らない。法解釈の違いにすぎない」
分析:
法の趣旨(通報者保護)よりも、「知事が悪くない可能性」を強調することで心理的な正当化を図るタイプ。
しかし実際には、公益通報者保護法の運用基準はかなり明確であり、消費者庁の助言は行政として従うべき“実質的な指導”に近いものです。
「告発者が悪い」論(スケープゴート型)
主な言い分:
- 「内部告発した職員が裏切り者」
- 「組織の機密を漏らしたのだから処分されて当然」
- 「告発で県政が混乱した。県民に迷惑をかけている」
分析:
通報者を“正義”ではなく“トラブルメーカー”と見なす認識。
日本では内部告発文化が根付きにくく、「忠誠心」や「和を乱さないこと」が美徳とされるため、保守的県民層や行政関係者にこうした意見が多く見られます。
「マスコミや反対派が煽っている」論
主な言い分:
- 「マスコミが偏向報道しているだけ」
- 「野党や県職員組合が、斎藤知事を潰すために騒いでいる」
- 「百条委員会も政治的な動き。真実ではない」
分析:
“陰謀論型”とも言える擁護パターン。
不正の指摘を「知事を攻撃するための政治的材料」と位置づけることで、事実から目をそらし、「敵対構図」で物語化します。
「知事の善意」論(人格信仰型)
主な言い分:
- 「斎藤さんはそんな悪いことをする人じゃない」
- 「本人は正しいと思って行動した。悪意はない」
- 「若い知事が経験不足で誤解されているだけ」
分析:
客観的な法令違反よりも「人柄」で擁護するパターン。
政治的リーダーを“人格的に信じる”支持者によく見られ、宗教的とも評される「信仰型支持」です。
「処分されてないから問題ない」論
主な言い分:
- 「刑事罰も行政処分も出ていないから、違法ではない」
- 「検察が動いていない=問題なし」
- 「騒いでいるのは一部の人だけ」
分析:
「司法判断が出るまでは無罪」という法廷主義的論理を行政に当てはめるもの。
ただし、行政は本来“司法以前の自律的な法令遵守”が求められるため、これは誤った理解です。
「些細なミス」論(過小化・矮小化)
主な言い分:
- 「情報を少し共有しただけでしょ?」
- 「そんなことで知事を責めるのはおかしい」
- 「県民生活に関係ない話だ」
分析:
公益通報者保護制度の本質を理解せず、「小さな事務ミス」として軽視する傾向。
行政の信頼や職員の通報意欲を損なう重大性を理解していない層です。
「怪文書」主張側が挙げる主な論点・根拠
匿名で先に外部へ配布した点が問題
まず匿名文書を報道機関等へ流した行為を「外部に拡散することで公益通報の手続きを踏まず、意図的に世論を動かそうとした」と見なす主張。これが「怪文書」扱いの根拠になる。
内容に事実不確定・根拠不明の記述が含まれるとする指摘
文書の中に「真偽が明確でない記述」が含まれており、第三者(県側や一部の調査者)が「事実無根や確認不足」と評価した点を根拠に「怪文書」と断定する意見がある。
通報の意図(目的)の疑義
公益通報者保護法の要件には「通報の目的が不正の是正であること」が重要だが、匿名配布→世論喚起の流れから「不正目的(政治的動機や報復など)ではないか」と疑う見方が出る。百条委向けの書面でもこの点が論点になっている。
職務時間中に文書作成・配布が行われた疑い
県は「業務時間中に虚偽を含む文書を作成・配布した」として懲戒処分の理由にした部分があり、これをもって不正な行為とする主張がある。
公用PCの私的文書による悪性立証
公用PCに、告発とは無関係/私的性格の文書・データがあった
- それをもって「その人物は仕事時間中に私的作業もしていた」「告発を行う動機が私的混入している」「虚偽・工作目的だった可能性がある」と疑う
- よって「その告発(匿名文書/通報)は、公益目的・善意の通報とは言えない」「だから公益通報保護法の保護対象にならない」
- 或いは「疑いが濃い/信用できないから、知事らが通報者を特定・聴取した対応は正当だ/保護制度を適用すべきでない」
この主張は、「通報者の信頼性や動機・背景を疑う」ことで通報そのものの正当性をそぎ、「保護の土台」を揺さぶろうとするものです。
この主張の法的・論理的問題点
推定の逆転を認めすぎるリスク
通報者が何らかの私的行為をしていたというだけで、通報の公益性全体を否定するのは、通報制度を萎縮させる恐れがある。司法・行政の通報制度では「善意・合理的信じる理由」が重視され、「一部疑義」があれば即排除とはしない。
私的文書と告発内容が無関係である可能性
公用PCにあった「私的な文書」が、告発内容・手段・目的と無関係である可能性は高い。告発における不正事実指摘と、私的メモ・日記などとは別軸なので、両者を直結させる論理には注意が必要。
証拠の取得手続・違法性
公用PCのデータ取得や閲覧・使用方法において、不適切な捜査・強制手続によって取得されたものを根拠とするのは違法性・証拠能力の点で問題になる可能性がある。
動機・目的の多元性
通報者にも内在的な動機の混ざりがあり得る(怒り、不満、対抗意識など)一方で、主たる目的が不正の目的(公序良俗に反し、不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的)でない限り、制度として一定保護される。動機の「不純さ」だけで全面否定できない。
立証責任論
私的文書があったことをもって「告発自体が公益通報ではない」とするには、文書の内容・文脈・動機を立証する責任が主張者側にある。単なる疑義では認められない。
「これは公益通報(保護対象)だ」とする反論・主張
後に正式に公益通報の窓口へ実名で提出している
匿名配布が先でも、4月4日に正式な通報を行っており、その時点で公益通報法の手続きに係る議論が生じる。形式的に通報手続を踏んだ点を重視する見解。
通報の内容に公益性が認められる可能性
通報が行政上の不正や公金・選挙関連など公益性の高い事柄を指摘している場合、外部通報(報道機関等への提供)も通報方法として正当化されうる(ケースにより)。百条委の議事資料でも、公益性の判断は中立的な調査を経て出すべきだとされている。
第三者委や有識者の見解は分かれている
弁護士や有識者の間でも評価が割れており、単純に「怪文書」と決めつけるのは早計という意見がある。メディアの取材・専門家意見でも両論が示されている。
兵庫県の第三者委員会が「公益通報者保護法違反」と指摘した根拠の中核
公益通報としての位置づけを肯定しつつも限定的・複雑な判断
報告書は、元県民局長の文書作成・配布・通報行為を「公益通報」の一形態と捉えうる可能性を認めつつ、ただしそのまま全面的に保護されるわけではないとの見解を示しています。
主要論点と調査委の判断
通報対象事実(公益通報に該当しうるか)
公益通報者保護法(およびその指針)が対象とするのは、犯罪行為や刑罰・過料の対象になる行為などの「不正」行為である。
本件文書には、贈収賄に関わる可能性のある「贈答品問題」、補助金・協賛金絡みの「背任」問題、さらにはパワハラの指摘などが含まれていると認められる。これらは、(少なくとも一部は)公益通報の対象となる可能性があると考えられる(通報対象事実性を満たす可能性がある)と判断しています。
ただし、すべてが刑罰対象になるわけではなく、パワハラそのものは通常、刑法犯罪とはされないため、そこについては公益通報の保護対象になるかどうか慎重に判断すべき、という立場です。
通報目的(不正目的か否か)
通報行為が「不正の目的」でなされていないことが、公益通報と認められるためには重要であるが、現実には目的が混在することもありうる。
本件では、報告書は、元局長の主張(政治的批判・不満の代弁、組織改善を願う意図など)を一定程度妥当と見ており、重大な不正目的だけでなされたものとは言えない、という判断を示しています。
この点をもって、報告書は「本件文書の作成・配布は公益通報に該当し得る」とする方向性を採っています。
利害関係者の関与・通報者探索・不利益取扱い
公益通報制度・保護法(と指針)には、利害関係者が通報対応業務に関与してはならないという規定があり、通報者を探索してはならないという制限規定もある。
本件では、知事、元副知事、幹部職員ら利害関係者が文書対応に深く関与していたことが指摘され、この点を制度趣旨に反する不当な関与としています。
また、通報者を探索する行為(メールチェック、局長への尋問、公用パソコンの回収など)が行われたことが違法性を帯びると判断しています。
通報行為を理由とした懲戒・不利益な取り扱い(退職保留、懲戒処分など)がなされた点についても、不利益取扱いの禁止規定に照らして問題があると判断しています。
真実相当性と保護適用の制限
公益通報として保護を受けるためには、通報内容が「真実相当性」をもつことが求められるという見解を報告書は採っています。
調査委員会は、贈答品問題や優勝パレード絡みの補助金・支出問題などについては、文書に一定の真実相当性があったと判断しています。
一方で、パワハラ指摘部分については、暴行罪・傷害罪に該当するような刑事性を含むとは認められず、真実相当性を全面的に肯定するには至らないとの判断をしています。
処分の適否・効力制限
通報行為を理由とする懲戒処分には問題があるとし、特に元局長が作成・配布した文書を理由に科された懲戒処分部分については効力を否定すべきとの意見を示しています。
ただし、文書以外の別の行為については処分の効力を認めるべきという考えも示されています。
公益通報としての位置づけ
調査委は、元県民局長の告発文書を 公益通報の一形態 として扱う可能性を認めており、「通報対象事実性」「通報目的の適合性」「真実相当性」といった要件を検討した上で、部分的な保護を肯定する立場を採っています。
ただし、この位置づけは無条件ではなく、通報者探索行為や利害関係者関与、不利益取扱いがあった点などを考慮して、保護の適用範囲を限定すべきとの判断をしています。
特に、文書作成・配布部分を理由とする懲戒処分には効力を否定すべきとの見解を示しており、通報行為そのものを処罰根拠とすることには強く異論を唱えています。