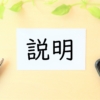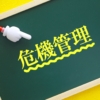第三者委員会の結論を否定するのは誰の責任か ― 裁判をすべきなのは県議会ではなく知事本人
目次
第三者委員会とは何か
第三者委員会は、不祥事や告発があった際に組織の自浄力を示すために設置される検証機関です。法的拘束力は持ちませんが、組織が自らの説明責任を果たすための重要な仕組みとして、近年多くの自治体や企業で運用されています。
ただし専門家の間では、委員選定や運営の独立性が十分でないケースも多く、「金科玉条のように扱うべきではない」という指摘も少なくありません。それでも、『組織が自ら設置した検証結果』として一定の重みを持ちます。
第三者委員会を活用する理由
第三者委員会が設けられるのは、主に「迅速な事実確認」と「行政の信頼回復」を両立させるためです。
裁判のように法的拘束力はありませんが、
-
手続きが早く(通常は数か月〜半年程度)
-
専門家が中立的立場で調査し
-
行政が自らの問題を整理・改善できる
というメリットがあります。
つまり、裁判に頼らずに行政の健全性を保つ“実務的な解決手段”なのです。
裁判との違いと限界
裁判は最終的な法的判断を下す手段ですが、
-
手続きが長期化(2〜3年かかることも多い)
-
公費や人件費の負担が大きい
-
行政の意思決定が停止する
というデメリットがあります。
特に行政組織の場合、長期化はそのまま県政の停滞に直結します。
訴訟が続く間、関係部署は「判断を避ける」傾向になり、政策決定のスピードが落ちるのです。
委員会の認定を受け入れないリスク
第三者委員会の報告を「納得できない」として無視することは、行政が自ら選んだ迅速な検証手続きを自ら無効化する行為です。
その結果、
-
行政判断が止まり、職員が萎縮する
-
議会や市民との信頼関係が崩れる
-
「知事が気に入らない結論は無視する」という悪い前例を作る
といった、組織全体の機能不全を引き起こします。
兵庫県の第三者委員会が出した結論
兵庫県が設置した第三者委員会は、告発文書を精査し、その内容を「公益通報に該当する可能性がある」と認定し「公益通報者保護法違反」を認定しました。なお、本委員会の設置には県費として約3,600万円が投じられています。
この点は重要です。委員会を設置し報告書を受け取ったのは県であり、最終的な行政責任を負うのは知事を含む県執行部です。
「裁判で決めればいい」という主張の矛盾
「不服なら裁判へ」という主張は一見正論のように聞こえますが、次の点で矛盾があります。
1. 委員会は県自身の内部検証手続きである
第三者委員会は訴訟を前提にした仕組みではありません。県が自ら設けた検証の結論を、県トップが一方的に否定することは自己矛盾に当たります。
2. 裁判を起こすべき当事者は誰か
委員会報告に不服があるのであれば、裁判を起こすべき当事者は県議会ではなく、報告書の設置・受領を決めた斎藤知事自身です。県議会は監視・チェックの役割を担いますが、報告書の法的な正当性を争う立場にあるのは報告書を設置した側(斎藤知事)です。
県議会は、報告書を「信頼できない」とする立場ではなく、「報告書を踏まえて是正を求める」側です。
3. 最初から裁判を選択すれば無駄な支出は避けられた
委員会設置に約3,600万円の公費が投じられている以上、「裁判で決めればよかった」という主張は、税金の使途と行政の説明責任を軽視するものです。
自身にとって都合の良い結論が出れば受け入れて、自身にとって都合の悪い結論が出れば否定するので、あれば第三者委員会に約3,600万円も公費を投じる必要は無く、最初から裁判をすれば良かったのです。
もし「裁判で決めるべき」と考えるなら、最初から3,600万円をかけて委員会を設ける必要はありません。
つまり、「裁判で決着を」と言う人ほど、行政の無駄遣いを容認している矛盾があります。
自ら設けた検証機関を否定する知事の責任
第三者委員会は行政の自浄作用を担う制度です。報告が自分に不利だからと否定し、告発者を処分する行為を正当化する行為は、制度本来の趣旨を損なうものです。
報告書に疑義があるならば、斎藤知事こそが法的手続きを取って結論を覆す責任があるはずです。それを県議会に転嫁するのは筋が通りません。
結論
県が設置した第三者委員会の結論を否定するのであれば、裁判を起こすべきは県議会ではなく、斎藤知事本人です。自らが設置を決め、税金を投じた委員会の報告書を「気に入らないから無視する」ことは、行政の透明性と信頼性を著しく損ないます。
自浄作用を示すための制度を否定することこそ、最大の「自浄力の欠如」です。