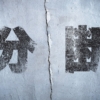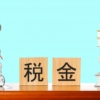日本リメイクの内部通報問題──兵庫県の「斎藤知事型」対応が企業にも波及する危険性
目次
日本リメイクでの内部通報問題
2025年10月、リフォーム業大手「日本リメイク」で、内部通報を行った社員に対して不利益な対応があったと報じられました。
記事によると、社員が会社の不正を指摘したところ、会社側が通報内容を「不正な目的の告発」とみなし、懲戒処分を検討していたとされています。
このような対応は、公益通報者保護法の趣旨に反しており、改正法で明確に禁止されている「通報者特定や報復行為」に該当する可能性があります。
内部告発者に4千万円賠償請求 障害者ホームが元役員提訴
障害者向けグループホームの運営をめぐり、入居者からの食費の徴収方法や、公的報酬の請求の在り方について問題が指摘され、自治体から行政上の指導を受けた事業者があった。 この事案では、内部で不正の可能性を指摘した元役員に対し、事業者側が多額の損害賠償を求めて訴訟を提起した一方、元役員側は、当該行為は正当な公益通報であり、訴訟は報復的なものであるとして反訴している。 このように、内部告発を行った関係者が、事後的に訴訟の対象となるケースは、公益通報者保護制度の実効性や、通報者が安心して問題を指摘できる環境が確保されているのかという点で、社会的な課題を提起している。
兵庫県に見られた前例と企業風土への影響
兵庫県では、斎藤元彦知事の下で、県職員による内部告発(文書問題)に対して、知事側が通報者探しを行ったとされる事例がありました。
この問題では、第三者委員会が「公益通報としての性質を有する」と認定したにもかかわらず、県は通報者を守らず、むしろ調査対象として扱いました。
斎藤知事は「誹謗中傷性の高い文書」と言っています。これは、告発文書が不正の目的だったと暗に示すもので、「不正の目的」だったから、告発者探索も告発文書の作成・配布を行ったことに対する懲戒処分も正当な措置であったとの見解なのです。
このような県の対応は、「通報者を守らなくても問題にならない」という誤った前例を社会に示したことになります。
結果として、兵庫県内の企業が、
「行政がやっているのだから、うちも同じように対応して構わない」
という誤解を持ち、通報者潰しが民間にも波及する危険性が生まれています。
「誹謗中傷性が高い」=「公益目的ではない」というレッテル化
斎藤知事は、第三者委員会が「公益通報の性質を有する」と明言しているにもかかわらず、
「あの文書は誹謗中傷性の高いものであり、内部通報とは言えない」
という趣旨の発言を繰り返しています。
この言葉の意味は、法的に言えば次のような主張を暗示しています。
「通報の主たる目的が公益ではなく、個人攻撃(不正な目的)である」
つまり、**「公益通報に該当しない」=「保護法の対象外」**というロジックに持ち込み、
- 通報者を特定しようとした行為
- 通報行為を理由とする懲戒処分
を「違法ではない」と位置づけようとしている、という構図です。
【法の趣旨を行政トップが軽視した前例】
公益通報者保護法は、
「通報者の特定をしてはならない」「通報を理由に不利益取扱いをしてはならない」
という行政職員にも適用される法的義務を明確に定めています。
ところが兵庫県の場合——
- 2024年3月の「内部告発文書」について、
**通報者を特定しようとした(または特定に近い調査を指示した)**とされる知事の行為があり、
消費者庁の法定指針にも反していると指摘されている。 - さらに、第三者委員会報告書では
「公益通報の可能性を否定できない」と言及されているにもかかわらず、
知事側がそれを「不正な文書」と決めつけ、通報者の側を懲戒処分・社会的排除した。
つまり、法を執行すべき側が法の趣旨を無視した。
これは、法制度の信頼を根底から崩す前例になってしまいました。
【行政トップの行為が“文化的免罪符”になる】
行政トップが通報者を敵視する姿勢を見せると、
その県の組織・企業社会に次のような空気が広がります。
「知事がやっているのだから、民間でも問題ないだろう」
「通報者より組織の名誉を守るのが正しい」
このような空気は、**「通報者排除の文化」**を形成します。
結果として、企業内部でも次のような行動パターンが常態化しやすくなります:
- 不正を指摘した社員が「裏切り者」扱いされる
- 内部通報を握りつぶす、または通報者を退職に追い込む
- 経営側が「公益目的ではない」と主張して報復を正当化する
まさに、今回の埼玉県の「日本リメイク訴訟」で起きた構図です。
【兵庫県内企業で起こりやすい“構造的要因”】
兵庫県では、以下のような条件が重なっており、
民間企業にも“告発者潰し”が波及しやすい土壌が整っています。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 行政の前例 | 県トップ自らが通報者を特定し、処分まで行った。 |
| 監督機関の弱さ | 消費者庁が兵庫県への強い是正指導を行っていない。 |
| 県庁・企業風土 | 「上に逆らうことは悪」という封建的体質が根強い。 |
| 司法的チェックの遅れ | 裁判による違法認定や是正措置がまだ行われていない。 |
| メディア環境 | 県政批判を深く掘り下げる報道が限定的。 |
このような環境では、企業側が
「公益通報に見せかけた個人的攻撃」
と主張するだけで、通報者を法的・社会的に追い詰めることが容易になります。
つまり、行政の姿勢が企業の“抑止力”を奪っている状態です。
兵庫県は「通報者リスク県」になりつつある
兵庫県のように、
行政トップが公益通報者保護法の精神を軽視した前例が放置されると、
県内企業に次のような連鎖が起こり得ます:
- 通報が「内部の裏切り」として扱われる
- 通報者を排除しても社会的非難が弱い
- 行政が守らないなら、企業も守らない
- 結果として、県全体のガバナンスが脆弱化
つまり、
兵庫県では行政・民間を問わず「通報者が守られにくい県」になりつつあるという現実があります。
改正公益通報者保護法での刑事罰
2022年6月施行の改正公益通報者保護法では、
行政機関・企業の職員が、通報者の特定につながる情報を漏らしたり、特定を試みたりした場合に、
刑事罰(最大30万円以下の罰金) が科されるようになりました(第21条)。
つまり、通報者を守るための「抑止力」が、従来より強化されています。
ただし「公益通報」に該当しないと保護対象外
しかし、法の保護を受けるためには、その通報が 「公益通報」 に該当する必要があります。
ここで重要なのが、通報の目的です。
- 通報の「主たる目的」が公益(違法行為の是正、社会正義の実現など)である
→ ✅ 保護対象 - 通報の「主たる目的」が個人的な恨みや報復、他人を陥れることなど不正な目的
→ ❌ 保護対象外
「不正な目的」とされれば刑事罰の対象外になる仕組み
2022年改正の公益通報者保護法では、通報者の特定や報復行為に対して**刑事罰(30万円以下の罰金)**が設けられました。
しかし、保護を受けるには、通報が「公益通報」に該当することが条件です。
つまり、企業側が通報を次のように主張すれば、法の網をすり抜けることが可能になります。
「この通報は公益のためではなく、個人的な報復目的であり、不正な目的の通報だ」
このように「不正な目的」と判断されると、
- 通報者を守る法的保護が外れる
- 通報者特定や処分を行っても、刑事罰の対象にならない
- 結果として、告発者潰しの抑止力が働かない
という構造的な抜け穴が存在します。
現実問題として
「公益目的か不正目的か」は、主観的な判断が多分に含まれます。
行政や企業が「これは不正な目的の通報だ」と都合よく解釈すれば、
告発者を保護しない口実にもなり得ます。
この構造は、まさに兵庫県のケース(斎藤知事の対応)で示されたように、
「通報者の動機」を問題視して、本来の不正追及を逸らす手口と重なります。
今後の課題と提言
「公益目的か不正目的か」の線引きは非常に曖昧で、行政や企業の恣意的な判断が入り込みやすい領域です。
兵庫県のように、トップが通報者を敵視する風土が広がれば、企業社会でも同様の構造が再現される可能性があります。
真に内部通報制度を機能させるためには、
- 通報の「動機」ではなく「内容と真実相当性」に基づいて保護を判断すること
- 行政が率先して公益通報者を守る姿勢を示すこと
が不可欠です。
まとめ
日本リメイクの事例は、斎藤知事による兵庫県の対応と驚くほど似た構図を持っています。
行政が保護法の理念を軽視すれば、その姿勢は企業にまで波及し、
「通報者が守られない社会」へと逆行してしまう危険性があるのです。