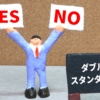斎藤知事の「真実」とは何か?──SNSで語られない“事実”とGoogleが示す答え
目次
SNSでは見えるのに、Googleでは見えない「斎藤知事の真実」
Googleで「斎藤知事 真実」で検索しても、信者的な擁護言説は上位に出てきません。
一方、X(旧Twitter)では“斎藤知事こそ正義だ”という投稿が繰り返されています。
この差は、単なる人気の問題ではなく、情報の信頼性を自動的に評価するGoogleアルゴリズムの違いによるものです。
Googleが信じる「真実」──E-E-A-Tとは何か
Googleは検索品質の中核に、次の4要素(E-E-A-T)を置いています。
| 要素 | 意味 | 評価される内容 |
|---|---|---|
| Experience(経験) | 実体験・一次情報の信頼度 | 当事者・現場・記録 |
| Expertise(専門性) | 専門知識・法的根拠 | 弁護士・公的文書 |
| Authoritativeness(権威性) | 発信者の社会的信用 | 報道機関・学識者 |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報源の正確さ | 出典明示・一次資料 |
この評価に基づき、第三者委員会報告書や公的資料、報道記事は上位表示されます。
逆に、匿名のX投稿やファン的擁護は、信頼スコアが低く、検索結果から排除されます。
さらに、YMYL(Your Money or Your Life)と言われるお金や健康に関するジャンルは、より厳しい基準を適用していて、政治の分野もその分野に含まれ、Googleは通常の検索結果の評価基準よりも、より厳しい基準を適用しています。
Googleは、Googleの検索結果で上位に表示された結果を信じて、「健康被害」や「経済的損失」を被るようなことを望んでいないためにE-E-A-Tを重視しているのです。
SNSにあふれる「真実」は、なぜ信頼されないのか
SNSでは、論理よりも「感情」が評価されます。
- 過激な投稿ほどエンゲージメントが高くなる
- “敵味方”構造が拡散を促す
- ファクトチェックより共感が優先される
そのため、SNSでは信者的な真偽不明の発信も共感されれば、多くの人に共有されることになります。
Google検索が拾わないのは、「排除」ではなく「信頼性評価の結果」です。
斎藤信者が主張していること(典型的な主張・論点)
支持者・擁護者がSNSなどでよく見かける主張には、以下のようなものがあります:
| 主張 | 内容 | 補足・典型言説例 |
|---|---|---|
| 「マスメディアによる印象操作・捏造」説 | テレビ・新聞は偏っていて、斎藤知事を悪者に仕立て上げようとしている。 | 「マスゴミが嘘をついてる」「報道が都合よく切り取っただけ」など。 |
| 「陰謀・既得権益層の抵抗」説 | 利権・既得権益層や官僚・企業と戦ったゆえに潰されかけた、というストーリー。 | 「斎藤は港湾利権を切ろうとしたから、闇勢力が動いた」など。 |
| 「被害者/誤解されたリーダー」説 | 疑惑・告発はすべて誤解・工作で、真実はSNSで語られている。 | 「実は被害者なんだ」「全部デマだ」「本当の真実は僕らしか知らない」など。 |
| 「報道しない自由を行使している・隠蔽」説 | メディアは“報道しない自由”を行使して、問題点を報じない。 | 「マスメディアは報じない」「都合悪いことは隠してる」など。 |
| 「告発・告発者は悪意・陰謀の道具」説 | 内部告発者や告発文書を「根拠のない噂拡散者」「告発文書は怪文書」と見なす。 | 「噂話を集めた文書」「証拠が添付されていないから無効」など。 |
| 「一般人から受け取った告発文書は公益通報ではない」説 | 一般人から受け取った告発文書を斎藤知事は公益通報と知る由も無かった。 | 「兵庫県警」も公益通報としての受理には至っていない。 |
| 「説明責任は十分に果たした/弁護士に任せたからOK」説 | 疑惑が出ても、代理人弁護士対応で説明しているから問題ない、という主張。 | 「代理人が説明してるからいいじゃないか」など。 |
これら主張は、支持・共感を呼びやすい語調、被害者意識、メディア不信、対立構図の提示などを含み、情緒的な訴えを含むことが多いです。
また、支持者側には「報道されないことこそ真実だ」という逆説的思考が働きやすく、報道・検証が弱いところを“隠蔽の証拠”に転用する傾向も見られます。
公開資料・報道・第三者チェックから見えている“検証可能な事実”/疑義
以下は、一般に公開されている報道・第三者チェック機関・公的文書などによって確認された事実および、疑義が残る点です。
| 項目 | 公開されている事実・指摘 | 補足・不確実な点 |
|---|---|---|
| 公益通報の判断 | 3月20日の一般人から告発文書を受け取り、4月1日に藤原弁護士に相談。その前に通報者探索を行った。 | 斎藤知事は「公益通報者保護法に照らして適法、適正、適切」と発言しているが、そもそも法的根拠無しに通報者探索を行った。 |
| 一般人から受け取っても、知事が「内部職員による告発文書」であると認識していた | 百条委員会で片山元副知事は、「その日の打ち合わせの時に知事から『徹底的に調べてくれ』というお話があったような記憶があります」と証言した。 | その文書が県職員が作成した内部文書(内部告発)との認識で、「一般人」経由で知事に届いたものだったとすれば、実質的には「内部通報」情報を知事が受け取ったことになります。 |
| 第三者委員会が10件のパワハラを認定 | 百条委員会は『パワハラの可能性がある』という指摘にとどめている点も多かったが、第三者委の報告書では『パワハラにあたる』と認定。「嘘八百、公務員失格」もパワハラと認定。 | 斎藤知事は、パワハラを認め謝罪も、一般職員は1件でもパワハラをすれば懲戒処分されますが、斎藤知事は「襟を正す」と言っただけで、自らへの処分はしていません。 |
| 第三者委員会が公益通報者保護法違反を認定 | 告発者を特定した県の対応は公益通報者保護法に違反するとした。 「違法の可能性が高い」などとした県議会調査特別委員会(百条委員会)の調査報告書よりも厳しい内容となった。 | 斎藤知事は、「指摘は真摯に受け止める」と言いながら「当時の対応は適切」と発言し、「最終的には司法の判断」と主張。元県民局長の遺族が裁判を起こさないことを見越した卑怯な態度を取っている。 |
| 消費者庁から技術的助言 | 公益通報者保護法を所管する消費者庁が、知事の記者会見での発言について「庁の公式見解とは異なる」と指摘したうえ、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づき技術的助言をするという前代未聞の異常事態に立ち至っている兵庫県。 | 法を所管する官庁から技術的助言を受けたわけだから、当然、返答しなくてはならない。上脇教授は「どんな返事をしたのかわかる文書やメールを見せて」とお願いした。 しかし県は不存在だという。 |
| 第三者委員会が情報漏洩は知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘。刑事告発 | 兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラなどを告発した元県民局長(昨年7月死亡)の私的情報が漏れた問題で、県の第三者調査委員会は27日、井ノ本知明・前総務部長が県議に漏えいしたとの報告書を公表した。漏えいは、斎藤氏と片山安孝元副知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘。 | 上脇博之神戸学院大学教授は10日、斎藤元彦兵庫県知事、片山安孝元副知事、井ノ本知明元総務部長に対する地方公務員法(守秘義務)違反の疑いの告発状を神戸地検に提出した。 上脇教授は兵庫県在住で、全国82人の弁護士が告発代理人についている。 |
| 公職選挙法違反で刑事告発 | 兵庫県の斎藤元彦知事が再選した知事選を巡り、県内のPR会社にSNSなどによる広報を依頼し報酬を支払ったのは公職選挙法違反(買収、被買収)の疑いがあるとして、弁護士と大学教授が2日、斎藤氏と同社代表に対する告発状を神戸地検と兵庫県警に送付したと明らかにした。 | 当初の告発状では公選法221条1項1号の「買収罪」として告発事実を構成していたのを、221条1項2号の「利害誘導罪」にも該当するということで、再構成した告発事実を追加し、検察官としての起訴事実の構成の選択肢として提示したものです。 |
| 背任容疑で刑事告発 | プロ野球の優勝パレードへの協賛金の見返りに、金融機関の補助金を増額して兵庫県に損害を与えたとして、市民団体が10月9日、斎藤前知事と片山前副知事を背任の疑いで兵庫県警に刑事告発しました。 |
第三者委員会と報道が示した“検証可能な真実”
兵庫県が設置した第三者委員会の報告書では、
- 本件文書には数多くの真実と真実相当性のある事項が含まれており、「うそ八百」として無視することのできないもの、むしろ、県政に対する重要な指摘をも含むものと認められた。
- 本件文書の存在が発覚した後の県の対応には、公益通報者保護法及び指針に違反する通報者探索を行った点をはじめとして重大な問題があった。
としています。
つまり、告発文書に対する県の対応は適切では無かったと言う結論です。
報道各社もこの報告書を基に取材を進めており、「斎藤知事の真実」と言われる情報の多くが、報告書と照らして整合性を欠くことが分かります。
信者的言説が広がる「心理」と「構造」
斎藤信者と呼ばれる層が強固なのは、
- 「敵に攻撃されるリーダーを守る」共同体心理
- SNS上で共鳴し合うエコーチェンバー現象
- 承認欲求とフォロワー数を目的とした投稿行動
などが複合しています。
この構造を理解すれば、SNS上の“真実”は政治的信念ではなく、心理的安心の産物であることが見えてきます。
“真実”を見抜くための3つの視点
- 出典を確認する:報告書・記者会見・公式文書など、一次情報を読む
- 感情ではなく論理で読む:語調より内容の整合性を重視
- 誰が得をするかを考える:発信の動機を見極める
これが、「斎藤知事の真実」を見誤らない最も確実な方法です。
まとめ──「真実」はどこにある?
Googleが上位表示するのは、センセーショナルな投稿ではなく、検証に耐える記録。
「斎藤知事 真実」というGoogle検索が増えるほど、人々は“物語”ではなく“事実”に触れることが出来るのです。
真実はSNSの中には無く、Googleの中にあります。「SNSに真実がある」と言っている斎藤信者は、ネットリテラシーの低さを自ら公言しているようなものです。