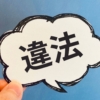東京ファクトチェック協会の「【続報】斎藤知事は公益通報者保護法違反ではない?元局長遺族が給与を自主返納」に反論します
目次
一見「法的措置を取らなかった=処分を受け入れた」と見せかけていますが、実際には社会的背景・心理的圧力・権力の非対称性を無視した極めて一面的な見解
1.「訴訟を起こさなかった=不当処分を認めた」という飛躍
東京ファクトチェック協会の主張は、「訴訟を起こすことが合理的 → 起こさなかった → よって処分は正当だった」という誤った三段論法に基づいています。
実際の法社会学では、
訴訟を起こさない理由は「処分が正当だから」ではなく、「精神的・経済的に争えない」「社会的圧力が強すぎる」「司法が公平に機能しないと感じる」といった理由が大多数を占めることが知られています。
特に公務員が亡くなった後の遺族が県相手に訴訟を起こすのは、精神的にも物理的にも極めて困難です。
2. 公権力 vs 遺族の「圧倒的な非対称性」
兵庫県という行政機関は、法務担当部署・顧問弁護士・広報体制を持つ巨大な権力主体です。
一方、遺族は個人であり、代理人を立てたとしても、その資金的・精神的負担は計り知れません。
また今回のケースでは、
- 告発後に激しい人格攻撃・誹謗中傷があった
- SNS上で「元県民局長は嘘つき」「虚偽告発だ」との拡散が続いた
- 知事本人が「誹謗中傷性の高い文書」と公的に発言した
という状況の中で、遺族が県に対して訴訟を起こせる精神状態ではなかったと推察されます。
これを「訴訟を起こさなかったから正当」と結論づけるのは、被害者側に過剰な自己防衛義務を課す誤った思考です。
3.自主返納の「真意」を都合よく解釈している
東京ファクトチェック協会は「給与返納=処分を認めた証拠」としていますが、実際にはこのような事情も考えられます:
- 県からの**圧力的示唆(暗黙の同意要求)**があった
- 遺族が「これ以上争って注目されたくない」と判断した
- 精神的に限界を超えており、「争う」より「終わらせる」ことを優先した
つまり、返納は“同意”ではなく、“諦め”や“防衛”の結果である可能性が高いのです。
4.「公益通報だったなら訴訟を」と言うのは制度趣旨の誤解
公益通報者保護法の目的は、
「通報者が不利益な扱いを受けないように保護する」ことにあります。
つまり、通報者や遺族に訴訟を起こす責任を課す制度ではないのです。
むしろ、
- 行政機関(=兵庫県)が自律的に調査・是正を行うこと
- 消費者庁などが行政指導を行うこと
が制度の中心です。
訴訟を前提とする考え方自体が、制度趣旨を根本的に誤解しています。
5. 「木村花さん」や「池袋事故遺族」との比較は極めて重要
「木村花さんの母」や「池袋事故遺族」、この二つのケースと今回のケースでは前提条件がまったく異なります。
| 項目 | 木村花さん遺族 | 池袋事故遺族 | 渡瀬元局長遺族 |
|---|---|---|---|
| 相手 | SNS利用者(民間) | 元官僚(個人) | 兵庫県(行政権力) |
| 社会的注目 | 国民的関心 | 高い関心 | 県内限定・メディア沈黙 |
| 支援 | 多くの弁護士・世論の支援 | 弁護士団体の支援 | ほぼ孤立 |
| 攻撃の内容 | SNS上の中傷 | 無責任な言説 | 公権力・県広報・知事発言による社会的圧力 |
| 訴訟のハードル | 比較的低い | 高いが支援あり | 極めて高い(政治的・心理的圧力) |
したがって、渡瀬氏遺族が法的措置を取らなかったのは、合理的に理解できる行動です。
それを「通報ではなかった証拠」と断ずるのは、被害者心理と権力構造を理解しない暴論です。
一見「法的に筋の通った説明」のように見えますが、実際には法的・社会的・倫理的に多くの誤謬を含んでいます
1. 「懲戒処分」と「社会的責任」はすでに別の問題
東京ファクトチェック協会は「給与返納=社会的責任の取り方」と述べていますが、すでに渡瀬元局長は**懲戒処分(職務専念義務違反)**を受けています。
行政処分とは、国家・地方公共団体による制裁の一形態であり、一度それを科された時点で法的・社会的責任はすでに完結しています。
つまり、これ以上の「責任」を求めることは、「二重処罰」に近い道義的圧力であり、公平な法的評価とは言えません。
給与返納は「法的な義務」ではなく、心理的圧力や社会的同調への屈服の結果である可能性を排除できません。
2. 「訴訟を起こさなかった=非を認めた」は誤った法解釈
法治国家では、確かに「不服があれば裁判で争う」ことは制度上の原則ですが、それは法的手段が利用可能であるという前提のもとでの話です。
現実には、次のような理由で訴訟を断念する人は数多く存在します。
- 精神的に消耗し、争う意欲を失っている
- 相手が行政機関であり、**圧倒的な権力差(非対称性)**がある
- 裁判を起こすことによる社会的バッシングを恐れている
- 「司法が公平に扱ってくれる」と信じられない
実際に、行政処分を争う人はごく少数です。
「訴訟を起こさない=正当性を認めた」というのは、被害者の沈黙を“同意”と誤解する典型例です。
3. 「百条委員会」「第三者委員会」での認定が決定的
元局長の行為は、すでに
- 兵庫県議会 百条委員会
- 兵庫県設置 第三者委員会
の両方で、公益通報の可能性がある、またはその性質を有すると認定されています。
つまり、制度上の公的機関が「通報としての性質を有していた」と判断しているのです。
この時点で、
「職務中に私的な誹謗文書を作成した」
という東京ファクトチェック協会の断定は、公的調査結果に反する虚偽的な断定になります。
4. 遺族の行動は「諦め」や「防衛」であって「認定」ではない
元県民局長の遺族は、知事支持層や一部メディアからの執拗な誹謗中傷・人格攻撃を受けています。
そのような状況下で、訴訟という長期的で過酷な手段を選ぶことは、精神的に不可能に近いものです。
むしろ、「これ以上争えばさらに叩かれる」と感じ、**「終わらせるための選択」**として自主返納に応じた可能性が高いと考えられます。
この行動を「正当性の認定」とするのは、被害者心理への著しい無理解です。
5. 「法的確定」と「真実の確定」は別次元の問題
行政処分が「確定」しているからといって、それが真実に基づいた正当な処分とは限りません。
法律上の確定とはあくまで「形式的な手続の終結」であり、真実の探求・倫理的評価とは別次元です。
公益通報者保護法の目的は、「通報者が報復されないように守ること」であって、「通報者が訴訟を起こすことを前提に保護する制度」ではありません。
したがって、
「訴訟を起こさなかった=通報ではない」という結論は、法制度の趣旨を根本から誤解した暴論です。
東京ファクトチェック協会の主張には、公益通報制度の趣旨・運用・判例の理解が決定的に欠けている
1. 「批判的記載がある=誹謗中傷」ではない
公益通報の多くは、組織内の不正や不適切な行為を明らかにするものであり、その性質上、関係者に対する批判的内容を含むのは当然です。
消費者庁の公式資料でも、
「通報内容が上司や組織の行為を批判的に記載することをもって、直ちに誹謗中傷とみなすことはできない」
(※消費者庁「事業者における通報対応に関するQ&A」より)
と明記されています。
したがって、「批判的記載=誹謗中傷」と短絡的に結びつける東京ファクトチェック協会の主張は、
公益通報の本質を完全に誤解した見解です。
2. 「送付先10か所から相手にされなかった」は事実誤認
東京ファクトチェック協会は「送付先10か所すべてから相手にされなかった」と断じていますが、
これは明確な誤りです。
実際には、取材報道メディアのひとつである SlowNews(スローニュース) の報告によれば:
「真実であった場合に影響の大きい⑥『パレードの協賛金』、⑦『パワハラ』、そして場合によっては④『贈答品』を中心に取材を進め、事実が確認されれば報道するかどうかを判断しようと考えた。」
「【新連載】兵庫“メディアの敗北”の真相② 「怪文書」にも見えた内部告発をどう扱ったのか」
https://slownews.com/n/n7ae34a35ab5c(出典:スローニュース 2025年4月16日)
つまり、複数のメディアが内容の真偽を検証する姿勢を示していたという事実が存在します。
「相手にされなかった」という断定は虚偽です。
3. 知事自身が「内部情報である」と認識していた
斎藤知事は、一般人から文書を受け取った時点で、その内容や文体・人事情報の詳細さから
「県の人事に精通している人物が作成したもの」と発言しています。
これは、知事自身が内部者からの通報(内部告発)である可能性を認識していたことを意味します。
つまり、公益通報の可能性を前提として対応すべき立場にあったにもかかわらず、通報者の探索を指示したこと自体が、公益通報者保護法の趣旨に反します。
4. 第三者委員会が「真実相当性」を認定している
兵庫県が設置した第三者委員会は、調査報告書の中で以下のように評価しています:
「文書の一部には事実に基づく内容が含まれており、その作成・配布の動機を直ちに不正目的と断定することはできない。」
つまり、委員会自体が**「怪文書」ではない**ことを認めています。
それにもかかわらず、東京ファクトチェック協会が「誹謗中傷性が高い」「怪文書」と断定するのは、
公的調査結果を否定する恣意的な評価です。
5. 公益通報に「証拠の添付」は必要条件ではない
公益通報者保護法では、通報時に「証拠資料」を添付することは義務付けられていません。
むしろ、次のような事情から、証拠を持ち出さない方が適切な場合もあります。
・内部資料を無断で持ち出すと守秘義務違反になる
・公益目的であっても守秘義務違反で懲戒処分を受けるおそれがある
したがって、通報者は通常、「合理的な根拠に基づき通報した」と判断されれば十分です。
消費者庁も明言しています:
「通報者が直接証拠を有していなくても、信頼できる情報源や複数の状況証拠に基づく通報であれば保護対象となり得る。」
つまり、証拠の添付がないことを理由に「公益通報ではない」とするのは制度趣旨の誤解です。
6. 「自主返納=公益通報ではない」は論理のすり替え
給与返納は、あくまで遺族が「これ以上騒動を長引かせたくない」と考えて行った可能性が高く、法的な認定や公益性とは無関係です。
第三者委員会と百条委員会の双方で「公益通報としての性質があった」または「真実相当性が認められる」
と判断されている以上、給与返納という行為をもって公益通報性を否定するのは論理的に破綻しています。
東京ファクトチェック協会の文章には、事実誤認や論理のすり替えが複数含まれています
1.「給与返還に関しては公金の問題」「都合が悪くなったら怪文書をばら撒く」
→ 事実誤認です。
兵庫県の監査結果では、
「当該ファイルの編集時間から、業務外の記述時間を特定することは不可能であるため、返還請求を実施しないことに違法・不当な点はない」と明確に記載されています。
つまり、不正支出と認定されていないため、給与返還の義務はありません。
「公金問題」や「服務規律違反による返還責任」という主張は、県の正式判断と矛盾します。
2.「怪文書をばら撒き、政治家を殺す」
→ 印象操作・事実の歪曲です。
元県民局長が作成した文書は、誹謗文書ではなく、**具体的事実を基にした内部告発文書(公益通報の要件を満たす可能性がある)**です。
また、第三者委員会の調査報告書やメディア報道では、
・文書の内容に「虚偽」とされた部分は確認されていない
・むしろ、県の対応(通報者探索・処分過程など)に法令上の問題が指摘されている
とされています。
したがって、「怪文書」や「政治家を殺した」などの表現は不当なレッテル貼りに当たります。
3.「中田宏氏の怪文書事件」との比較
→ 事例の性質が全く異なります。
中田元横浜市長の件は、完全な匿名の第三者が、虚偽内容を含むビラを撒いた 名誉毀損事件 です。
一方、兵庫県の文書問題は、県庁内の実務経験者が、組織運営上の不正や違法の疑いを記した 内部告発文書。
したがって、性質が異なるため、「同様の先例」とするのは**ミスリード(誤誘導)**です。
4.「メディアが政治家を陥れる」論
→ 根拠のない陰謀論的主張です。
日本の主要報道機関(NHK、朝日、毎日、読売、神戸新聞など)は、いずれも独自の取材・裏付けに基づいて報道しており、特定の「思想」で白黒を逆転させるような報道は存在しません。
むしろ、報道が継続されているのは、
・斎藤知事側の説明が二転三転している
・公益通報対応や記録管理に疑義が残る
・県民からの説明責任要求が続いている
からです。
【まとめ】
東京ファクトチェック協会の論理構成は、
- 行政権力に極めて有利に働き、
- 被害者に不当な「立証責任」と「行動義務」を押しつけ、
- 「通報者の沈黙」を「加害者の正当化」に転用する
という二次加害的構造を持っています。
「ファクトチェック」と称しているにもかかわらず、公的調査の結論を軽視し、遺族の状況を無視する点で、中立性・客観性を欠いた政治的論評と評価せざるを得ません。
東京ファクトチェック協会の主張は、
- 公益通報制度の法的理解に誤りがあり、
- 公的調査結果を無視し、
- 権力側の主張を代弁する形で被通報者を正当化しようとする内容になっています。
元県民局長の文書は、
「誹謗中傷文書」ではなく、「組織的不正に関する内部情報を含む公益通報文書」であり、その評価は第三者機関によっても裏付けられています。
| 主張 | 実際の事実 |
|---|---|
| 元県民局長文書は「怪文書」 | 真実相当性のある公益通報文書 |
| 給与返還は「公金問題」 | 監査結果で返還不要と判断済み |
| メディアが政治家を「殺した」 | 報道は事実に基づく公的監視活動 |
| 中田宏氏の件と同様 | 全く性質の異なる事案(虚偽ビラ vs 公益通報) |
このように、「そっとしておいてほしい」に同情を引きつけながら、本質的な問題(知事側の不透明な対応)をぼかす手法は、世論誘導・印象操作の典型的な構成です。