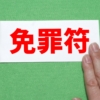兵庫県庁で進む組織の劣化──知事不祥事と現場士気低下の深刻な連鎖
最近、兵庫県から届いた「ふるさとひょうご寄附金」への御礼状が、驚くほど稚拙な文章だったことが話題になっています。
文面の不自然さや形式の乱れは単なる誤りではなく、兵庫県庁という組織全体の劣化を象徴しているように見えます。
背景には、知事による一連の不正疑惑や不祥事対応の不誠実さがあり、県職員のモチベーションが急速に低下している現実があるのではないでしょうか。
目次
不祥事の連鎖が止まらない兵庫県政
兵庫県庁では、ここ数年で以下のような深刻な問題が次々に発生しています。
- 知事らによる公益通報者保護法違反の疑い
- 斎藤元彦知事が4件の刑事告発を受けている事実
- 県職員による立花孝志氏への個人情報漏洩事件の放置
- 県広報公式アカウントへの不正アクセス事件
- 知事肝煎り事業「はばタPay+」での個人情報流出
これほど多くの問題が同時期に起きている自治体は全国的にも異例です。
しかも、どの案件についても明確な説明責任がなされていないことが、県政への信頼を大きく損なっています。
御礼状に表れた「行政の劣化」
ふるさとひょうご寄附金に対して送られた御礼状は、本来ならば全国の寄付者への感謝と信頼を伝える重要な公式文書です。
ところが今回の書面には、以下のような問題が見られます。
- 文体が統一されておらず、推敲不足が明らか
- 改行・段落構成が崩れ、行政文書としての体裁を欠く
- 表現が重複し、意味が曖昧
- 「未筆ながら」など古風な言い回しが文体と噛み合わない
これらは単なる「ミス」ではなく、職員の緊張感や目的意識が失われている兆候と見るべきです。
かつての兵庫県庁なら、こうした文書は複数のチェックを経て修正されていたはずです。
組織内部で何が起きているのか
不祥事が続くと、行政組織には次のような悪循環が生まれます。
- 士気の低下
正しい行動が評価されず、職員が萎縮する。 - 責任回避の蔓延
リスクを取らず、何もしないことが最善になる。 - チェック機能の麻痺
内部通報が握り潰され、改善が止まる。 - 形式主義の横行
形だけの文書・広報が増え、県民との信頼関係が薄れる。
つまり、現場の努力よりも「知事に逆らわないこと」が優先される空気ができあがるのです。
「もう持たない」兵庫県庁
兵庫県庁は約7千人の職員を抱える大組織です。
現場には依然として優秀で真面目な職員が多く、行政サービスそのものは辛うじて保たれています。
しかし、トップの姿勢が変わらないままでは、
「この組織では正しいことをしても報われない」
と感じる職員が増え、優秀な人材の離脱や行政判断の停滞が起きるのは時間の問題です。
第1段階:士気の低下と沈黙の蔓延(現在進行中)
特徴
- 職員が「何を言っても変わらない」と感じ、改善提案や異論を控えるようになる
- ミスを見つけても報告しない
- 上層部の指示に形式的に従うだけの“受け身行政”が常態化
影響
- 文書・広報・答弁などに「魂の抜けた言葉」が増える
- 調査・報告書などが「誰の責任でもない内容」に終始する
- 現場の活力が失われ、行政サービスの質が低下
現在の御礼状のような“形式だけの文書”は、この初期段階の典型です。
第2段階:中間層の崩壊と忖度の制度化
特徴
- 管理職層がトップの意向を忖度し、現場との間で「防波堤」ではなく「伝声管」になる
- 不正や不具合の報告が途中で握りつぶされる
- 県民対応よりも「知事の機嫌取り」や「見せ方重視」の施策が優先
影響
- 職員間の信頼関係が壊れ、縦割り・派閥化が進行
- 不正を指摘した職員が孤立または排除される
- 公益通報制度が事実上機能しなくなる
この段階では、組織の「倫理観」が失われ、腐敗が内側から進む状態になります。
第3段階:優秀人材の流出と“失敗を恐れる組織文化”の固定化
特徴
- 真面目な職員ほど疲弊し、他自治体や民間へ転出
- 残るのは「空気を読む人」「責任を取らない人」だけになる
- 県庁内での人材育成やノウハウ継承が滞る
影響
- 政策立案力の低下(外部コンサル頼みの県政へ)
- 行政判断のスピードと質が低下
- 市町や県民との信頼関係が修復困難になる
この段階に入ると、組織は**「縮小均衡」**に陥り、存在意義を見失います。
第4段階:ガバナンスの崩壊と行政不全
特徴
- 情報漏洩・不正アクセス・会計処理の不備など、管理系統の異常が頻発
- 不祥事が発覚しても責任を取る者がいない
- 組織内で恐怖と無関心が同居する
影響
- 外部監査・議会・マスコミの信頼を完全に喪失
- 職員の中に「もう終わった」との諦めが広がる
- 知事交代や大規模リストラ以外では再建不可能になる
この状態を「行政の機能不全」と呼びます。外形的には業務が続いていても、実態は**「命令が通らない、責任も取らない組織」**です。
第5段階:県民からの信頼崩壊と自治体ブランドの失墜
特徴
- 県民が県政に期待しなくなる
- 「兵庫県に任せるより民間でやった方が早い」との風潮が定着
- 優秀な人材が兵庫県庁を志望しなくなる
影響
- 予算規模が縮小し、地方交付税頼みになる
- 他府県との連携も弱まり、県の影響力が低下
- 結果的に、兵庫県が「衰退県」として扱われるようになる
崩壊を食い止める唯一の道
崩壊の進行を止めるには、トップ自らが透明性を取り戻すしかありません。
- 自身に関する告発・不祥事について説明責任を果たす
- 公益通報制度を尊重し、内部告発者を守る姿勢を示す
- 職員を信頼し、「現場が主役の県政」へ舵を切る
これができなければ、どれほど優秀な職員がいても、兵庫県庁の信頼は回復しません。
立て直すために必要なこと
兵庫県が信頼を取り戻すためには、以下の3点が不可欠です。
- 透明性の回復
公益通報や情報漏洩の対応を、第三者の監視下で公開。 - 職員の声を吸い上げる仕組みの再構築
「言っても無駄」という空気を壊し、現場が自由に意見できる体制を。 - 知事自身の説明責任と自浄姿勢
過ちを認め、県民に正直に説明する姿勢こそが最大の信頼回復策。
結論
兵庫県庁の組織劣化は、まだ「崩壊」には至っていません。
しかし、斎藤知事による不正や説明回避が続けば、現場の士気は確実に限界を迎えます。
今こそ県民と職員が声を上げ、**「真面目な職員が報われる県政」**を取り戻す時です。
行政組織を守るのは、最終的には内部の人間と県民の信頼の力です。
斎藤知事がこのまま「ごまかしと自己保身の政治」を続けるなら、
兵庫県庁はゆっくりと、しかし確実に崩壊していくでしょう。
それは突然の事件ではなく、
文書の質の低下、説明責任の放棄、職員の沈黙――
そんな日常の中で静かに進む“組織の死”です。