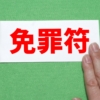斎藤元彦知事に見られる「正常性バイアス」──危機を軽視するリーダーが兵庫県にもたらすリスク
「正常性バイアス(normalcy bias)」とは、危険や異常事態が起きても「大したことはない」「自分だけは大丈夫」と過小評価してしまう心理傾向を指します。
人間が心の平穏を保つための防衛反応ですが、組織や社会を率いるリーダーに強く現れると、危機を軽視し、対応を誤る致命的な欠陥となります。
斎藤知事に見られる正常性バイアスの兆候
本日、国交省で開催された「命と生活を守る新国土づくり研究会」に会長として出席しました。気候変動により風水害の激甚化・頻発化が進み、今夏のような記録的渇水も起きています。県民の命と暮らしを守り、農林水産業を支えるためには、河川やダム、ため池等の治水対策が重要です。会議では二つの提言… https://t.co/kXAxLpOjv2 pic.twitter.com/ihRIX8zuiH
— 兵庫県知事 さいとう元彦 (@motohikosaitoH) October 28, 2025
表向きの発言と現実との乖離
斎藤知事の投稿文を見ると、「命と生活を守る」「災害対策を強化する」といった言葉が並びますが、実際の行動と体制を見ると、そのメッセージとは裏腹です。
幹部用公舎への入居を拒否し、県庁まで20分以上離れた場所に居住しているという事実は、災害発生時に迅速に指揮を執る責任者としての自覚の欠如を示しています。
これは、単なる「ライフスタイルの自由」ではなく、県民の安全を左右するリスク管理上の問題です。
県のトップが災害対策本部に即座に駆けつけられない状況を容認している時点で、「県民の命と暮らしを守る」という発言の説得力は失われます。
自宅住所を隠し、登庁時間を軽視
災害時の初動対応において、知事の迅速な判断と現場指揮は極めて重要です。
しかし、斎藤知事は「プライバシー」を理由に公舎入居を拒否し、自宅の所在地もごく一部の職員しか知らないとされています。
これは「自分の任期中は災害が起こらない」といった楽観的な認識に基づく判断とも考えられます。
初動対応の遅れによる致命的リスク
災害対策本部の設置が遅れる
災害発生時、都道府県では**知事が本部長となる「災害対策本部」**を設置します。
しかし知事が登庁しなければ、本部の設置や指示が遅れ、
- 避難指示・警戒区域指定
- 自衛隊への災害派遣要請
- 被災自治体との情報共有
など、県全体の判断が遅滞します。
特に、**兵庫県のように広い県域では「30分の遅れが数百人の被害差を生む」**と言われます。
指揮系統の混乱と現場の停滞
現場が独断で動けない
知事がいない間、部局長や危機管理監が暫定対応しますが、
法的・政治的に判断が伴う案件(例:避難命令、自衛隊要請、国への緊急支援要請など)は知事の決裁が必要です。
結果、現場が「判断待ち」の状態となり、時間だけが過ぎていきます。
情報の錯綜と信頼低下
県庁内で「知事がどこにいるか分からない」「登庁予定が不明」などの混乱が生じると、
報道・市町村・国機関への情報伝達にもズレが生じ、行政への信頼そのものが揺らぎます。
県民への情報伝達の遅れ
災害時、知事は県民に対して安心と信頼を与えるリーダーの象徴です。
- 会見・緊急メッセージの発信
- SNSや防災無線での呼びかけ
- 報道機関への方針説明
これらが遅れることで、住民は「避難すべきか」「どこが危険か」を判断できず、
避難の遅れ・誤判断による犠牲者の増加につながります。
市町村との連携不全
兵庫県のように地形が多様な県では、各地で同時多発的に災害が発生する可能性があります。
知事が不在のままでは、
- 市町長からの支援要請に即応できない
- 被害状況を国に報告できない
- 物資・救助隊の広域調整が止まる
というように、県庁が「支援の司令塔」として機能不全に陥るリスクがあります。
「政治的責任」と「法的責任」の発生
知事が迅速に登庁できず、結果として被害が拡大した場合、
- 災害対策基本法による「防災責務違反」
- 行政の不作為による「国家賠償請求」
- 議会や監査による「政治的責任追及」
といった法的・政治的リスクも生じます。
特に兵庫県は阪神・淡路大震災の経験県として、
「トップの初動が遅れることの恐ろしさ」を誰よりも知っているはずです。
それにもかかわらず、現職知事が県庁から遠く離れた場所に住み、
災害時の登庁体制を軽視しているとすれば、県民の安全を根底から脅かす行為です。
情報漏洩問題とSNS投稿の軽視
はばたんPay+の情報漏洩では、知事自らが定例会見を中止するなど、説明責任を回避する姿勢が見られました。
また、高校生20名との写真をSNSに投稿し、個人情報特定リスクを軽視した点も問題視されています。
「自分の発信は安全で正しい」という過信が、リーダーとしての危機感の欠如を示しています。
違法行為の指摘を“対応は適切”と片付ける
公職選挙法違反・守秘義務違反・公益通報者保護法違反などの疑惑に対し、知事は「対応は適切」「指示していない認識」と一蹴。
第三者委員会の報告にも向き合わず、「自分は正しい」と思い込む態度は、典型的な自己正当化+正常性バイアスの表れといえます。
正常性バイアスがもたらす危険な未来
危機対応の遅れ
災害・情報漏洩などの初動対応が遅れ、被害を拡大させる恐れ。
組織のモラル崩壊
現場職員が「報告しても無駄」と感じ、問題隠蔽が常態化。
県民の信頼喪失
説明責任を果たさないことで、県政全体への不信感が深まる。
直接的被害の拡大
災害・個人情報流出・行政判断ミスなど、県民の生活に実害が及ぶ。
必要なのは「知事個人の正常性」ではなく「制度の安全弁」
正常性バイアスの強いリーダーを抑制するには、個人の良識に頼るのではなく、制度的な安全装置が必要です。
- 第三者による危機管理評価制度の導入
- 議会・監査機関の独立性強化
- 情報公開制度を活用した県民監視
- 専門家・メディアによる継続的な検証報道
兵庫県に求められるのは、「信頼できる危機管理体制」と「知事の自己正当化を止める仕組み」です。
斎藤知事の正常性バイアスを放置すれば、いつか「取り返しのつかない悲劇」を招く可能性があります。
まとめ
斎藤知事の行動は、正常性バイアスの典型例といえます。
「自分は大丈夫」「問題は大したことではない」という思い込みが続く限り、県政は健全性を失い、県民の安全も脅かされかねません。
今こそ、トップの心理的傾向を冷静に分析し、制度と社会の力でリスクを制御する必要があります。