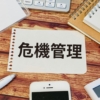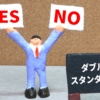斎藤知事の「名前を出す/出さない」戦略:はばタンPay+で業者名を公表しながら、都合の悪い人物は沈黙する理由
目次
斎藤知事が名前を「出す人」と「出さない人」
囲みの記者会見で、斎藤知事は
- はばタンPay+の委託業者2社の名前
- 定例会見の日程変更を依頼した県議会議員2名の名前
を自ら口にしました。
一方で、
- 昨年の知事選で“2馬力選挙”を行い、デマ拡散を指摘された立花孝志氏
- 知事の遠足や私的活動をYouTubeで配信している**「ふくまろネットニュースチャンネル」**
については、どんな場面でも一切名前を口にしません。
この「名前を出す/出さない」の使い分けこそ、斎藤県政の危うさを象徴しています。
「犬笛政治」とは何か
政治学では、特定の支持層だけに届く暗号的メッセージを「犬笛(ドッグホイッスル)」と呼びます。
表向きは無害に聞こえても、実際は支持者や信者に「誰を攻撃すべきか」を示す役割を持つものです。
斎藤知事が特定の企業や議員の名前を出すと、SNS上でその相手が攻撃される構図が見られます。
逆に、「ふくまろ」や「立花孝志氏」など自らの選挙や広報に関わる人物は徹底的に守られる。
この二重構造が「斎藤知事は身内を守り、外部を攻撃させる」という印象を強めています。
切り捨てられた側近たち
かつて信頼を寄せていた
- 折田楓氏
- 井ノ本元総務部長
といった人物を都合が悪くなると切り捨てた前例もあります。
このような“忠誠の不安定さ”は、組織内に恐怖と不信を生みます。
結果として、
「次は自分が切り捨てられるかもしれない」
という空気が職員や側近の間に広がり、庁内の士気を下げる原因になります。
内部崩壊のリスク:忠誠の基盤が“理念”ではなく“利害”に偏るとき
政治心理学的に見ると、斎藤知事の支持構造は理念ではなく利害によって成立しています。
つまり、「予算」「人事」「ポスト」などの利害が揺らぐと、一気に支持が崩れるリスクがあります。
このようなリーダーシップを「防御型リーダーシップ」と呼びます。
防御型リーダーの組織では、批判を恐れて情報が上がらず、問題が表面化した時には既に手遅れという事態が多く発生します。
予測される今後の展開(比喩的な“身内から刺される”)
現実的に起こり得るのは、暴力ではなく政治的・組織的な裏切りです。
| 想定されるシナリオ | 内容 | 発生可能性 |
|---|---|---|
| 内部告発・リーク | 内部からの文書・証言が外部に流出 | ★★★★☆ |
| 支持者離反 | 元支援者や関係企業が距離を置く | ★★★☆☆ |
| 庁内の消極的抵抗 | 職員が形だけの対応しかしなくなる | ★★★★★ |
| 政治的孤立 | 議会・財界の支持が減退 | ★★★★☆ |
すでに、庁内文書の劣化や説明責任の軽視などにより、**「消極的抵抗」**が進行している兆候が見られます。
対立構造を作る理由:説明できないことを「敵味方」でごまかす
普通の行政トップなら、批判を受け止めて説明することで信頼を維持します。
ところが、斎藤知事は「敵」と「味方」をはっきり分け、敵には攻撃的に、味方には徹底的に甘く接する傾向があります。
これは、自分の行動を正当化できないから、説明の代わりに“敵を作って戦う構図”にすり替えていると見るのが自然です。
つまり、「説明責任」ではなく「攻撃で目をそらす」戦略です。
政治心理学から見た行動パターン
この行動は、政治心理学的に「投影型防衛機制(projective defense)」と呼ばれるものです。
簡単に言うと──
自分の中にある“やましさ”や“不安”を、他者に投影して攻撃することで心の安定を保つ
という心理です。
たとえば:
- 情報漏洩問題の責任を問われると → 委託業者の名を出す(責任転嫁)
- 公選法違反疑惑を問われると → 「適法の認識に変わりはない」と強弁
- パワハラ認定を受けても → 「襟を正せば問題ない」と開き直る
この一連の言動は、「自分の過失を直視できない人間が、他者を攻撃して均衡を保つ」典型的なパターンです。
支持層を維持するための「分断政治」
もう一つの狙いは、“敵”を設定することで支持者を結束させることです。
斎藤知事の周囲には、いわゆる“信者的支持層”が存在しますが、その結束は政策への共感ではなく「敵を共有する感情」で成り立っています。
「批判している人=悪」
「知事を攻撃する人=県の敵」
という単純な構図を作り出すことで、支持層を心理的に支配しているわけです。
この手法はトランプ大統領や一部のポピュリズム政治家にも共通して見られる「分断による支配」です。
長期的には「自滅型リーダーシップ」
短期的には敵を作ることで一時的な支持を得られますが、
長期的には次のような弊害が生まれます。
- 庁内で意見が言えなくなり、問題が隠蔽される
- 側近が離反し、内部告発が起こる
- 支持者が疲弊し、信頼を失う
- 最終的に孤立化する
つまり、「敵を攻撃して守る」構造は、やがて自分自身を蝕む自己防衛の罠になります。
説明責任を果たせないリーダーの典型
「普通の人から見ればメリットがない」というのはまさにその通りで、合理的な戦略ではなく、心理的防衛反応としての行動だと考えられます。
「説明できない不正や矛盾を抱えているリーダーほど、敵を作りたがる」
──これは多くの歴史的事例で共通する構図です。
結論:孤立への道を歩む知事
「身内から刺される」と言うよりも、
**「身内が静かに離れていく」**という形で、
最終的には政治的孤立に向かう可能性が高いと考えられます。
組織の信頼は、恐怖ではなく共感によって維持されるものです。
信者的な支持層に頼る“犬笛政治”を続ける限り、兵庫県政は内部から崩壊していくでしょう。