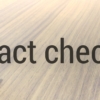“言葉を失った知事”──11月4日会見が示した統治崩壊の瞬間
目次
「下校の時間です」──行政トップが発した異例の言葉
2025年11月4日の兵庫県定例記者会見。
その場面はあまりにも象徴的だった。
「そろそろ、あのー、下校の時間にもなっておりますので、ご理解頂きたいと思います。」
行政の長として、定例会見の場で「下校の時間」という表現が出た瞬間、会見は公的説明の場から逃走を図る知事の姿を浮き彫りにした。
質問と答弁の“論理”が完全に崩壊
この日の知事の答弁には、一貫した論理構造が存在しなかった。
- 「いつ判断したか」と問われて「適法・適正」と答える
- 「どの選挙を指すのか」と聞かれて「制度一般の話」にすり替える
- 「立場を変えたのか」と問われても「時代の流れ」
- 「立花氏の関係は?」と問われて「意味が分からない」
質問と答えが全くかみ合わない、コミュニケーションの断絶。
これは単なる不誠実さではなく、説明能力そのものの喪失を示している。
“適法・適切・適正”という壊れたレコード
知事の答弁に繰り返し登場する3つの言葉——
「適法」「適切」「適正」
これらは、本来「行動の根拠」を説明するための語である。
しかし、繰り返されるたびに中身は空洞化し、質問への回答ではなく、自己防衛の呪文となっていった。
この「言葉の形骸化」こそ、信頼崩壊の最終段階である。
もはや“政治”ではなく“自己防衛”の会見
この会見で知事が行っていたのは、説明ではなく防御だった。
どの質問にも「反論」も「否定」もなく、ただ「定型文を繰り返す」ことで沈黙を装う。
しかし、その沈黙はもはや“冷静な対応”ではなく、説明できない自分を守るための殻だった。
権威の崩壊:言葉を失うということ
政治学者マックス・ウェーバーは、権力の正統性を支える「合法的支配」(合法性・合理性)および「カリスマ的支配」(信頼性に近い意味でのカリスマへの帰依)を挙げた。
斎藤知事の会見では、
- 「合法性」──公益通報者保護法違反を“適法”と主張
- 「合理性」──質問に答えず、論理の欠如
- 「信頼性」──虚偽説明と矛盾の積み重ね
このすべてが崩壊した。
それでもなお職に留まることは、もはや制度上の空洞化に等しい。
理性的な県民は、すでに気づいている
前回の選挙で斎藤知事に投票した県民の多くは、「斎藤さんはハメられた」「斎藤さんは悪くない」「改革への期待」というイメージで支持した。
しかし、今回の会見で見えたのは、説明できない・反省しない・誤魔化すだけという現実。
信者的な支持層を除けば、常識ある県民なら誰しも「もうこの人ではダメだ」と感じたはずだ。
この会見は、政治的立場を超えた“理性の分岐点”となった。
結論:兵庫県政の“言葉による統治”は終わった
民主主義の根幹は「言葉で説明し、納得を得ること」。
だが、11月4日の会見では、知事は質問を理解できず、言葉を正しく使えず、最後は「下校の時間」と言って逃げた。
行政トップが言葉を失ったとき、政治は終わる。
兵庫県政は今、政策の是非ではなく、「言葉を取り戻せるかどうか」の瀬戸際にある。