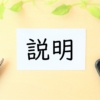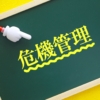「共感」から「沈黙」へ──立花孝志氏を語らない斎藤元彦知事に残る“思想的一体感”
立花孝志氏の「自供」が兵庫県政を直撃する可能性
──「コメント控える」では逃げ切れない重大局面へ
2024年の兵庫県知事選後に放送されたインターネット番組で、斎藤元彦知事がNHK党代表・立花孝志氏と出演し、「共感させていただいた」と発言していた映像が再び注目を集めています。
名誉毀損容疑で逮捕された立花氏に対して、知事は現在「コメントを控える」と繰り返しています。
しかし、過去の「共感」発言を撤回しないままの沈黙は、県政トップとしての政治倫理が問われる重大な問題です。
公益通報の問題とか内部告発の問題について、ご自身がやられたという観点から、すごく問題点の本質をとらえておられるな、というのが、私が思っていたことと同じことを立花さんがおっしゃっていたので、そこはすごく共感させていただいたことがありますね
「斎藤元彦氏、立花孝志氏の印象語る「公益通報の問題点の本質をとらえておられる」立花氏は謝罪」
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202411180000036.html?Page=2(出典:日刊スポーツ 2024年11月24日)
目次
選挙直後に語った「共感」の言葉
番組司会者が「立花さんに一言」と促すと、斎藤知事は次のように答えています。
「最初の出会いはJCの討論会でした。それまで存じ上げていなかったんですが、リハックさんの討論会のときに公益通報や内部告発の問題について、すごく本質を捉えておられると感じた。私が思っていたことと同じことを立花さんがおっしゃっていたので、共感させていただいたことはあります。」
この発言は単なる挨拶ではなく、「問題の本質を捉えている」「自分と同じ考え」と明確に述べており、思想的な一致を認めた発言といえます。
立花孝志氏の応答:「斎藤知事を守った」と明言
立花氏は続けてこう発言しました。
「あの状態ではああするしかなかった。それをしないと犯罪が広がっていた。
斎藤知事がやったことが違法だと言う人たちが信じられなかった。」
つまり、当時問題視されていた「文書問題」における知事の行動を正当化し、擁護しています。
斎藤知事はこれを訂正も否定もせず、頷きながら聞いていました。
結果として、「立花氏の価値観を受け入れた」構図が成立しています。
現在の発言:「コメントを控える」に転じた理由
2025年11月、立花氏が名誉毀損容疑で逮捕されました。
この件に対し、斎藤知事は記者団にこう述べています。
「報道で承知しておりますが、捜査に関することもありますので、私からコメントを控えたい。」
「共感」から「沈黙」へ。しかし、過去に思想的に一致していた相手が逮捕されても、何も説明しないのは不自然です。
この沈黙は、「過去の共感を撤回できない」「否定すると矛盾が生じる」という政治的ジレンマの表れです。
なぜ否定できないのか?3つの仮説
① 共感の根が“思想的同一性”だった
両者とも「内部告発の問題」や「犯罪との闘い」を強調してきました。
その構造的共通点が、単なる政策論を超えた“感情的共鳴”を生みました。
② 立花氏が“知事にとって不都合な情報”を握っている
知事選では「二馬力選挙」と呼ばれる協力関係が問題視されました。
もしその裏付けとなる証拠(会議記録・映像・通信履歴など)を立花氏側が保持していれば、知事は否定できません。
③ 「否定=過去の自己否定」になる
「立花氏の考えに共感した」と語った以上、今になって否定すれば「当時の自分が誤っていた」と認めることになる。
政治家としての一貫性を失う恐怖が、発言を封じています。
「沈黙」が生む倫理的責任
もし本当に立花氏の言動を問題視しているなら、知事として明確に次のように述べるべきです。
「当時の発言は不適切でした。誹謗中傷に繋がる行為には一切賛同できません。」
それを避けている限り、「今も同じ思想を共有しているのではないか」という疑念は消えません。
政治家にとって、沈黙もまた“メッセージ”です。
この沈黙が長引くほど、県政の倫理的信頼は揺らぎます。