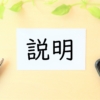兵庫県知事・斎藤元彦氏、11月11日定例会見でも「質問ゼロ回答」連発——問われる説明責任とリーダーの資質
目次
質問に「YES/NO」で答えない異常な会見構造
選挙ウォッチャーちだい氏の質問は、非常に明確でした。
「関係しているのか?」「黒幕だと思っていたのか?」「おねだりやパワハラは無かったのか?」——いずれもYESかNOかで答えられる単純な質問です。
しかし斎藤知事は、いずれの質問にも直接答えず、一般論・抽象論でかわす答弁を繰り返しました。
たとえば「関係しているのか?」と問われて「捜査中なのでコメントを差し控える」と繰り返すのは、法的リスクを回避する答え方ではありますが、政治家としては「疑惑を深めるだけ」の最悪の対応です。
「捜査中なのでコメントできない」は政治家の“安全弁”であり“逃げ道”
刑事事件などの捜査が進行している場合、関係者が不用意な発言をすると「捜査妨害」や「証拠隠滅」とみなされる可能性があります。
そのため、官僚や企業広報ではよく使われる常套句です。
しかし、今回の件は一般的な刑事事件の当事者コメントではなく、「県政をともに担ってきた県議が、自殺にまで追い込まれた問題」です。
しかもその背景には、知事自身が関係した「内部告発の扱い方」や「県政内の力学」があると報道されている。
つまり、これは県の組織問題であり政治問題です。刑事捜査を理由にコメントを差し控えることは、むしろ「政治的責任」から逃げていると見られるのが当然です。
「捜査中」は法的には理由にならない
法律的には、「捜査中であるからコメントできない」という義務は存在しません。
刑事訴訟法にも地方自治法にも、知事が捜査中の事案に関して意見を述べてはならないという規定はありません。
むしろ、公共団体の長としては、
「亡くなられた県議の死を重く受け止め、県としても原因の究明と再発防止に全力を挙げる」
という声明を出すことこそが、本来の行政責任の取り方です。
そのようなコメントを避け、「捜査中だから差し控える」というのは、法律の盾を使った説明責任の放棄に過ぎません。
「沈黙は中立ではなく、隠蔽のサインに見える」
特に今回のように、県議会議員が亡くなった背景に「知事選」「内部告発」「県庁内の圧力」などの疑惑が絡んでいる場合、知事の沈黙は「慎重」ではなく「関与の疑念を強める行為」と受け取られます。
県民の目線からすれば、
- 「もし自分に関係がないなら、なぜハッキリ否定しないのか?」
- 「県政のトップとして、なぜ議員の死を悼む一言さえ言えないのか?」
と感じるのは当然です。
「コメントを差し控える」は、真相解明の意思がないというメッセージにも聞こえます。
「知事だからこそコメントすべき」理由
知事は、単なる行政の長ではなく、県民の代表であり、組織文化の象徴です。
その知事が「コメントを控える」と言えば、部下も同じように沈黙します。
結果として、組織全体が「責任を取らない文化」に染まってしまう。
このケースで知事が言うべきだったのは、次のような言葉です。
「県議会議員の尊い命が失われたことを大変重く受け止めています。
捜査の進展を見守りながらも、県としても原因究明と再発防止のため、全力で取り組みます。」
この一言があるかないかで、県政の信頼は天と地ほど変わります。
「黒幕」発言への異常な回避と心理的側面
「竹内英明氏を黒幕と思っていたか?」という問いに対しても、知事は「県政にご尽力いただいた」などと、質問と無関係な美辞麗句を繰り返しました。
これは政治心理的にみて、
- 「黒幕と思っていた」と答えれば、立花氏の主張を裏付けてしまう
- 「思っていない」と答えれば、過去の自分の発言・行動との整合性が取れなくなる
というジレンマを避けようとする「回避型答弁」そのものです。
結果として「感謝申し上げる」という無難な言葉を繰り返すことで、**“否定も肯定もせず、ただ沈黙を続ける”**という戦略をとったと見られます。
「黒幕と思っていたか?」に答えられない異常さ
選挙ウォッチャーちだい氏が繰り返し尋ねた質問——
「竹内英明氏を黒幕と思っていたか?YESかNOかでお答えください。」
この質問に対して斎藤知事は、
「竹内元県議におかれましては、県政へのご尽力を感謝申し上げます」
「お亡くなりになられたことにお悔やみ申し上げます」
と繰り返すのみで、「黒幕とは思っていない」と否定する言葉は一切ありませんでした。
政治的にも心理的にも「即否定」が自然な流れ
政治家としての常識から言えば、このような場面での最適な答えは極めて明快です。
「黒幕などと思ったことは一度もありません。県政にご尽力いただいた竹内県議の死は痛恨の極みです。」
この一言で、県議への敬意も表せ、誤解も解け、知事としての品位も守られます。
それを避けたということは、
- 「当時、本当に黒幕と見ていた可能性がある」
- 「否定すると過去の行動(発言・対応)との整合性が崩れる」
- 「捜査・関係者との発言食い違いを避けたい」
など、何らかの“裏事情”が存在する可能性を示唆しています。
“追い詰められた回答”に見える心理的背景
知事のような高位公職者が、この種の質問にまともに答えられないのは、心理的防衛に走っていると考えられます。
これは、
- 真実を語ると自分に不利になる可能性がある
- 嘘をつくと後で矛盾が生じる
- どちらを選んでもダメージを受ける
という“板挟み状況”にあるときに発生します。
結果として、「感謝」「お悔やみ」など安全な言葉を繰り返し、核心を回避する行動に出るのです。
沈黙が生むのは「誤解」ではなく「確信」
斎藤知事はおそらく、「不用意に発言して誤解されることを避けたい」と考えているのでしょう。
しかし、現実には逆効果です。
沈黙すればするほど、「否定できない事実がある」と受け止められます。
今回のやり取りで特に印象的なのは、記者が「答えられないということは、黒幕だと思っていたということでは?」と指摘しても、知事が依然として否定も訂正もしなかった点です。
もはや「誤解を防ぐ」どころか、自ら疑惑を深める発言構成となっています。
竹内氏の死をどう受け止めるべきか
竹内英明元県議は、県政の一翼を担ってきた人物です。
その死が「内部告発」「名誉棄損」「県政への不信」と絡む中で起きたことを考えれば、
知事として最も求められるのは「誠実な説明と心からの哀悼」です。
「政治的な立場を超えて、同じ兵庫県政を支えた同志の死をどう受け止めるのか」
——その問いに明確に答えない限り、
県民の信頼は回復しません。
「パワハラ・おねだり」発言への責任回避
立花孝志氏が「パワハラはなかった」「おねだりはなかった」と発言していたことに対して、知事自身も同様の主張を選挙中に行っていました。
しかし今回の会見で「本当だったのか?」と問われても、
「第三者委員会のご指摘を真摯に受け止めている」
とだけ述べ、真実の有無には触れませんでした。
「真摯に受け止める」とは、政治的言語で言えば**“当時の発言が誤っていた可能性を認めるが、明言は避ける”**という意味合いに近く、結果的に「嘘をついていた」と受け取られても仕方ない構図です。
「第三者委員会の指摘を受け止める」とはどういう意味か
斎藤知事が11月11日の定例会見で述べた
「第三者委員会のご指摘、報告書は真摯に受け止めている」
という言葉は、一見「反省」を示しているように聞こえます。
しかし、第三者委員会が報告書で認定したのは、
- 知事によるパワハラ行為の存在
- 数々のおねだり行為(贈収賄未満の不適切要求)
です。
したがって「真摯に受け止める」と言うのは、
**“委員会が認定した事実を受け入れる”**という意味であり、同時に過去に自らが発言していた
「パワハラはなかった」「おねだりはなかった」
という主張を否定したことに等しいのです。
選挙中の主張との整合性が完全に崩壊
2024年の兵庫県知事選挙期間中、斎藤知事は立花孝志氏と連携しながら、「内部告発文書はデマ」「パワハラもおねだりもなかった」と繰り返し訴え、その主張をSNSや街頭演説で拡散していました。
しかし、第三者委員会報告書が「パワハラ10件認定」「おねだり行為の存在」を明記した以上、それらの主張は客観的に誤りだったことが確定しています。
にもかかわらず、会見で
「本当だったのか?」
と問われた際に「真摯に受け止める」と答えたのは、
自らの“虚偽発言”を認めたに等しい答弁です。
「真摯に受け止める」は政治的に都合の良い“中間表現”
政治家がスキャンダルに直面したとき、もっとも多用するフレーズの一つが「真摯に受け止める」です。
この言葉の本質は、「謝罪でも否定でもない“グレーな逃げ道”」にあります。
「真摯に受け止める=認めるが謝らない」
という構図を作り出すことで、法的責任を回避しながら「反省している風」を演出できる。
つまり、責任は取らずに印象だけを和らげる政治言語なのです。
今回もまさにこの典型例であり、
「真摯に受け止める」と言えば済むと思っている時点で、本当の意味での説明責任を果たす意思がないことが露呈しています。
選挙公約と現実の乖離
斎藤知事は2021年の選挙中、「クリーンな県政」「利権と決別」を掲げていました。
しかし、選挙後に明らかになったのは、
- パワハラの多発
- おねだり(不適切要求)行為の認定
- 内部告発者への報復的対応
- 情報漏洩や虚偽説明の繰り返し
という、まったく逆の実態です。
これらを踏まえれば、「真摯に受け止める」と言った瞬間に、
選挙中の“クリーンさの演出”が完全に虚構だったことが明らかになります。
県民への裏切りと説明責任の欠如
県民が求めているのは、「どこが誤りだったのか」「誰にどのように謝罪するのか」という具体的な説明です。
「真摯に受け止める」では何も伝わりません。
むしろ県民にとっては、
「嘘をついていたが、今さら訂正も謝罪もしない」
という態度にしか映らないでしょう。
このまま説明責任を放棄すれば、次の選挙で県民の審判を免れることは不可能です。
「ふくまろ」質問で見せた“逃げの極致”
最後に「ふくまろ」や「ふくまろネットニュースチャンネルを知っているか」と問われた場面では、
「さまざまなメディア主体があると思います」
「ここにおられる記者さんも含めてさまざまな主体がある」
と、質問の意味自体を曖昧化するという異様な対応でした。
この回答は、「知っている」とも「知らない」とも言えない状態であり、仮に関与や接点があった場合の責任回避を意識しているように見えます。
「ふくまろ」質問の本質——単なる知名度確認ではない
選挙ウォッチャーちだい氏が質問したのは単なる「知っているかどうか」ではありません。
背景には、2024年の兵庫県知事選でボランティアとして活動していた**「ふくまろ」氏(YouTuber)**が、
- 選挙中に知事(当時候補者)を支援する形で動画配信を行い、
- 選挙後も継続して知事の“遠足”や“現場視察”に同行して撮影・配信し、
- YouTubeで広告収入(=経済的利益)を得ている
という、政治的公平性・倫理性に関わる重大な疑問がある点にあります。
選挙支援と収益化の関係——公選法・倫理のグレーゾーン
この問題の核心は、「政治活動への関与と経済的利益の結びつき」です。
もし「ふくまろ」氏が斎藤陣営のボランティア・関係者として活動しながら、その映像をYouTubeで配信し、広告収益を得ていた場合、
- 実質的に選挙運動を営利目的で行っていた
- または候補者のイメージ向上を通じた経済的利益の享受
に該当する可能性が生じます。
これは公職選挙法上の「報酬供与の疑義」や、少なくとも政治倫理条例に抵触する恐れのある行為です。
知事自身がその存在を“知っている”と認めれば、「なぜそのような人物を同行させたのか」「県政活動との線引きは?」という説明責任が生じるため、あえて“知らないとも言えない・知っているとも言えない”曖昧な返答を選んだと考えられます。
テンプレ回答に逃げた理由——「知っている」と言えば説明が必要、「知らない」と言えば虚偽の可能性
会見での斎藤知事の回答:
「さまざまなメディア主体、取材主体があることだと思います。」
「ここにおられる記者さんも含めて、さまざまな主体があると思います。」
この回答は、政治的リスクを避けるための典型的な“テンプレート逃避答弁”です。
「ふくまろ」を知らないはずがありません。
知事選のボランティアとして同行し、視察現場や県内イベントで一緒に映っている映像は複数存在します。
つまり——
「知っている」と言えば、選挙活動・県政活動・営利活動の関係を説明せざるを得ない。
「知らない」と言えば、明白な虚偽答弁となる。
どちらも地雷であるため、「メディア主体」という抽象的な言葉で煙に巻いたのです。
県政の透明性を脅かす「非公式広報ルート」
本来、公的な活動(視察・出張・行事)は、県の公式広報チームや報道機関を通じて透明に公開されるべきです。
そこに“特定の個人YouTuber”が同行し、知事の発言や映像を独占的に編集・収益化している状態は、
- 公的映像の私的利用
- 政治的中立性の損失
- メディアアクセスの公平性の欠如
といった深刻な問題を孕んでいます。
県民が知事の活動を知る手段が、「特定の支持的YouTuberのチャンネル」に依存するようでは、県政の透明性は失われ、県庁公式広報の信頼性も揺らぎます。
「恐れて答えなかった」沈黙の代償
斎藤知事が今回「ふくまろ」をめぐる質問に一切答えなかったのは、自らがこのチャンネルとの関係を説明するリスクを理解していたからでしょう。
しかし、このような曖昧な態度は、むしろ関係の深さを印象づける結果になりました。
県民から見れば、
「もし問題がないなら、堂々と『関係はない』と言えばいい」
という話です。
沈黙は中立ではなく、「やましさの表明」にしか見えません。
沈黙は「無罪」ではなく「責任放棄」
斎藤知事の一連の会見対応は、もはや「説明責任の放棄」と言わざるを得ません。
「捜査中」「差し控える」「真摯に受け止める」などのフレーズは、政治家が危機回避のために使う**“免罪符のテンプレート”**ですが、県民が求めているのは「回避」ではなく「説明」です。
このような対応を続ける限り、
- 「立花孝志との関係」
- 「2馬力選挙の実態」
- 「竹内元県議との関係」
- 「はばタンPay+情報漏洩」
など、すべての疑惑が「答えない=やましいことがある」と受け止められていくでしょう。