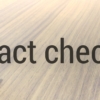兵庫県知事選をめぐる不起訴処分とは?「嫌疑不十分」の意味をわかりやすく解説
目次
兵庫県知事選での不起訴処分と「嫌疑不十分」とは?
2025年11月12日、神戸地検は、昨年の兵庫県知事選挙に関連して公職選挙法違反の疑いで書類送検されていた斎藤元彦知事とPR会社代表を不起訴処分としました。
理由は「嫌疑不十分」。報道によれば、「PR会社に支払われた報酬は、選挙運動の対価とは認められなかった」と説明されています。
そもそも「嫌疑不十分」とはどういう意味?
「嫌疑不十分」とは、犯罪の疑いはあるが、有罪と断定するには証拠が足りないという意味です。
つまり、「違法の可能性は否定できないが、裁判で立証するには不十分」という検察の判断です。
検察が不起訴とする理由には、主に次の3種類があります。
不起訴の3つのパターン
嫌疑なし
→ 犯罪そのものが存在しない、または被疑者が関与していない。
嫌疑不十分
→ 犯罪の可能性はあるが、証拠が不十分で有罪を立証できない。
起訴猶予
→ 犯罪は認められるが、反省や情状を考慮して起訴しない。
今回の兵庫県知事選のケース
この事件では、PR会社がSNS運用などを担当し、「広報全般を任せていただいた」と発信していたことから、
「選挙運動の報酬にあたるのではないか」として、弁護士と大学教授が刑事告発していました。
その後、県警が今年6月に書類送検し、神戸地検は7月に斎藤知事を任意で事情聴取。
しかし、地検は「SNS運用などの業務が選挙運動と断定できる証拠がない」として、嫌疑不十分で不起訴処分としました。
不起訴=無罪ではない
ここで注意すべきなのは、「不起訴=無罪」ではないという点です。
嫌疑不十分の場合は、「証拠が足りないから起訴しなかった」だけであり、違法の可能性そのものが消えたわけではありません。
検察が「嫌疑なし」と判断した場合のみ、「犯罪の事実がなかった」と言えます。
「嫌疑不十分」は“証拠がない”だけでなく“証拠が集められなかった”も含む
検察が「嫌疑不十分」と判断する典型的なケースは次の3パターンです。
(1)証拠がそもそも存在しなかった
- 事件当時の契約書、金銭授受の記録、メール・SNSのやり取りなど、
犯罪を立証できる直接的な証拠が存在しない場合。 - 証言も曖昧、または食い違いが多い場合。
この場合、「やった可能性はあるが、立証できない」という結論になります。
(2)証拠が存在したが、確保できなかった
- 関係者が証拠を隠滅、削除、破棄していた場合。
- データがクラウド上や国外サーバーなどにあり、捜査権限が及ばなかった場合。
- 家宅捜索を行っても、関係書類・電子データなどが既に消去済みだった場合。
この場合も、「捜査しても証拠が見つからなかったため、有罪を立証できない」という形で嫌疑不十分になります。
(3)証拠はあるが、“犯罪の意図”を立証できない
- 金銭のやり取りや契約書など「形式的証拠」はあっても、
それが選挙運動の報酬であることを証明できないケース。 - たとえば「SNS運用契約」や「広報コンサル契約」のように、
一般的な業務委託の形をとっている場合、
「報酬の名目=選挙運動対価」と断定するのは非常に難しい。
このような“意図の証明”ができない場合も、嫌疑不十分となります。
家宅捜索をしても証拠が出ない場合の意味
家宅捜索は、令状に基づいて行う強制捜査の一種で、「重大な犯罪の可能性がある」「重要な証拠が存在する蓋然性が高い」と判断された場合に行われます。
しかし、
- 家宅捜索をしても証拠が出てこなかった場合、
→「証拠がない」「またはすでに隠滅されている」と見なされる。 - 出てきた証拠が不明確・解釈が分かれる場合、
→「犯罪との因果関係が立証できない」として嫌疑不十分。
特に、電子データ(SNS運用記録、広告契約メール、請求書PDFなど)は、削除やクラウド移転で容易に消せるため、後から確定的証拠を得るのは難しくなります。
実務上、「証拠隠滅」と「嫌疑不十分」は紙一重
たとえば、
- 関係者が口裏を合わせる
- 契約書を“別名義”に変更する
- 金銭の流れを別の法人経由にする
といった行為があったとしても、
それを「隠滅」として立証できなければ、結果として「嫌疑不十分」に分類されます。
つまり、
「証拠が足りない」には、“見つからなかった”と“消された(と思われる)”の両方が含まれる
ということです。
今回のケースにおける検審申立ての可能性とハードル
斎藤元彦知事(および関連するPR会社代表)の公職選挙法違反疑いで書類送検され、不起訴処分となった件について、検審申立てが行われ得るかを考えると、以下がポイントです。
ハードル/確認すべき点
対象となる不起訴処分か:今回、不起訴処分が出ており、検審の対象要件の一つを満たしています。
申立てがなされるか:検審に進むには、告発者・被害者等からの申立て(あるいは検審が職権で行うケース)があります。
管轄・時効など:検審を申立てられるかどうかは、どの検察審査会の管轄か、申立て時期がどうかなど、制度的な条件があります。
議決に至るか:「起訴相当」となるかどうかは、その事件・証拠・社会的影響によって異なります。検察が不起訴にした理由(このケースでは「嫌疑不十分」)が検審で覆るかどうかも不透明です。
申立てされるかの見通し
公職選挙法違反という、政治・選挙という社会的関心の高い事件であるため、告発等を行った側が検審申立てを検討する可能性はあります。
ただし、検察が「嫌疑不十分」を理由に不起訴としており、証拠の積み上げ・当事者の関係性・報酬の実質性など争点が複雑であるため、検審に持ち込んでも「起訴相当」と議決されるかは楽観できません。
郷原弁護士は、不起訴を受けての記者会見で、来週にも検察審査会に申し立てを行うと発言されていました。
補助金問題でも不起訴に
さらに、斎藤知事はプロ野球の優勝パレード補助金増額問題でも刑事告発されていましたが、こちらも「嫌疑不十分」として不起訴処分となりました。
つまり、いずれの件も「違法の可能性はあったが、有罪立証には至らなかった」という判断です。
「嫌疑不十分」は“グレー”な判断
「嫌疑不十分」は、決して「潔白」という意味ではなく、証拠が足りず起訴を見送ったグレーな状態を指します。
県民としては、形式的な結論だけでなく、「なぜ十分な証拠が集まらなかったのか」「調査の過程でどんな問題があったのか」も注視することが重要です。