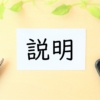【兵庫県政の行き詰まり】「違法」指摘を受け入れない斎藤知事と、動けない県議会
目次
- 1 第三者委員会も百条委員会も「違法」を認定
- 2 では、なぜ県議会は動かないのか
- 3 統治崩壊の危機に、議会はどう責任を取るのか
- 4 知事だけでなく、県議会も説明責任を放棄している
- 5 知事の不法行為を「容認」しているのに…議会は異常だと感じていないのか
- 6 今、最も異常なのは「異常だと認識していない議会」
- 7 県議会も県民に対する説明責任を負っている
- 8 立花孝志の逮捕で「選挙の正当性」が揺らいだ
- 9 デマに基づく投票は「民意」と呼べない
- 10 議会は県民に説明せよ
- 11 県議会が「選挙の正当性」を追及しないのは職務放棄に近い
- 12 逮捕が示すのは「選挙に重大な瑕疵があった」という可能性
- 13 県議会が追及すべき “5つの論点”
- 14 県民はすでに「議会にも期待していない」
- 15 今こそ、議会は「もう一度、県政と県民の側に立つべき」
- 16 結論:行動しなければ、議会も歴史の責任を負う
─ 統治崩壊の危機に、県議会はどう向き合うのか ─
2025年11月16日の産経新聞は、兵庫県政の深刻な膠着状態を象徴する記事を掲載した。
告発者処分の「違法」指摘を、斎藤元彦知事が依然として頑なに否定し続けている一方で、県議会は再度の不信任決議に踏み込めず、事態は1年以上にわたり動かないまま停滞している。
しかし、この“動かないことによる損失”がどれほど大きいかを、議会はどれほど自覚しているのだろうか。
「告発者処分の「違法」指摘受け入れぬ斎藤兵庫知事、「前回の反省」で県議会は動けず」
https://www.sankei.com/article/20251116-FUAL3DUTJFOH3NJYEREK3RE4AM(出典:産経新聞 2025年11月16日)
第三者委員会も百条委員会も「違法」を認定
斎藤知事が処分した告発者に関して…
- 百条委員会:公益通報者保護法に「違反している可能性が高い」
- 第三者委員会:斎藤知事の対応は「明らかに違法」、パワハラも認定
にもかかわらず、知事は今もなお、
「適法に対応してきた」
と主張し続けている。
この頑迷さが県政不信を深刻化させ、多くの県民が政治から距離を置いてしまっている。
では、なぜ県議会は動かないのか
産経新聞は次のように報じている。
「かたくなに受け入れようとしない姿勢に議会からの批判は強いが、再度の不信任には慎重な意見が大半」
なぜか?
その理由は大きく3つある。
① 前回の“不信任の反省”
記事によれば、ある県議はこう語ったという。
「県民に十分な説明をせず、不信任に踏み切った反省がある」
これは、裏返せば“説明不足の責任を負いたくない”という自己保身の論理だ。
② 知事再選という「民意」を恐れている
昨年の知事選挙では、SNSのデマによる動員が強く働いた。
しかし、議会はそれを“純粋な民意”として扱わざるを得ず、判断をためらっている。
③ 自身も対抗馬を出せなかった負い目
対立候補をまとめられなかったため、「その後に強く出られない」という構造的弱さがある。
結果として、
県議会は知事と真正面から戦えず、県政の空白を放置してしまっている。
統治崩壊の危機に、議会はどう責任を取るのか
議会が「動かない」ことによって、県政はすでに壊れ始めている。
● 統治機能の崩壊
・情報漏洩が続発
・職員のコンプライアンス意識の低下
・知事の責任回避体質が固定化
・行政内部に告発者潰しの空気が広がる
・県民の不信が常態化
これらは、政治学でいう “統治の空洞化” の典型例だ。
このまま続けば、兵庫県の行政は立て直しに数年単位の時間が必要になる。
知事だけでなく、県議会も説明責任を放棄している
兵庫県政の最大の問題は、斎藤知事が説明責任を果たしていないこと――これはすでに多くの県民が感じています。
しかし、もうひとつ深刻なのは、「議会もまた、説明責任を果たしていない」 という事実です。
本来、知事の不正や違法行為をチェックするのが議会の責務です。
それにもかかわらず、第三者委員会や百条委員会が「明らかに違法」と指摘したにも関わらず、議会は再度の不信任を避け、知事を事実上“容認”する姿勢に傾いています。
知事の不法行為を「容認」しているのに…議会は異常だと感じていないのか
ここに、県民の強い疑問があります。
◎ 斎藤知事
- 告発者処分は「適法」と主張し続ける
- パワハラ認定も受け入れない
- 情報漏洩も「指示はしていない」と完全否定
- 会見でも説明を避け続ける
◎ 県議会
- 第三者委員会は「違法」と断定
- 百条委員会も「違法の可能性が高い」と認定
- にもかかわらず、再度の不信任決議へ踏み込めない
この構造は極めて異常です。
“知事が違法行為を繰り返しても、議会は止めようとしない”
これは地方自治の仕組みが機能不全に陥っている状態です。
議会は「前回の不信任で説明不足があった」「知事再選という民意がある」などと自己保身の理由を並べていますが、その間にも、県政は崩壊へと進みつつあります。
今、最も異常なのは「異常だと認識していない議会」
政治の世界で最も怖いのは、
★「異常が日常になり、誰も異常だと思わなくなる」状態です。
兵庫県議会はまさにその段階に足を踏み入れています。
- 違法行為が指摘されても知事は開き直る
- 県議会はそれを止めない
- 説明責任を果たすべき立場の者が誰も説明しない
- 県政の信頼は失われ続ける
議会がこの異常事態を異常と感じていないのであれば、それは組織として末期的と言わざるを得ません。
県議会も県民に対する説明責任を負っている
議会は、知事を監視する立場であると同時に、有権者に対して説明する責任を負う公選職です。
県民がいま知りたいのは以下です:
- なぜ、違法行為を認定されたのに不信任を再提出しないのか?
- 議会が動かないことで生じる県民の損失をどう考えているのか?
- このまま膠着状態を続けることは、議会にとって責任放棄ではないのか?
- 議会は、自分たちが統治崩壊を助長しているという自覚があるのか?
これらに答えない限り、議会もまた「県政不信の当事者」でしかありません。
立花孝志の逮捕で「選挙の正当性」が揺らいだ
2024年兵庫県知事選挙では、立花孝志による虚偽情報(デマ)拡散が大量に行われ、SNS上での印象操作が選挙の雰囲気を支配した。
そして今、その中心人物である立花孝志が、元県議に対する名誉毀損容疑で逮捕・送検された。
この事実は、選挙結果の正当性に重大な疑念を生じさせている。
- デマ → 有権者の判断を歪めた
- デマ → 選挙戦の構図を不当に操作した
- デマ → 一部候補者に不当に有利に働いた
こうした“歪んだ環境の中で行われた選挙”は、
民主主義において本来求められる 「自由で公正な選挙」 の条件を満たしていない可能性がある。
デマに基づく投票は「民意」と呼べない
選挙の民意とは、本来こうあるべきです:
① 候補者に関する正確な情報
② 政策や人格についての公正な評価
③ 有権者の自由な判断
しかし、2024年の兵庫県知事選は明らかに違った。
議会は県民に説明せよ
議会は次を明確に答えるべきだ。
- このまま放置した場合、統治崩壊をどう防ぐつもりなのか?
- 崩壊した行政機能を正常化するのに、どれだけの時間とコストがかかるのか?
- その間に県民が被る不利益をどう補うのか?
- なぜ「動かない」ことが、議会として最善の判断だと言えるのか?
県政の崩壊リスクは“議会の判断ミス”によって大きくなっており、議会はその説明責任から逃げてはならない。
● デマが政策議論を完全に上書き
真偽不明の攻撃的な投稿が大量に拡散され、政策や実績よりも「怪情報」が選挙を支配した。
● 一部の候補に有利な印象操作が行われた
立花孝志の動画やSNS投稿は、特定候補を利するよう意図的にデマを流した疑いが強い。
● 有権者は誤った情報をもとに投票した
つまり、民意が歪められた 可能性が高い。
その中心人物が逮捕された以上、「この選挙は公正に行われたのか?」と問うのは当然である。
県議会が「選挙の正当性」を追及しないのは職務放棄に近い
本来、県議会には以下の責務がある:
- 選挙の公正性が損なわれた疑いを調査する
- 行政が恣意的にデマを利用していた可能性を検証する
- 有権者の判断が歪められたなら、その影響を明らかにする
- 再発防止策を制度的に整備する
しかし現状はどうか?
◎ 議会は選挙の正当性に一切踏み込んでいない
まるで
「選挙の結果は聖域」
と扱うかのように、議論さえ避けている。
これは極めて危険である。
◎ デマ選挙が許されれば、今後も同じことが繰り返される
悪質なデマを撒いた者が「選挙結果に影響を与えた後、逮捕される」という事態を議会が問題視しないのなら、兵庫県は今後ずっと“デマと印象操作に弱い県政”のままだ。
逮捕が示すのは「選挙に重大な瑕疵があった」という可能性
立花孝志の逮捕は、単なる一個人の刑事事件ではない。
次のような論理的帰結を持つ:
- 逮捕された → デマが刑事事件レベルで悪質だった
- そのデマが選挙中に大量拡散された
- 有権者の判断を不当に左右した
- その結果が選挙結果に影響した可能性が高い
つまり、
選挙の公正性そのものが揺らいでいる
という極めて重大な問題を示している。
県議会が追及すべき “5つの論点”
県議会は以下の点を避けてはならない。
① デマが選挙結果にどれほど影響したのか
SNS分析・選挙データ分析を踏まえ、客観的調査が必要。
② 特定候補に有利な情報操作が行われた可能性
第三者委員会も認定している“知事周辺の異常な組織文化”との関連性。
③ 知事側がデマを止めるどころか容認した疑い
記者会見での「表現の自由」発言が象徴的。
④ デマ拡散者と候補者陣営の関係
選挙法・政治資金規正法の観点から調査が必要。
⑤ 民意の歪みによる選挙の正当性
選挙の自由と公正が侵害された可能性がある以上、議会が無視するのは許されない。
県民はすでに「議会にも期待していない」
斎藤知事の問題を放置しているのは、もはや知事だけではない。
動かない議会もまた、県政不信を助長している当事者である。
自己保身のためか、党派配慮のためか。
理由はどうあれ、「戦わない」議会に失望する県民は確実に増えている。
議会が正しく動かなければ、
県民が行政の不正をただす手段は 検察審査会・住民監査請求・住民訴訟・メディア・市民運動 に頼らざるを得ない。
今こそ、議会は「もう一度、県政と県民の側に立つべき」
大正大学の江藤教授は、産経新聞の中でこう提言している。
「不信任からの1年を検証し、議会が住民や知事との議論の場を仕掛けるべきだ」
議会に求められるのは“先延ばし”ではなく、“行動”だ。
- 特別委員会の再設置
- 公開の説明会
- 住民との対話の場の構築
- 透明性ある検証プロセスの提示
- 必要なら、再度の不信任を選択肢に戻すこと
これらはすべて、議会が本来負うべき義務だ。
結論:行動しなければ、議会も歴史の責任を負う
知事が違法指摘を受け入れない。
議会も動かない。
この悪循環こそが、兵庫県政の最大の“病”であり、
放置すればするほど、県政は取り返しのつかないほど壊れていく。
県議会は、「なぜ動かないのか」ではなく、「どう動くか」これを、今こそ県民に示すべき時だ。
立花孝志逮捕後、選挙の正当性を検証しない県議会は職務放棄である
今、兵庫県に必要なのは
- デマによる選挙汚染の検証
- 計画的な情報操作の可能性の調査
- 選挙の正当性を回復するための議論
- 有権者への説明責任
である。
これをしなければ、県議会は「知事の不正をチェックできない」だけでなく、選挙の公正性を守る役割すら果たしていない ということになる。
この問題を避けることは、議会としての責任放棄であり、民主主義の自殺行為だ。