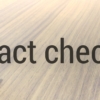「エアコンはあるのに使えない」兵庫県高校体育館の現実― 設置だけ進め、電気代の予算をつけない“数字優先”の政策とは ―
兵庫県で進められている「高校体育館へのエアコン設置」。
しかし、現場では驚くべき実態が明らかになっています。
・授業中は基本的に使えない
・操作盤には鍵がかけられている
・使用できるのは終業式・始業式・オープンハイスクールなど限定的
・現場の教員だけの判断ではONにできない
この問題について朝日新聞も報じていますが、背景には、電気代(運転費)の予算がそもそも付いていないという致命的な問題があります。
エアコンがあっても使えない——。一体なぜこのような事態が起きているのでしょうか?
「斎藤知事が設置進める高校体育館エアコン「授業で使えない」その訳は」
https://www.asahi.com/articles/ASTCG3SPJTCGPIHB00NM.html(出典:朝日新聞 2025年11月17日)
目次
なぜエアコンが使えないのか?
理由は「電気代の予算が無い」から
体育館にエアコンを付ければ、当然電気代が増えます。
しかし、兵庫県は設置費用のみを予算化し、ランニングコストを計画していない のです。
実際、他自治体では体育館エアコンの使用は1時間1500〜2500円(例:箕面市・2018年) とされており、これは決して無視できる額ではありません。
体育館は広く、天井も高く、冷房には大量の電力が必要です。
運転費を計画していない状況で、現場が自由に使えるはずがありません。
「設置率」だけを重視する“数字優先の政策”
斎藤知事のアピールは「外箱=設置率」だけ
今回の問題を根本的に生んでいるのは、成果として“見える数字”だけを重視した政策設計 だと考えられます。
- エアコンの「設置率」
- 「導入実績」
- 「全国比較」
こうした “外から見える数字”を取り繕うための政策 が先行し、実際の運用(予算・人員・ルールづくり)が全く追いついていません。
現場教員や子どもの快適性・安全は後回し。
「設置した」という事実だけを県民にアピールするために行われた施策と言わざるを得ません。
現場の声:「エアコンあるのに使えない」子どもも教員も無力感
SNSには、保護者や生徒から以下のような声が相次いでいます。
- 「鍵がかかっていて授業中に使えない」
- 「夏の体育館は地獄なのに、エアコンは飾り」
- 「子どもたちは感謝どころか“意味がない”と感じている」
- 「教室のエアコンも保護者懇談の時だけしか使えない学校もある」
設備の外観だけ整え、“見栄えだけの政策”が子どもたちを苦しめる結果になっている のが現状です。
県職員はなぜ止められなかったのか?
本来、行政では設備を導入する際、次のことをセットで考えます。
- 維持費(電気代・メンテナンス費)
- 人員配置
- 運用ルール
- 継続的な予算措置
これらを含めて政策が設計されるのが普通です。
それなのに今回のような「使えないエアコン設置」が起きた背景には、
●知事の“設置優先・見栄え優先”の政治姿勢
●県庁内の議論が抑圧される体質
●若手・中堅職員の大量退職によるガバナンス低下
●トップの意向を忖度せざるを得ない状態
といった、近年の県庁内部の問題が関係していると考えられます。
つまり、「現場が困ろうが、運用が破綻しようが、設置率を上げることが最優先」という空気が県庁に蔓延している可能性が高いのです。
誰が最も困るのか?
●現場の教員
・暑さ指標(WBGT)が危険値でも使えない
・熱中症リスクの管理が難しい
・保護者からの問い合わせに答えられない
●子どもたち
・体育館は真夏は蒸し風呂状態
・部活動、集会、授業の環境が過酷
・「エアコンがあるのに使えない」という不信感だけが残る
最も苦しむのは子どもたちなのに、県はその現実を直視していません。
斎藤知事が自滅して行く
斎藤県政で繰り返されている一連の“いびつな施策”——
エアコン設置だけ進めて電気代の予算を付けない、SNS映えする外形だけ整えて中身が伴わない、現場や県民の声ではなく“見栄えの数字”を優先する——
こうした構造は、一度だけの失策ではなく、県政全体に共通する「決定の仕組みの問題」 です。
この体質が変わらない限り、同じような「見かけ倒しの政策」は必ず繰り返されます。
県民はいずれ異常さに気づく
今はまだ「詳しい事情を知らない県民」も多く、
- 表面的な成果
- SNSでの演出
- “何かやっている感”
が一定の支持につながっています。
しかし、生活に直結する政策が実際には機能していない という事実は、遅かれ早かれ県民の生活実感として表れてきます。
- エアコンはあるのに使えない
- 公金がどこに消えているのかわからない
- 説明責任を果たさない県政
- 県庁内の不祥事の頻発
- 重大案件の“放置”
こうした積み重ねは、必ず県民意識を変えていきます。
「おかしいのでは?」と気付く瞬間が、必ずやってきます。
このままでは“自滅型”の県政になる
いまの斎藤県政は、
●表面の数字だけ整える
●中身が伴わない
●現場の声が届かない
●説明責任を果たさない
という構造になっています。
このタイプの政治は、短期的には評価されても、時間が経つほど矛盾が噴き出して自壊していきます。
理由は簡単で、「本質的な改善が行われていない」からです。
●県職員は疲弊
●現場は機能不全
●県民の不満だけが蓄積
●支持者層以外は徐々に離れていく
●メディア報道も厳しくなる
●県庁内部の統制も崩れる
いま既に兆候は出始めており、このまま続ければ“自滅型の県政”になる可能性が極めて高いです。
むしろ県民に必要なのは「気づきのきっかけ」
斎藤県政は、「うまくいっているように見せる」ことは得意でも、「実態を改善する」ことは非常に苦手です。
だからこそ、今回のエアコン問題のように、“生活に直接影響する矛盾”が可視化されると、一気に不信感が広がるという特徴があります。
エアコンは子ども・学校という誰でも理解できるテーマなので、これは県民の意識を変える大きなきっかけになり得ます。
まとめ:「設置すること」が目的化した政策は、必ず現場を苦しめる
エアコンの設置そのものは良い政策です。
問題は、“使える状態にしていない”こと。
- 電気代の予算がない
- 運用ルールが整っていない
- 意思決定が「数字優先」
- 現場の実態を無視したトップダウン
これでは、「あるのに使えない」最悪の公共投資 です。
子どもたちの安全や教育環境を本当に考えるのであれば、必要なのは「設置」ではなく、“使えるための予算と制度” です。
今後は、設置率の数字ではなく、「どれだけ子どもたちが快適に学べるか」という視点で政策が組み立てられることが求められます。
●斎藤県政がこのまま続けば、“いびつな政策”は必ず増え、矛盾は拡大する。
●県民はいずれ「異常さ」に気づき始める。
●その時、もっともダメージを受けるのは斎藤知事自身。
つまり、斎藤知事の政治スタイルは、自らを追い詰めていく構造になっています。