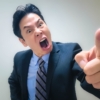第三者委員会の認定に対する企業や自治体の対応
目次
第三者委員会は法的拘束力は無い
第三者委員会には法的拘束力がありません。第三者委員会は法令で設置が義務付けられているわけではなく、企業が任意で設置する組織です。調査報告書や提言に法的強制力はなく、企業がその内容に従う義務は発生しませんが、調査の客観性や信頼性を高めるために設置されるものです。
その客観性や信頼性のため、企業や自治体は第三者委員会の認定を受け入れています。企業が第三者委員会の報告を受け入れないと、ステークホルダーからの信用が失墜してしまい、企業存続の危機に直面する恐れさえあります。
電通(2015年 高橋まつりさん過労自死事件)
第三者委員会が「過労死・違法な長時間労働」を認定。
電通は委員会の認定を受け入れ、経営陣辞任・再発防止策・労働時間の是正を実施。
厚労省から労基法違反で書類送検もされ、委員会の調査結果が処分の根拠となった。
東芝(2015年 不正会計問題)
第三者委員会が「経営陣のプレッシャーによる粉飾決算」を認定。
東芝は認定を受け、歴代社長・会長らが辞任。
上場企業としてガバナンス改革(社外取締役増員、監査体制強化)を導入。
オリンパス(2011年 損失隠し事件)
第三者委員会が「歴代経営陣による組織的隠蔽」を認定。
経営陣は総退陣、株主代表訴訟や刑事訴訟に発展。
委員会報告を基に新経営陣が再建策を発表。
大阪市(大阪市立中学校 校長のパワハラ問題)
第三者委員会が「パワハラ認定」を行った。
市教育委員会は認定を受けて校長を懲戒処分。
再発防止研修や相談窓口の拡充を実施。
兵庫県明石市(市長の暴言問題, 2019年)
第三者委員会が「職員へのパワハラ的言動」を認定。
泉房穂市長は一度辞職 → 出直し選挙で再選。
市としては委員会認定を受け入れ、再発防止のガイドライン策定。
横浜市(保育園での虐待事案)
第三者委員会が「虐待の存在」を認定。
市は認定を受けて保育園に行政指導、改善計画提出を義務化。
日本大学アメフト部危険タックル問題(2018年)
第三者委員会が「監督・コーチの指示を認定」。大学は当初、認定を全面否定 → 批判を受けて最終的に受け入れ。
朝日新聞(慰安婦報道検証, 2014年)
第三者委員会の検証により誤報を認定。
会社は謝罪・記事取消を行ったが、一部の認定については異論を出す論者も多かった。
兵庫県斎藤知事の第三者委員会の認定に対する対応(兵庫県の対応は異常)
文書問題第三者委員会
第三者委員会は11件のパワハラと公益通報者保護法違反を認定しました。
斎藤知事はパワハラを認め謝罪とパワハラ研修を受講しましたが、「襟を正し、再発防止も含めて、しっかり対応していくのが私の責任」として、処分はありませんでした。
公益通報者保護法違反については、県の対応は「適切だった」として、第三者委員会の認定には従っていません。
情報漏洩第三者委員会
県議に元県民局長の私的情報を漏洩したとして、調査が行われました。県議に情報を見せた井ノ本元総務部長は知事からの指示で業務として行ったと主張していて、その他、知事以外の牛タンクラフのメンバーも知事からの指示だと供述しました。
知事が総務部長であるE氏対し事項を特定せずに一般的に議会筋との共有を指示することがあってもおかしくは無いと思われるにも関わらず、前掲の通り、本件については一般的なパターンでの情報共有の指示すら否定する知事の供述には不自然さも否めないと考えました。
知事の前記供述は採用することが困難と言うべきであると言う結論に達しました。
第三者委員会は、情報漏洩に関して知事の指示があった可能性が高いと認定しましたが、“漏えいは指示していない”と真っ向から否定して、受け入れていません。
斎藤知事が第三者委員会の報告を受け入れないのなら
法的手続きに委ねる
刑事・民事訴訟に発展させる
第三者委員会の認定を受け入れず、「司法で最終判断を仰ぐ」という方法。
行政訴訟や労働審判
行政訴訟や労働審判に持ち込むケースもあり、最終的に司法の判断に委ねる形になる。
第三者委員会の設置には多額の公費が投入されている
文書問題の第三者委員会に3,600万円。情報漏洩の第三者委員会に600万円の税金が使われています。
県民の信頼回復が目的なのに逆効果
第三者委を設ける本来の目的は、
- 「公平・中立な立場で事実を明らかにする」
- 「組織の信頼を回復する」
ことにあります。
ところが、報告を受け入れず「参考意見にすぎない」と扱えば、むしろ不信感が増幅し、税金投入の効果が逆転してしまう。
全く無駄になった税金
第三者委員会の認定を全く受け入れず、受け入れないことの理由にを全く説明しない斎藤知事は、県民の税金を無駄遣いしたとしか言えない状態です。
恐らく、自分にとって都合の良い結論であれば受け入れて、都合の悪い結果であれば受け入れないと言うことなのだと思います。
そうであれば、第三者委員会を設置したこと自体が無意味であり、そのようなことに税金を使った、斎藤知事は責任を取るべきたです。