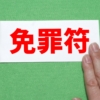【ジェンダー問題】「女性には“うん”、男性には“はい”」 斎藤知事の無意識の差別が公の場で露呈
目次
「女性記者には“うん”」「男性記者には“はい”」——記者の指摘
2025年11月4日の兵庫県定例記者会見で、著述家の菅野氏が、斎藤元彦知事の女性記者への態度の違いについて、次のように指摘しました。
「今僕に『お疲れ様です』と仰った。女性の記者だと『お疲れ様でーす』になる。
男性記者だと相槌は『はい』だが、女性記者だと『うん』なんです。
男性と女性で態度が違う。公の場なので女性差別はやめてください。」
一見すると些細な言葉遣いに見えるかもしれません。
しかしこれは、行政トップの公的場面における態度の公平性・敬意の一貫性に関わる重要な問題です。
知事の回答:「自然な流れで対応しています」
これに対して斎藤知事は、
「ご指摘は真摯に受け止めますけども、自然な流れで会見への対応をさせていただいています。」
と答えました。
しかしこの回答は、差別を否定するものではなく、“意識していない”と正当化するものです。
まさにこれが「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」の典型例であり、「自然な対応」という言葉の裏に、性別による無自覚な態度の差が存在していることを示しています。
繰り返される“無意識の差別”の指摘
この問題は今回が初めてではありません。
アークタイムズの尾形氏も以前から、
「男性記者と女性記者で、知事の受け答えの態度が明らかに違う」
とYouTube上で複数回指摘しており、行動パターンとして常態化していることが分かります。
県政トップという立場でありながら、「親しみやすく接しているつもり」が「女性を軽く扱っている」と受け止められている時点で、社会的リーダーとしてのジェンダー意識に深刻な欠陥があります。
行政トップに求められる“言葉の平等性”
公的な記者会見においては、発言や態度のすべてが「県民へのメッセージ」となります。
その中で、
- 男性には形式的で丁寧な言葉、
- 女性には軽く、馴れ馴れしい言葉、
という差があれば、県民に与える印象は極めて悪いものになります。
行政の信頼は「誠実さ」と「公平さ」の両輪で成り立ちます。
一方で虚偽発言(前回記事)により誠実さを失い、もう一方でジェンダー差別的態度によって平等性を失った——これが現在の兵庫県政の実情です。
「無意識」だからこそ危険なバイアス
「自然な流れ」という言葉に象徴されるように、知事自身は自覚なく差別的行動を取っている可能性があります。
しかし、社会心理学的に見ると、無意識の差別ほど修正が難しいのです。
行政の長がその危険性を理解していないこと自体が、県庁組織全体のジェンダー平等推進の足かせとなりかねません。
このような「差別の再生産」は、現場職員や県民の意識にまで波及します。
信頼喪失の連鎖:誠実性の次は平等性
これまでの斎藤知事には、
- 第三者委員会報告を否定する発言(誠実性の欠如)
- 「記者クラブ総会が決めた」という虚偽説明(説明責任の欠如)
がすでに指摘されてきました。
そして今回の「女性への態度差」は、平等性の欠如を示す新たな証拠です。
虚偽と差別、二つの問題が重なったとき、
行政トップとしての信頼は完全に崩壊します。
兵庫県政は今、誠実性・平等性・透明性という行政の三本柱をすべて失いかけています。
無意識の差別意識が起こした問題
元県民局長の告発文に対して「徹底的に調べろ」と指示したことは、歯向かう部下は容赦しないと言う差別意識から出たものです。
また、元県民局長の私的情報が県議に漏洩した問題でも、井ノ本元総務部長に罪を擦り付けるのも、部下は自分の意のままに従え。と言う差別意識から来るものです。
このような差別意識に支配されている県政は、今後も様々な差別により、県職員や県民に被害を与え続けると思います。
構造的リーダーシップ欠如の露呈
「嘘をつく」「責任を転嫁する」「性別で態度を変える」——
この三点がすべて揃った今、斎藤知事のリーダーシップは、もはや組織を導くものではなく、信頼を破壊する構造的要因そのものとなっています。
行政の透明性・説明責任・ジェンダー平等という基本原則を軽視する姿勢を改めない限り、兵庫県政の信頼回復は極めて困難です。
斎藤知事の言動は、もう県の組織を健全に維持することは出来ない状況になっていると推測されます。
新たな県知事が誕生しても、破壊されてしまった県の組織を立て直すのに何年要するのか?
兵庫県はもう危険な領域に突入しています。すでに顕在化している問題も出て来ています。