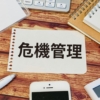【県民不在の県政】斎藤元彦知事が守っているのは県民ではなく「自分のプライド」──自分のための政治がもたらす崩壊
目次
「県民のため」ではなく「自分のため」の会見
2025年11月4日の定例会見──
マイナンバーを含む情報漏洩が発生したにもかかわらず、斎藤元彦知事は、公式な謝罪も説明も行わなかった。
「担当部局が詳細を確認したので発表した」
「私はぶら下がりで対応している」
この発言が示しているのは、「県民の不安を取り除くための説明」ではなく、「自分が責任を問われないための言い訳」だ。
行政の長としての行動ではなく、自己防衛の反射行動にすぎない。
プライドを守るための“説明拒否”
斎藤知事の対応には一貫した特徴がある。
- 第三者委員会の「違法認定」を否定
- 百条委員会の「虚偽答弁指摘」を無視
- パワハラ10件認定にも処分なし
- はばタンPay+情報漏洩には謝罪なし
どの局面でも、「自分の非を認めない」姿勢が際立つ。
つまり、県民への説明よりも自分のプライドを守ることを優先しているのだ。
県民不在の県政運営──責任の所在が“自己中心”
政治における「説明責任」とは、権力の行使を県民の理解と信頼によって正当化することだ。
しかし斎藤知事の県政では、この原則が完全に崩壊している。
| 問題 | 県民が求めている説明 | 知事の対応 |
|---|---|---|
| 情報漏洩 | 被害範囲と再発防止策 | 「担当部局が対応」 |
| 文書問題 | なぜ探索を指示したのか | 「指示した認識はない」 |
| 公選法違反容疑 | 調査経過と見解 | 「適法の認識に変わりはない」 |
| 百条委員会報告 | 虚偽答弁の有無 | 「真摯に受け止める」 |
──いずれも、県民の疑問には答えず、自分の立場だけを守る。
その結果、県政の中心にあるべき「県民」が、完全に置き去りにされている。
「プライド政治」がもたらす三重の害
斎藤県政の“自己防衛型政治”は、次の三つの害をもたらしている。
- 行政の信頼喪失
責任を取らないトップの下では、職員も本音を言えなくなる。
現場の士気が低下し、行政の判断力が鈍る。 - 政策の形骸化
「見栄え」「発信」「遠足」重視のPR型県政となり、中身よりも写真・SNSが優先される。 - 県民の政治離れ
「どうせ追及しても無駄」という無力感が広がり、民主主義の根が静かに枯れていく。
危機時にこそ見える“本当のリーダーシップ”
危機の場面は、リーダーの本性を最もよく表す。
- 県民の安全を第一に考える人は、真っ先に謝罪する。
- 自分のプライドを守る人は、責任を回避する。
斎藤知事の対応を見れば、どちらを選んだかは明らかだ。
県民を守るよりも、自分の「権威」と「メンツ」を守った。
その瞬間に、政治家としての使命は終わっている。
もはや“県民の代表”ではない
県民に寄り添う」「県民の信頼に応える」という言葉を、斎藤知事は繰り返してきた。
しかし、行動が伴わない言葉は空虚だ。
今や兵庫県政は、“県民不在”の県政に転落している。
説明せず、謝罪せず、責任を取らない。
その政治はもはや「県民のため」ではなく、「自分のため」の政治である。
フィールドパビリオンin淡路①/淡路市江井地区で線香づくりの職人体験をしました。淡路島西海岸の江井浦では、江戸時代の海運業の繁栄を礎に線香づくりが始まり、今では日本一の生産量を誇る地場産業として受け継がれています。職人の指導のもと、「盆切」と「生付け」という工程に挑戦しました。筋は… https://t.co/U6Ex3B3yMy pic.twitter.com/O6esMiE3Ha
— 兵庫県知事 さいとう元彦 (@motohikosaitoH) November 7, 2025
危機下での“観光ポスト”は何を意味するのか
現在、兵庫県政では
- はばタンPay+でのマイナンバー情報漏洩(総務省報告レベル)
- 第三者委員会による「知事指示の可能性が高い」認定
- 百条委員会での虚偽説明疑惑
- 記者会見での答弁崩壊、県民説明責任の欠如
など、行政の信頼を根底から揺るがす重大局面が続いています。
その最中に、知事自らがX(旧Twitter)で
「線香づくり体験」「筋は悪くないとのお言葉をいただきました」
と投稿している。
この「無邪気さ」は、危機管理意識の欠如というよりも、“危機そのものを認識していない”統治麻痺状態とさえ言えます。
「優先順位を見誤るリーダー」は信頼を回復できない
行政のリーダーは、発信内容の“優先順位”で信頼を左右します。
今のタイミングで県民が知りたいのは、「淡路の線香の歴史」ではなく、「情報漏洩の全容と再発防止策」「誰が責任を取るのか」ではないでしょうか。
それにも関わらず、知事が「筋は悪くない」と笑顔で発信しているのは、危機対応よりも自己演出(イメージづくり)を優先している証拠です。
この「現実逃避的PR政治」は、もはや県政の病理的特徴になりつつあります。
“HFP”という舞台装置に逃げ込む構図
この投稿は「HYOGOフィールドパビリオン」関連の企画として発信されています。
HFPは元々、万博に合わせて兵庫の地域資源を発信するプロジェクトですが、知事のSNSでは「遠足のような地方巡り」の道具になっており、もはや政策発信ではなく**“イメージ消費”の舞台**と化しています。
本来、フィールドパビリオンは“地域が主役”の取り組みであるべきですが、知事個人の広報演出に使われている現状は、事業の趣旨そのものを損なっています。
「県民感覚」との乖離
ばタンPay+の情報漏洩に不安を抱く県民、文書問題で行政不信を募らせる職員、自治体の信頼失墜に懸念を抱く地方議員。
こうした現実に直面している県民にとって、知事が「線香づくりを体験」「筋は悪くない」と発信する姿は、**“他人事のような知事”**という印象しか残りません。
本来、こうした文化発信は平時の県政が信頼されてこそ意味を持ちます。
危機のさなかで発信するのは、まるで**「火事の中で記念写真を撮っている」**ようなものです。
優先順位を失ったリーダーに、危機は収拾できない
斎藤知事の投稿には悪意はないかもしれません。
しかし、その「善意のPR」が、いまや現実を見ない統治姿勢の象徴になっています。
・危機対応よりSNS発信
・説明よりイメージ演出
・県民より自己満足
──この3つの傾向こそ、兵庫県政を蝕む“慢性疾患”です。
危機の時ほど、「何を発信しないか」「何を最優先するか」が問われます。
そして今の兵庫県政には、その判断力が決定的に欠けています。
県民の不安に対する丁寧な説明は全く行わず、自己満足のために県知事と言う地位を利用し続ける斎藤知事。
この知事は、災害が起こっても災害対策についての発信はせず、地場産品の発信をするのだろうか。