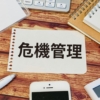斎藤元彦知事、障害者スポーツ大会を欠席して祭り観覧?優先順位を問う声も【兵庫県】
目次
兵庫県選手団の出発を前に——知事の姿はなし
兵庫県代表選手を激励する「全国障害者スポーツ大会兵庫県選手団結団式」が開催された。
この式典は、全国大会に挑む県代表選手たちの士気を高める重要な行事であり、県知事としての出席が期待される場でもある。
しかし、当日出席したのは服部副知事。代理として応援メッセージを述べたという。
一方の斎藤元彦知事は、同じ日に「灘のけんか祭り」を訪問していた。
知事はSNSで「祭りの活気」をアピール
斎藤知事は自身のSNSで次のように投稿している。
「播州では秋祭りが本格化しています。本日、播州姫路の『灘のけんか祭り』に伺いました。
屋台が激しくぶつかり合う練りの迫力は圧倒的です。五穀豊穣を祝う伝統文化であると同時に、地域社会に活気をもたらす祭りは、地域の核となる大切な存在です。
担ぎ手の確保など様々な課題に対応しながら、次世代へ引き継ごうとする関係者の皆さまのご尽力に、心より敬意を表します。」
文化行事の意義を発信する姿勢は理解できるが、同日に県全体の代表行事が行われていたとなると、知事としての行動の優先順位が問われる。
播州では秋祭りが本格化しています。本日、播州姫路の「灘のけんか祭り」に伺いました。屋台が激しくぶつかり合う練りの迫力は圧倒的です。五穀豊穣を祝う伝統文化であると同時に、地域社会に活気をもたらす祭りは、地域の核となる大切な存在です。担ぎ手の確保など様々な課題に対応しながら、次世代へ… pic.twitter.com/ziIctwshXu
— 兵庫県知事 さいとう元彦 (@motohikosaitoH) October 15, 2025
公務より「パフォーマンス」重視?
障害者スポーツ大会は、共生社会の実現を象徴する全国的な取り組みであり、知事が出席して選手を激励することには大きな意味がある。
一方で、「灘のけんか祭り」は地域の伝統行事とはいえ、知事が公務より優先して観覧する理由は見えにくい。
特に、SNSでの発信内容が「地域活性」や「伝統文化の継承」といった一般的なコメントにとどまっている点も、「支持者向けのパフォーマンスだったのではないか」という疑念を強めている。
優先順位を誤ったと言われても仕方がない判断
服部副知事による代理出席は行政手続き上の問題ではないが、県民の印象としては「障害者スポーツより祭りを優先した」と映る。
障害者や支援者の立場からすれば、
「知事に応援してもらいたかった」
という思いがあったはずだ。
斎藤知事の行動は、法的な問題こそないものの、公務の優先順位を誤ったと言われても仕方がない判断 だったのではないだろうか。
投稿の印象:公務より「観光インフルエンサー」的
斎藤知事の投稿群は、全て次のような特徴を持っています:
- 「訪問報告」+「ご当地紹介」+「観光誘致・食文化PR」
- 県の課題や政策判断への言及が少なく、ポジティブな話題中心
- 「〜に伺いました」「〜を体験しました」「〜をいただきました」といった個人目線の旅行記調
つまり、「知事としての政治判断・説明」よりも、
“旅する県知事”というイメージづくりに重点を置いている構成です。
これにより、「知事って観光地を巡ってるだけじゃないの?」という印象を受ける人が増えています。
実際の公務とのギャップ
知事の公務は本来、
- 予算・条例の策定、県議会対応
- 行政機関の監督と指揮
- 危機管理(災害・不祥事・政策判断)
などが中心です。
しかし斎藤知事のSNS発信は、そうした「県政の核心部分」に触れず、
観光・イベント・食文化・PR系に偏っています。
特に問題視されるのは、県政の信頼性が問われている時期(文書問題・第三者委員会報告直後など)にも、トーンを変えずに“笑顔の地域訪問”投稿を続けていることです。
「楽そうに見える」理由
もう少し具体的に言語化すると、こうなります。
| 要素 | 内容 | 県民の受け止め方 |
|---|---|---|
| 投稿内容 | 観光・グルメ・体験系 | 「仕事というより遊びに見える」 |
| 表現トーン | 常にポジティブ、トラブル・問題に触れない | 「都合の悪い話を避けてる」 |
| 写真構成 | 笑顔・食事・地域交流のショット中心 | 「公務というよりSNS映え」 |
| タイミング | 不祥事直後でも同じ投稿テンション | 「空気が読めていない」 |
つまり、実際に仕事が楽かどうかではなく、“そう見せてしまっている”広報戦略が問題なのです。
他県知事との比較
たとえば、
長崎県の大石賢吾知事
石木ダムについて、「知事は現場の景色が変わったって言ってるけど、分からないんだよね」という意見がありました。県HPを見てみましたが、確かに更なる工夫が必要ですね。改めて、みんなで考えます。… https://t.co/YzJaO5jDq2 pic.twitter.com/rdjpAQ7xhw
— 大石賢吾(長崎県知事) (@OishiKengo) September 1, 2025
北海道の鈴木直道知事
AI政策の推進については、誘致を進めているAIデータセンターの集積などを活かし、全道でAIの研究開発や活用に取り組みます。
— 鈴木直道(北海道知事) (@suzukinaomichi) June 20, 2025
また、国のAI基本計画の検討状況を注視しつつ、デジタル産業や半導体などの関連分野も広く含めた推進方策を取りまとめ、本道の活性化に繋げていきます。
埼玉県の大野ともひろ知事
★埼玉大学で学生の皆さんと意見交換会を行いました
— 大野もとひろ 埼玉県知事 (@oonomotohiro) October 16, 2025
おはようございます。
昨日は埼玉大学で学生の皆さんから「所有者不明土地の有効活用」など5つのテーマで政策提言をいただきました。
それぞれ若者らしい感性と新たな発想に根差した具体的な内容ばかりで、大いに考えさせられ、刺激を受けました。… pic.twitter.com/N2PfZ8Iiyd
などは、地域紹介も行いますが、必ずその裏に政策課題や行政的意義を結びつけています。
「○○を視察→課題発見→今後の対策を検討」といった形です。
勿論、自撮り写真などは全くありません。
対して斎藤知事の場合は、
「行きました→楽しかった→関係者に敬意」
で終わってしまう。
そのため、県政運営より**“発信のための行動”**に見えてしまうのです。
■ まとめ
- 「全国障害者スポーツ大会兵庫県選手団結団式」は、県を代表する公式行事。
- 当日は服部副知事が代理出席。
- 斎藤知事は「灘のけんか祭り」を訪問し、SNSで発信。
- 行政的には問題がなくても、知事の公務姿勢として疑問が残る。
県民の代表として、どの場に立つべきだったのか——
斎藤知事の「優先順位の判断」が問われている。