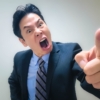斎藤知事は、司法が違法と認めなければ責任を取らなくても良いのか?
斎藤信者の中には、「司法の判断が出ていないのだから斎藤知事は違法では無い」と言う人がいますが、司法の判断が出ていなければ違法では無く、斎藤知事は責任を取らなくても良いのでしょうか?
目次
「違法」の意味には2種類ある
司法判断上の違法(法的責任)
裁判所が違法と認定した場合、損害賠償や刑事罰といった法的責任を負います。
→ 裁判で「違法ではない」と判断されれば、法的には責任を問われないことになります。
行政・政治上の違法・不適切(政治的・倫理的責任)
裁判所の判断がなくても、第三者委員会の調査や住民からの批判により「不適切」「違法の疑いが強い」とされれば、知事としての政治責任を問われることになります。
→ 裁判で決着していなくても、住民や議会に対して説明責任を果たす必要があります。
知事の立場で重要なのは「説明責任」
知事は地方自治法や憲法に基づき「住民の代表」として行政を担います。
したがって「裁判で違法とされなければ責任を取らなくてよい」という態度は、法的には一理あるように見えても、政治的責任や道義的責任から逃れる理由にはならないのです。
多くの知事や大臣が「違法と確定していない」段階で辞職・引責しているのは、まさにこのためです。
道義的責任が分からない」と斎藤知事が発言したことの問題点
公職者としての資質の疑問
知事は県民の代表であり、常に公的責任を伴う立場です。
その知事が「道義的責任が分からない」と公言することは、公職者としての資質や責任感が欠如していると受け止められます。
信頼回復の姿勢が見られない
不祥事が起きたときに最も重要なのは「法的に問題がなくても、住民の信頼をどう回復するか」です。
道義的責任を理解しない、あるいは軽視する態度は、信頼回復を放棄していると映ります。
議会との信頼関係を壊す
百条委員会は地方自治法に基づき、住民のために真相を究明する場です。
そこで「道義的責任が分からない」と発言すれば、議会軽視・住民軽視と受け取られ、議会との対立を深めます。
県民への悪影響
住民は「知事は責任を取らなくてもよい」と考えていると感じ、不信感を募らせます。
また、マスメディアで報道される斎藤知事の言動に対して、疑問を感じる他の都道府県民から兵庫県民が侮辱されます。
その結果、県政への協力姿勢が弱まり、政策推進力が落ちる危険があります。
道義的責任を理解していた他の事例との対比
過去には、法的には違法でなかったが、道義的責任を重く受け止めて辞任した大臣・知事が数多くいます。
- 例:領収書の記載ミス、会食問題、秘書の不祥事など。
彼らが辞任した理由は「道義的責任を果たすことが信頼回復の第一歩」と認識していたからです。
斎藤知事の「分からない」という発言は、こうした政治家の基本姿勢と対照的であり、日本の政治文化・倫理観に逆行しています。
111万票で再選されたことは「政治的な支持の証明」にはなりますが、「免罪符」にはなりません
選挙の意味
選挙は「住民が次の任期も知事として任せるか」を判断する仕組みです。
したがって、再選=一定の有権者が支持したことは事実です。
ただしこれは「信任投票」的な側面であって、過去の行為を白紙に戻すことを意味しません。
免罪符にならない理由
法的責任は消えない
選挙で当選しても、過去の違法行為が「なかったこと」にはなりません。
刑事告発や民事訴訟があれば、選挙結果に関わらず司法判断が下されます。
現に、複数の刑事告発がなされており、検察の判断を待っている状態です。
道義的責任も残る
選挙で勝ったとしても「説明責任を果たさなかった」「信頼を失った」という評価は消えません。
多くの政治家は、選挙後も道義的責任を問われ続けています。
投票の理由は多様
有権者の投票理由は「政策への期待」「SNSにばら撒かれた真偽不明の情報を信じた」「二馬力選挙」など様々です。
そのため、必ずしも「問題行為を許した」という意味ではありません。
むしろ再選後に重くなる責任
再選されたということは、県民が「もう一度任せた」わけです。
その後に同じ問題が続けば、「二度目の裏切り」として信頼を大きく損ねるリスクがあります。
よって、再選は免罪符ではなく、むしろ「より厳しい説明責任・高い倫理性」が求められる立場に自ら立ったとも言えます。
再選後に第三者委員会が認定した公益通報者保護法違反は説明責任が求められる
再選後に、百条委員会から「違法の可能性」。第三者委員会から「違法」と認定された公益通報者保護法違反については、有権者が納得の行く説明責任が求められます。
「当時の対応は適切」「ご指摘は真摯に受け止めます」は、説明責任を果たしているとは絶対に言えませんし、違法と認定されたことに対する道義的、政治的、倫理的な責任があります。
斎藤知事が「説明責任」を果たさないことで起こる問題
住民の信頼を失う
知事は住民の代表であり、県政を預かる立場です。
説明責任を果たさない姿勢は、住民から見れば「不誠実」「隠蔽的」と映り、行政への信頼を大きく損なう結果になります。
信頼が失われると、住民が県の施策に協力しなくなり、政策実行力が低下します。
職員の士気が低下する
知事が説明を避け、問題をうやむやにすると、職員は「知事を信頼できない」「責任を取らないトップのために働きたくない」と感じます。
その結果、県庁内部で士気が下がり、優秀な人材の流出や組織の停滞を招きます。
議会やマスコミとの対立を深める
本来、議会や記者会見は住民への説明の場です。
そこで曖昧な発言や矛盾した説明を続ければ、「知事は説明責任を放棄している」と見なされ、議会から追及され、マスコミにも批判的に報じられます。
こうして「説明不足→批判拡大→さらに説明を避ける」という悪循環に陥ります。
長期的には県政運営全体が不安定になる
説明責任を果たさないトップのもとでは、県政が常に「不信感」という影を背負います。
県民・職員・議会・マスコミの協力が得られず、政策推進力が低下。
結果的に「県政の停滞」「住民生活への悪影響」につながります。
司法判断だけに依存する危うさ
行政の不正や不祥事は、必ずしも裁判に持ち込まれるとは限りません。
裁判になっても、長期間かかり、最終的に「違法ではない」と判断されることもあります。
それでも「住民の信頼を著しく損なった」場合、知事には政治的に責任を取ることが求められます。