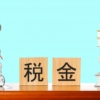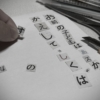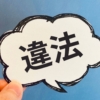内部告発を一般人経由で受け取った場合の法的責任 ― 斎藤知事の『通報者探索』は公益通報者保護法違反か
目次
前提条件
対象法令:改正後公益通報者保護法(令和4年施行)
事案:
・兵庫県知事が「3月文書」を一般人(県職員ではない)から受け取った。
・知事はそれを公益通報と認識しなかった。
・その後、県内部で文書の作成者(通報者)を特定するための探索を指示・実施した。
公益通報者保護法の保護対象の確認
公益通報者保護法の保護対象は次の3類型です(第2条):
- 労働者による内部通報(事業者に対して)
- 労働者による外部通報(行政機関等に対して)
- 労働者による公表通報(報道機関等に対して)
ここでいう「労働者」には、
- 正規・非正規を問わない職員、
- 自治体職員(地方公務員)も含まれます。
「一般人から受け取った」場合の扱い
質問では「知事が一般人から文書を受け取った」とあります。つまり、「県職員ではない人」からの情報提供なら、公益通報者保護法の保護対象外 です。
この場合、その「一般人」は労働者ではなく、法律上の「公益通報者」に該当しません。
したがって、公益通報者保護法違反にはなりません。
ただし、「実質的に内部通報と同視できる」場合
しかし、仮にその文書が県職員が作成した内部文書(内部告発)で、「一般人」経由で知事に届いたものだったとすれば、実質的には「内部通報」情報を知事が受け取ったことになります。
この場合、
- 知事がその通報内容を「公益通報」と認識すべき状況であったのに、
- 通報者を特定しようとした
となると、法第12条(不利益取扱いの禁止)および第13条(通報者特定禁止)に抵触する可能性があります。
文書の内容から見えること
「告発文書」には 県庁内部でしか知り得ない具体的情報 が複数含まれていました。
したがって、受け取った時点で斎藤知事や側近は、「この文書は県職員による内部文書(内部告発)だ」と容易に判断できる内容だったと考えられます。
知事側の行動が示す認識
報道や県の説明によれば、知事と側近は、
「複数の県職員が作成・配布した可能性があるとして、職員に調査を行った」
としています。
つまり、
「職員が関与している可能性を前提に調査を行った」
ということです。
これはすなわち、知事が「内部職員による告発文書」であると認識していたことを意味します。
兵庫県・斎藤知事が定例会見 パワハラ疑惑告発文書問題で経緯説明(2024年8月7日)
知事:
私が記憶しているのは、その時、片山元副知事はじめ、幹部職員から2点あり、1点目が、令和6年2月に県民局長メッセージという形で、県政のあり方を疑問視するというような内容が書かれていたということです。
それともう1点が、文書の内容から、県の人事に精通している方が作成されたと推測されるということでした。
例えば、それまでの人事のルール無視でトントン拍子に昇進とか、様々な観点から人事の精通される方がやったのではないかということから、元県民局長が文書を作成した可能性が高いのではないかとその時説明を受けました。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20240807.html(出典:兵庫県)
そうなると法的な位置づけは?
このように、
- 内容的に内部情報であり、
- 行動的にも職員作成を前提に調査している、
となると、たとえ形式的には「一般人」経由で届いたとしても、実質的には「内部通報情報」を受け取ったのと同視できます。
そのため、斎藤知事がその情報を「公益通報にあたる可能性のある内部通報」として扱う義務を負っていたと解釈されます。
それでも通報者探索を行った場合
もしその状況下で、知事が通報者を特定しようとしたなら、公益通報者保護法の
- 第12条(不利益取扱いの禁止)
- 第11条(通報者特定禁止)
のいずれか、または両方に抵触する可能性が高いです。
特に第13条は、「通報者を特定する行為自体」を禁止しているため、実際に特定したかどうかよりも、「特定しようとした行為」が問題になります。
一般人から受け取った文書を無視すれば何も問題は無かった
一般人から受け取った文書の時点では、公益通報では無かったので、斎藤知事が無視していれば何も問題は無かったのですが、文書を作成したのが、県職員であると考えて、対象者をリストアップして探索した時点でアウトです。
斎藤知事が、片山元副知事や県幹部に対して「徹底的に調べろ」と指示をした張本人なので、斎藤知事が公益通報者保護法違反です。
違法・不適切とされ得る理由
旧法の時点でも、
行政機関には「公益通報者の保護義務」や「不利益取扱い禁止(第12条)」が定められており、
通報者を探し出そうとする行為は、次のように解釈されていました。
- 通報者を探し出そうとすれば、不利益取扱いのリスクが高まるため、
法の趣旨(保護目的)に反する行為とみなされる。 - 消費者庁(所管官庁)も、行政解釈として
「通報者を探索する行為は、保護法の趣旨に反する不適切な行為」との見解を示していた。
つまり、旧法下でも明確に禁止されていなくても、違法性・不当性が指摘されうる行為でした。
第三者委員会・メディアでの議論との関係
兵庫県の第三者委員会も、
「文書が公益通報に当たるかどうか」ではなく、「その可能性を排除できない段階で通報者探索を行ったこと」自体が問題だと指摘しています。
つまり、
「公益通報だと確定していなくても、そうである可能性がある段階では、慎重対応が求められる」
というのが法の趣旨です。