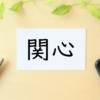斎藤知事をめぐる議会の動き(不信任に踏み切れない事情)
百条委員会の報告書も無視して、その他の刑事告発や公益通報者保護法違反についても説明責任を果たさず、議会を軽視する斎藤知事に対して、兵庫県議会は不信任案を出さないのは何故なのか?
目次
不信任案提出のハードル
- 知事に対する不信任決議案は、議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が賛成すると不信任決議ができます。
- 与党会派(自民党・公明党・維新の会など)が一定数を占めているため、野党が単独で提出しても可決には至りません。
- 議員たちは「どうせ否決される」と見込むと、提案すら避ける傾向があります。
与党会派の事情
- 与党側は、知事を支える立場にあるため「不信任=政権放棄」となり、自分たちの政治的立場や次の選挙への影響が大きいのです。
- 斎藤知事を全面的に支持しているわけではなくても、「今辞めさせれば県政が混乱する」として、追及を避けている可能性があります。
「説明責任不足」を容認する体質
- 議会自体が知事と距離を置いて対立するよりも、「次の予算」や「地元事業」で妥協を重ねる体質にあるため、正面から不信任という形を取らない傾向が強い。
- 日本の地方議会では特に「チェック機能よりも調整役」が優先される構造的な問題があります。
- 問題が起きてから時間が経過しており、議会と知事の関係が「なあなあ」になって来ており、県民の分断もそのうち収まるとの甘い考え。
政治的リスクの回避
- 不信任案が可決されると、知事は議会解散か辞職かを選ばなければなりません。
- 議会解散となれば、議員は自分の選挙を戦うリスクを負います。
- 多くの議員は「そこまでのリスクを取るのは得策ではない」と考えて、追及を控えます。
世論の動向を伺っている
- 111万票を得て再選されたという事実があり、議員にとっては「県民が再び選んだ知事を、不信任で覆すのは難しい」という心理的抵抗もあります。
- 世論が大きく「辞任すべき」という流れにならない限り、議会も動きづらいのです。
不信任案可決 → 知事の選択肢
地方自治法では、不信任案が可決されると知事は以下の二択を迫られます。
- 知事が辞職する
- 議会を解散し、再選挙に持ち込む
仮に再選挙で斎藤知事が再選された場合
「県民が改めて信任した」という解釈が成り立ちます。
→ この時点で、議会が「不信任」という重い判断を下したことが県民意思と逆行した、と見なされる。
結果として、議会に対して
- 「県民の意思を無視した」
- 「無駄に混乱を招いた」
- 「税金を使って不要な選挙をした」
といった批判が集中する可能性が高いです。
議会側のリスク
議会解散が選ばれた場合、議員自身が選挙を戦うことになります。その際、斎藤知事支持者が多ければ「知事を支持する議員を選ぶべき」という空気が強まり、不信任に賛成した議員が落選リスクを負うことになります。
「斎藤知事は辞任すべき」と言う世論形成が重要
個別の議員がどれだけ斎藤知事に対して、疑問や不適任と考えていても、最終的に判断するのは有権者です。
その有権者が「斎藤知事は辞任すべき」と言う世論に傾かなければ、不信任案の提出は難しいと言うことなのです。
斎藤知事への不信任決議、自民・維新ら「適切だった」…兵庫県議会6会派それぞれの思いは?読売新聞がアンケート(2025年9月24日)
「斎藤知事への不信任決議、自民・維新ら「適切だった」…兵庫県議会6会派それぞれの思いは?読売新聞がアンケート」
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20250923-OYO1T50034(出典:読売新聞 2025年9月24日)
斎藤元彦知事の不信任、全会一致決議から1年…支持・不支持で割れる県議会(2025年9月19日)
「斎藤元彦知事の不信任、全会一致決議から1年…支持・不支持で割れる県議会」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250919-OYT1T50032(出典:読売新聞 2025年9月19日)
斎藤知事に説明責任求めるも…水面下に終わった決議案 県議会が閉会(2025年6月12日)
兵庫県議会の6月定例会は12日、閉会した。県の情報漏洩(ろうえい)の責任をとるとして斎藤元彦知事が提出していた自身の給料削減案は、賛成多数で継続審査となった。斎藤知事に説明責任を求める声は高まったが、決議などの具体的な動きにはつながらなかった。
「斎藤知事に説明責任求めるも…水面下に終わった決議案 県議会が閉会」
https://www.asahi.com/articles/AST6D3G3XT6DOXIE018M.html(出典:朝日新聞 2025年6月12日)