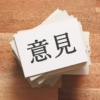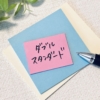兵庫県の「特別弁護士」判断は恣意的に誘導された可能性― 藤原弁護士への懲戒請求「棄却」の裏にある構図 ―
兵庫県弁護士会は、兵庫県の藤原特別弁護士に依頼した法的助言について、懲戒請求を棄却しました。しかし、その判断理由を読み解くと、兵庫県が「限定的な情報のみ」を提示し、その範囲で法的見解を引き出した可能性が浮かび上がります。
今回の綱紀委員会文書から見えてくるのは、弁護士の責任ではなく、行政による情報操作の疑いです。
別件ですが知事の対応は、公益通報者保護法に違反しないという、兵庫県弁護士会の決定が出ました。 pic.twitter.com/989pf3UVdd
— 日美 (@himidaisuke) November 2, 2025
目次
懲戒請求が棄却された理由
兵庫県弁護士会綱紀委員会の決定文書(令和7年9月30日付)によると、
対象となった藤原弁護士は、兵庫県総務部人事課から令和6年3月に依頼を受け、
「事実関係の調査」ではなく「法的助言」に応じた立場だったとされています。
文書には次のような趣旨が記されています。
「対象弁護士は、兵庫県の総務部人事課から依頼を受け、事実調査ではなく法的相談に応じたものであり、人事課から示された資料を前提に法的見解を回答した。
限定された判断材料に基づく法的解釈をしたにとどまる。」
つまり、藤原弁護士は「兵庫県が提示した限定的な情報」だけを材料に、その範囲内で一般的な法的見解を示したにすぎず、弁護士倫理上の問題は認められないと判断されたのです。
兵庫県による「情報の限定」と判断誘導の疑い
この判断は、一見すると「弁護士に非がない」という結論に見えます。
しかし、その裏を返せば、兵庫県が与えた情報の内容と範囲に問題があった可能性が浮かび上がります。
たとえば、もし県が当初から
- 「公益通報者保護法違反の疑いがある」
- 「内部通報者を探索した」
といった重要な前提を伏せていた場合、
弁護士は当然「そのような違法性はない」と誤った判断を下す恐れがあります。
このような状況では、弁護士の責任ではなく、相談内容を意図的に制限した行政側の恣意的行為が問われるべきです。
実際、綱紀委員会文書も「限定された資料」「限定された判断材料」という表現を繰り返しており、県が恣意的に事実を絞り込んでいた可能性を強く示唆しています。
時系列で見る「弁護士意見」依頼の背景
3月27日: 斎藤知事が記者会見で、匿名文書について「嘘八百」「公務員失格」などと強い言葉で否定し、同時に「徹底的に調べろ」と通報者探索を指示。この時点で、知事はすでに“匿名文書=不正な内部告発”と断定していました。
その直後(4月1日):
兵庫県総務部人事課が藤原弁護士に「法的助言」を依頼。
依頼内容は、文書を作成・拡散した職員への処分可否や行為が公益通報者保護法上の「通報」にあたるかどうか、というものでした。
つまり:
知事が先に“違法ではない方向性”を公に打ち出し、その後に「法的裏付け」を取る形で弁護士意見を求めた、**「事後的な正当化のための照会」**であった可能性が極めて高いのです。
綱紀委員会文書が示す“恣意的な構図”
文書では、弁護士が「限定された資料の範囲で回答した」と明記されています。
これが意味するのは次の通りです。
兵庫県が提示した情報には、「知事による通報者探索」「職員への圧力」「公益通報の定義に該当する具体的行為」など、
知事に不利な事実が含まれていなかった可能性が高い。
結果として、藤原弁護士は「外形的に見れば違法とは言えない」という**“部分的・限定的な見解”**を出しただけで、それを県が「法的に問題なし」と拡大解釈して利用した、という構図です。
目的は「通報者保護法違反の否定」だった可能性
公益通報者保護法では、通報者の特定・探索行為は明確に禁止されています。
もし、通報者探索を「公益通報ではない」と位置づけられれば、
- 知事による探索や懲戒は正当化され、
- 県の法的リスク(違法行為・損害賠償責任)が回避できる。
したがって、知事や県にとって最大の関心は、「これは公益通報ではない」という**“お墨付き”**を弁護士から得ることだったと考えられます。
弁護士判断を「盾」にする行政の構図
兵庫県はこれまでも、「特別弁護士の意見」を根拠に自らの対応の正当性を主張してきました。
しかし、今回の文書で明らかになったように、その「意見」や「見解」が県の都合のよい限定情報のもとで導かれたものであれば、実質的には行政が「望む結論を引き出した」にすぎません。
つまり、「弁護士が違法でないと言った」という主張は、その前提が恣意的であれば、行政の免罪符としての利用に過ぎないのです。
説明責任と再検証の必要性
兵庫県が藤原弁護士にどのような資料を提示し、どの範囲の事実を共有して法的助言を求めたのか――その過程を明らかにしない限り、この判断は不透明なままです。
もし、県が「第三者の独立した意見」を装いながら、実際には「限定された情報で特定の判断を引き出した」のであれば、それは行政倫理の重大な問題です。
県民に対して説明責任を果たすためにも、当時の相談文書・メール記録・法的照会の全文を開示し、恣意的誘導の有無を検証すべきです。
弁護士意見は「後付けの正当化」に使われた可能性
この綱紀委員会の判断は、「弁護士の行為には非がない」とするものでした。
しかし、それは同時に「行政側が恣意的に判断を誘導できる構造」を露わにしました。
藤原弁護士は「限定的な条件の中で回答した」だけ――つまり、問題の本質は兵庫県自身の情報操作と説明責任の欠如にあります。
要するに、
- 知事が先に「違法性なし」と断定
- その後、弁護士に限定情報だけを与え、同様の結論を補強させる
という流れは、行政内部での自己正当化ロジックの典型パターンです。
藤原弁護士の責任は限定的である一方、恣意的に情報を制御して結論を誘導した行政側(=斎藤知事および人事課)の責任は極めて重いと考えられます。