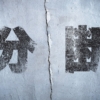兵庫県議会・総務常任委員会で露呈した「法律より知事の判断が優先される」矛盾
目次
公益通報者保護法の解釈を巡る“県と知事の一体化”の危うさ
総務常任委員会で浮かび上がった深刻な問題
令和7年11月17日の兵庫県議会・総務常任委員会では、伊藤傑県議の質問をきっかけに、
- 「国の法律」より「知事の判断」が優先されているのではないか?
- 公益通報者保護法の扱いに矛盾があるのではないか?
- 知事の判断を県組織全体に押し付けているのではないか?
という重大な問題がはっきりと露呈しました。
県執行部が繰り返す「法に基づいて判断している」という建前と、実際の運用との間に大きな乖離があることが、議論を通して明らかになったのです。
https://www.youtube.com/watch?v=neAcCsS2wLg
伊藤傑県議の質問:「法律と知事の判断のどちらが重要か?」
伊藤県議の問いかけは非常にシンプルでした。
国の法律と知事の判断では、どちらを優先すべきか?
もし知事が法律と違う判断をしたら、県職員はどちらを守ればいいのか?
これに対し、有田総務部長は次のように回答。
「法令に基づいて判断するのが大原則」
当然の答えですが、ここで伊藤県議は公益通報者保護法の3号通報の解釈へ話を進めます。
すると、有田部長は急に表情を曇らせて、
「所管外なので答えられない」
と逃げてしまいました。
まさに、建前と本音が真っ向から矛盾した瞬間でした。
知事の判断=「県の解釈」?
ここにある“人治主義”の危険性
増山県議・山本県議とのやり取りでさらに問題が明確になります。
有田総務部長は、
「結論に至るまでは相談している」
「最終的な判断は知事であり、それが県としての判断」
と答弁しました。
つまり構造としては、
- 職員が案をつくる
- 最終決定は知事
- 決まったものは“県の判断”として扱われる
という流れであると認めてしまったのです。
しかし、ここで最大の矛盾が生まれます。
公益通報者保護法の解釈で「国(消費者庁)」と明確にズレている
公益通報者保護法を巡っては、すでに消費者庁が、
- 兵庫県の対応に懸念を示している
- 斎藤知事の「発言訂正」を確認していないと国会で明言している
という状況です。
つまり、
国の法解釈と兵庫県の運用には大きな齟齬がある のです。
それにもかかわらず、兵庫県は消費者庁に対し、
「知事の解釈は、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がない」
と説明していると言われています。
これは、
- 法令に従うと言いながら、
- 実際には知事の自己正当化的な解釈をそのまま「県の判断」として押し通し、
- そのうえで“齟齬はない”と国に説明する
という非常に危うい構造です。
なぜ「今回の兵庫県の質疑」は消費者庁にとって大問題なのか
公益通報者保護制度を所管する消費者庁にとって、今回のように
地方自治体(兵庫県)が法の趣旨と異なる運用を行い、
それを組織ぐるみで正当化している疑いがある
という状況は、放置できない重大案件です。
以下、問題点を整理します。
① 法律(公益通報者保護法)より「知事の判断」を優先している構造が露呈
兵庫県は「法令に基づき判断している」と言いながら、実際には
- 最終的な判断=知事
- 知事の判断がそのまま“県の解釈”になる
と明言しています。
これは、
地方自治体が法の運用を“首長の恣意性”で左右できる
という危険な状態であり、法治主義に反します。
消費者庁の立場としては当然受け入れられません。
法の解釈は「国 → 地方」へ降りるものであり、地方の首長が勝手に解釈を変えることは許されない
からです。
② 消費者庁はすでに「斎藤知事の発言訂正は確認していない」と国会で明言済み
2025年11月10日の予算委員会で消費者庁の黄川田大臣は、
「斎藤知事から発言の訂正があったとは承知していない」
と答弁しています。
つまり、国(消費者庁)は、
- 兵庫県の公益通報者保護法の運用に疑義がある
- 少なくとも、県の説明と国の認識は一致していない
と公式に認めています。
その状況で、
「知事の判断=県の判断」
「県として国の法解釈を否定している」
という状態は、消費者庁の権威や法制度そのものを揺るがす重大問題です。
③ 兵庫県は消費者庁に「知事の解釈は、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がない」と説明している
兵庫県は消費者庁に対し、
「知事の解釈は、消費者庁の法解釈と齟齬はない」
と説明したとされています。
しかし今回の総務常任委員会では、
- 知事が最終判断
- それを県の判断として扱う
という構造が露わになりました。
つまり、
兵庫県は“知事個人の判断”を
“県組織の総意としての判断”と装って説明している
可能性があります。
これは消費者庁からすれば、
- 法の趣旨の歪曲
- 行政監督を欺く虚偽説明
- 中央官庁への不実報告の疑い
になり、重大な問題です。
④ 公益通報者保護制度の信頼性を揺るがす
公益通報者保護法は、日本全国の
- 行政
- 民間企業
- 医療・福祉
- 教育機関
すべてに適用される制度です。
兵庫県のような大規模自治体が
通報者保護よりも
内部の“首長の判断を守る”ことを優先している
と疑われるのは、制度全体の信頼が崩れるレベルの問題です。
消費者庁は全国への示しがつかなくなります。
⑤ 消費者庁としては「黙っていれば制度が崩壊する」状況
今回の兵庫県のやり取りは、消費者庁の立場から見て、
- 法制度の権威を損なう
- 国(消費者庁)の定めた法解釈を地方が勝手に変えている
- 県庁ぐるみで知事の判断を“公式解釈”として押し通している
- 国会での大臣答弁とも矛盾
という四重苦になります。
これは、消費者庁が絶対に放置できる案件ではありません。
むしろ、
「地方自治体が公益通報者保護法を正しく運用していない事例」
として国が是正指導を行うレベル
と言えます。
このやり取りは「兵庫県の問題」ではなく「国の行政制度の問題」に直結する
今回の総務常任委員会の発言は、
- 法律より知事の判断が優先
- 知事の判断を県の判断とする組織構造
- 公益通報者保護法の国との認識のズレ
- 消費者庁への虚偽説明の疑い
ーーという点で、
消費者庁としても看過できない重大問題
であることは明白です。
伊藤県議の指摘:「間違いを認めることは恥ずかしいことではない」
議論の最後、伊藤県議は奥谷県議の発言としてこう述べました。
「間違ったことを間違ったと認めるのは恥ずかしいことではない。
それを徹底してほしい」
これは単なる一般論ではありません。
- 知事の判断を守るために県庁全体が無理な説明を重ねている
- 法律よりも知事の発言を優先しようとしている
- 職員が「間違っている」と言い出しにくい雰囲気がある
こうした“組織の歪み”をただすべきだというメッセージです。
特に今回の議論では、
- 法治主義
- 組織ガバナンス
- 公益通報者保護法の運用
という県政の根幹に関わる問題が露わになりました。
兵庫県は「法治」ではなく「人治」に傾きつつあるのではないか
今回の総務常任委員会は、県庁組織が “法律より知事の判断を優先する体質” に近づいている現状を示しています。
- 法令に基づいて判断するという建前
- 現場が知事の判断に従わざるを得ない現実
- その知事の判断をそのまま“県の解釈”として国に説明する矛盾
- 公益通報者保護法の解釈を巡る国との認識のズレ
これは行政組織として極めて危険です。
県民が求めているのは、
知事のメンツを守る県政ではなく、
法律に基づき、公正で透明な県政運営
です。
今回の議会質疑は、その原点に立ち返る必要性を強く示していると言えるでしょう。