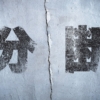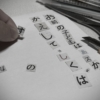「誰も自殺に追い込まれない兵庫」と現実の乖離──批判者への攻撃が生む“萎縮”と自殺リスクの深刻な矛盾
兵庫県は「誰も自殺に追い込まれることのない兵庫」を掲げ、自殺対策を県政の重要課題として位置づけています。しかし現実には、知事に批判的な質問をした記者がSNSで実名を晒され、所属する報道機関に抗議が殺到し、担当替えや取材制限が議論されるなど、深刻で異常な事態が進行中です。
さらに、県政に疑問を持つ県民や専門家の発言に対しても、誹謗中傷・攻撃が繰り返され、心理的な追い込みや孤立が生まれています。
本記事では、兵庫県が掲げる自殺対策の理念と、現実の県政周辺で起きている事態の矛盾を整理し、なぜこの状況が危険なのかを明らかにします。
目次
- 1 兵庫県の自殺対策が掲げる理念
- 2 批判的質問をした記者への“実名晒し”と攻撃の拡大
- 3 批判する県民や専門家への攻撃も深刻
- 4 表現の自由を“都合よく使い分ける”危険性
- 5 萎縮効果と民主主義への深刻な影響
- 6 「誰も自殺に追い込まれない兵庫」とは何か
- 7 行政トップが本来とるべき姿勢
- 8 元県民局長や竹内元県議の死と、斎藤知事の“矛盾した現実”を考える
- 9 元県民局長のケース──「嘘八百、公務員失格」発言と通報者探索
- 10 竹内元県議のケース──百条委員会の中心で重圧を受けていた
- 11 知事自身が生み出した環境──“批判者を追い詰める構造”
- 12 「どの口が言うのか」──県民の素朴で正当な感覚
- 13 本当に「誰も自殺に追い込まれない兵庫」を目指すなら
- 14 まとめ
兵庫県の自殺対策が掲げる理念
兵庫県の「自殺対策計画」では、次のような理念が強調されています。
- 誰も自殺に追い込まれない社会の実現
- 悩みを抱える人が安心して相談できる環境づくり
- 周囲の人が困っている人に気づき、温かく受け止める社会の形成
- 重点施策は「相談体制」「若者」「中高年」「女性」など、精神的配慮を伴う支援が中心
この理念からすれば、社会全体が温かさと理解で包まれ、誰も孤立しない環境が求められます。
しかし、現実にはこの理念と真逆の現象が起きています。
批判的質問をした記者への“実名晒し”と攻撃の拡大
知事の会見で厳しい質問を行った記者がSNS上で実名を晒され、誹謗中傷の対象になっています。
- SNSで実名と顔写真が拡散
- 所属報道機関に抗議が殺到
- 担当替えや取材活動の自粛が議論
- 専門家も「深刻で異常な事態」と警鐘
これは、単に「言論の対立」では済みません。
批判的な立場の人間が“公の場から排除される”構造
が生まれていることを意味します。
報道の自由に対する圧迫であると同時に、
当事者の精神的負担は計り知れず、
「誰も自殺に追い込まれない社会」とは真逆です。
批判する県民や専門家への攻撃も深刻
記者だけではありません。
県政に疑問を呈する県民、専門家、元県職員などに対しても、
- 誹謗中傷
- 侮辱
- 個人攻撃
- 根拠なきレッテル貼り
といった攻撃が繰り返され、「批判した側が精神的に追い込まれやすい環境」が形成されています。
本来、民主主義における批判は健全さを保つための重要な機能です。
しかし現在の兵庫では、批判者が“孤立し、晒され、攻撃される”構造が強まっています。
これは明らかに、県が掲げる自殺対策の理念と矛盾します。
表現の自由を“都合よく使い分ける”危険性
斎藤知事は、自分に都合のよい、反斎藤に対して攻撃するSNS投稿には「表現の自由」を強調し、最終的には「司法の判断」と発言しています。
しかし「表現の自由」は権利であると同時に、他者を攻撃し追い込んでよいという免罪符ではありません。
政治家がこの概念を選別的に使えば、支持者が過激化し、“攻撃は許されている”という誤った認識が広まり、批判者を追い込む圧力が加速します。
この構造は、精神的ストレス、自責感、孤立感を増幅させ、自殺リスクを高める最悪の環境です。
萎縮効果と民主主義への深刻な影響
批判しただけで攻撃される状況は、人々の心理に次のような影響を与えます。
- 「何も言わない方が安全だ」と考える
- 報道機関が質問を控える
- 県民が声を上げにくくなる
- 行政がチェックされなくなる
これは**萎縮効果**と呼ばれ、民主主義を静かに、しかし確実に破壊します。
このような環境下では、問題を指摘しただけで精神的に追い込まれ、「自殺に至ってもおかしくない状態」が現実的に生じ得ます。
「誰も自殺に追い込まれない兵庫」とは何か
本来、兵庫県が目指すべき姿は、
- 誹謗中傷で誰かが精神的に追い詰められないこと
- 批判的質問をした記者が攻撃されないこと
- 県政に意見を述べる県民が安心して声を上げられること
- 立場の弱い人が“晒されない”こと
であるはずです。
しかし現状は、“批判者が一番追い込まれやすい県”という皮肉な構造になっています。
行政トップが本来とるべき姿勢
状況改善のためには、知事自身が明確に次を表明すべきです。
- 批判する人への誹謗中傷を明確に否定する姿勢
- 実名晒しや攻撃的な投稿の鎮静化を呼びかけること
- 報道や県民の質問を尊重する姿勢の明確化
- “表現の自由”を特定の方向だけに適用しないこと
- 自殺対策計画の理念との整合性を説明すること
これが行われない限り、県が掲げる自殺対策は空文化し続けます。
元県民局長や竹内元県議の死と、斎藤知事の“矛盾した現実”を考える
斎藤知事は「誰も自殺に追い込まれることのない兵庫」を掲げ、自殺対策の強化を県政の最重要課題として語っています。しかし現実には、元県民局長、そして百条委員会で追及していた竹内元県議が相次いで亡くなりました。
お二人の死因は公式には「特定できない」とされていますが、それでも「斎藤知事の言動や県政運営との関係が完全にゼロとは言えない」と感じる県民が多いのは、極めて自然な反応です。
なぜなら、兵庫県自身が自殺についてこう説明しているからです。
「自殺は、様々な悩みが原因で心理的に追い込まれた末の死であり、自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥っていることが多い」
この言葉を踏まえると、県政によって精神的負荷を与えられた人がいた場合、それは十分に「遠因」になり得ます。
そして、そうした状況を生み出しておきながら、斎藤知事が「誰も自殺に追い込まれない兵庫」と語ることに、多くの県民が強烈な違和感を覚えているのです。
元県民局長のケース──「嘘八百、公務員失格」発言と通報者探索
元県民局長の死については、さまざまな背景が複合していたとされています。しかし、県が自ら認めている事実として、
- 知事が「嘘八百、公務員失格」と公の場で断定
- 公益通報者保護法があるにも関わらず通報者探索
- SNSでの誹謗中傷や攻撃が拡散
- 県側も“誤った初動”を認めた(通報者探索後に弁護士に相談)
これらが、元県民局長を精神的に追い詰めた可能性は否定できません。
県の自殺対策計画にはこう書かれています。
「悩みや不安を抱える者を温かく受け止め、孤立させないことが重要」
しかし、実際には県のトップの発言によって批判の集中砲火を浴びせられ、社会的孤立を加速させた構造が存在していました。
竹内元県議のケース──百条委員会の中心で重圧を受けていた
竹内元県議は、斎藤知事の「告発文書問題」を県議会特別委員会で追及する中心人物でした。
亡くなる直前には、
- 根拠なき誹謗中傷
- 「実名晒し」「陰謀論」的な攻撃
- 家族のもとにまで嫌がらせ
- 精神的消耗が深いと報道されていた
という状況に置かれていました。
死因は断定されていません。しかし、自殺について、
「複数の要因が積み重なった結果、心理的に追い詰められる」
のだとすれば、この環境が“遠因”にならなかったと言える人はいないはずです。
知事自身が生み出した環境──“批判者を追い詰める構造”
ここで重要なのは、元県民局長や竹内元県議のケースだけではありません。
現在の兵庫では、
- 記者が知事に厳しい質問をすると実名晒しされ攻撃される
- 批判的意見を述べた県民がSNSで攻撃される
- 記者会見で質問しただけで「敵」扱いされる
- 記者の所属社に抗議が殺到し取材がしにくくなる
- 支持者が“攻撃してもいい雰囲気”を感じて暴走する
という構造が広がっています。
これは県が掲げる理想とは真逆です。
兵庫県の計画は「孤立させない社会」を目指しているのに、知事の周辺では「批判者を孤立させる社会」が進行している。
これこそが最大の矛盾です。
「どの口が言うのか」──県民の素朴で正当な感覚
県は自殺についてこう説明しています。
「正常な判断ができないほど追い込まれた末の死」
であると。
この定義に当てはめれば、元県民局長や竹内元県議を追い込んだ要因の一つが「県政からの圧力」「周囲の攻撃」であった可能性は、完全には否定できません。
そうした状況を見た県民が、
「どの口が“誰も自殺に追い込まれない兵庫”と言うのか」
と憤るのは当然です。
行政のトップが掲げるスローガンは、その言葉が現実と一致して初めて意味を持ちます。
現状は、言葉と現実が完全に乖離しています。
本当に「誰も自殺に追い込まれない兵庫」を目指すなら
県が本気で自殺対策を語るのであれば、次の3つが不可欠です。
① 批判者への攻撃を明確に否定する
トップ自らが
「誹謗中傷は許されない」
「どんな意見の人も尊重されるべき」
と発信しなければいけません。
② 自らの言動による“間接的な影響”を真摯に省みる
特に元県民局長や竹内元県議の死は重く受け止めるべきです。
③ 県政が生みだした心理的圧力の構造を解消する
批判者を敵視する空気をなくし、誰もが安心して声を上げられる環境が必要です。
これをせずにスローガンだけ掲げても、
県民の心には届きません。
まとめ
兵庫県は「誰も自殺に追い込まれない社会」を掲げながら、実際には批判者が追い込まれる環境が作られてしまっています。
- 記者の実名晒し
- 批判者への攻撃
- 取材活動の圧迫
- 県民の萎縮
- 精神的負荷の増大
これらは自殺リスクを高め、行政の掲げる理念と完全に矛盾します。
本当に「誰も自殺に追い込まれない兵庫」を実現したいのであれば、まずは批判者を守り、意見が自由に言える環境づくりが必要です。
- 元県民局長や竹内元県議の死因は特定されていない
- しかし、県政の発言・圧力・攻撃的なSNS空間が“遠因”になった可能性は完全には否定できない
- 自殺は「複数の心理的要因が重なって追い詰められるもの」であり、県自体もそう説明している
- にもかかわらず、批判者が攻撃される環境を放置
- これでは「誰も自殺に追い込まれない兵庫」は言葉だけになってしまう
県の掲げる理念と、現実の県政運営の矛盾を直視することこそ、
本当に“誰も追い込まれない兵庫”への第一歩ではないでしょうか。