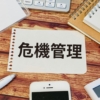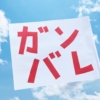「公益通報を“デタラメ”と断じる東京ファクトチェック協会の記事の危うさ ― 兵庫県文書問題で問われる通報者保護の倫理」
目次
はじめに:問題の東京ファクトチェック協会の記事とその主張
2024年の兵庫県「文書問題」をめぐり、
東京ファクトチェック協会の記事(リンク)が次のように述べています。
「斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見があります。
第三者委員会までもそのようなことを言っておりますが、デタラメです。」
この一文は一見、断定的で自信に満ちた主張に見えます。
しかし実際には、法律や制度の趣旨を無視し、
行政トップとしての倫理的責任を軽視する危険な発言です。
まず、東京ファクトチェック協会の記事の主張を整理すると、主に以下のようなロジックになっています。
- 3月12日の文書は「噂話を集めたもの」「匿名」「真実相当性を欠く」 → 公益通報に該当しない
- 通報主体(公益通報者)になり得ない者からの提供 → 公益通報ではない
- 通報先が通報内容を公益通報と認識していない → 通報者保護義務なし
- 通報内容が「不正の目的」である → 公益通報保護法の対象外
- 第三者委員会報告書にも法規定に基づく根拠なしと記載されている → 第三者委員会の主張も法的根拠薄
- 消費者庁の Q&A や法律解釈もそれに沿っている → 記事主張を補強
この記事では、**「事実と倫理の観点から見た東京ファクトチェック協会記事の問題点」**を整理します。
①「噂話を集めた匿名文書だから公益通報ではない」?
東京ファクトチェック協会の記事では、2024年3月12日に作成・配布された文書を「噂話を集めた匿名文書」「真実相当性を欠く」と断じています。
しかし、公益通報者保護法は「通報内容が真実であること」までは要件としていません。
公益通報者保護法逐条解説(抜粋):
築城解説では通報内容の真実相当性(「信ずるに足りる相当の理由」)を保護の要件としている。
ここで「信ずるに足りる相当の理由がある場合」とは、例えば、通報対象事実について、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠がある場合をいう。
また、第三者委員会報告書(2025年3月19日公表)でも次のように記載されています。
「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があったものといえる。(報告書P.142)
つまり、匿名であっても、公益目的が明確な通報であれば保護の対象になり得るのです。
匿名=除外という東京ファクトチェック協会の主張は、法の趣旨を著しく矮小化しています。
斎藤知事は「県職員による作成・配布」と認識していた
第三者委員会報告書によれば、知事自身がこの文書について、
「県職員が作成した可能性がある」と認識していたことが複数の証言で裏付けられています。
第三者委員会報告書(2025年3月19日)第9章~第12章、p.120
「知事は3月21日の段階で、文書が県職員により作成・配布された可能性があるとの前提で、
関係部局に対し探索を指示している。」
つまり、知事は“誰が書いたかわからない匿名文書”としてではなく、
“県職員による内部的な文書(=内部通報の可能性がある)”として受け取っていたのです。
その認識のもとで探索を指示した=通報者探索の禁止違反
公益通報者保護法に基づく指針では、次のように明記されています。
「労働者等及び役員並びに退職者が通報対象事実を知ったとしても、自らが公益通報したことが他者に知られる懸念があれば、公益通報を行うことを躊躇(ちゅうちょ)することが想定される。このような事態を防ぐためには、範囲外共有や通報者の探索をあらかじめ防止するための措置が必要である。」
斎藤知事が「県職員による作成・配布」と考え、
「徹底的に調べろ」と指示した時点で、公益通報者を特定しようとした行為にあたる可能性が極めて高いです。
そのため、第三者委員会は次のように結論づけています。
「片山元副知事ら県職員が齋藤知事の指示に基づいて通報者の探索をしたことは、保護法及びその委任を受けた指針第4の2(2)口に違反する行為であって、違法である」(報告書P.136)
②「通報主体になり得ない一般人からの提供だから公益通報ではない」?
公益通報者保護法の第2条では、**「事業者等の労働者その他通報対象事実に関与する者」**を通報者としています。
つまり、「行政機関の職員」も当然含まれます。
第三者委員会報告書も以下の通りです。
「本件文書の配布が「不正の目的」でなされたものと評価することはできない。本件文書の作成 配布行為は、3号通報に該当する。」(P.134)
通報者が誰であるかを確定していない段階で、「通報主体になり得ない」と決めつけるのは不当です。
むしろ、県が通報者探索を行ったこと自体が、法13条の禁止行為に該当する可能性を第三者委員会は指摘しています。
「誰が書いたのか分からないから保護しなくていい」ではなく、
“ひょっとすると職員かもしれない”と考えられる時点で、探索をしてはいけないというのが行政の正式な立場です。
斎藤知事の場合は「職員の関与を想定していた」
百条委員会(2024年9月6日)によると、
知事は2024年3月21日の時点で、すでにこう発言していたと記録されています。
「片山氏は今年3月21日に斎藤知事に呼び出され、「その日の打ち合わせの時に知事から『徹底的に調べてくれ』というお話があったような記憶があります」」
「斎藤知事から「徹底的に調べてくれ」という話があった 兵庫・片山元副知事が百条委で証言」
https://news.yahoo.co.jp/articles/dcd305d6f00196468bd0337c0457cd9bc6c1c25d(出典:Yahoo!ニュース 2024年9月6日)
つまり、知事は「誰が書いたかわからない」ではなく、
**「県職員が書いた可能性がある」**という認識を持っていたのです。
その認識のもとで探索を指示したなら、
それは**「公益通報者を特定しようとした」行為**に該当します(法第13条違反の可能性)。
③「通報先が公益通報と認識していないから保護義務なし」?
この主張は法律の読み違いです。
公益通報者保護法第11条は、
「行政機関の職員は、公益通報者を特定しようとしてはならない」と明記しています。
この義務は、「通報を公益通報と認識しているかどうか」にかかわらず発生します。
むしろ、公益通報である可能性を認識できる状況で探索を行えば、違法行為に近づくのです。
新井消費者庁長官(2024年4月17日記者会見):
「兵庫県の第三者委員会は西播磨県民局長の問題に対して、これは3号通報に該当し知事が行った通報者の探索行為は公益通報者保護法違反としているけれども、これに対する対応は除外されているということが問題になっています。」
よって、「認識していなかったから問題ない」という主張は、法的にも倫理的にも成立しません。
④「通報内容が不正の目的だから公益通報に該当しない」?
東京ファクトチェック協会の記事は、「通報が不正の目的(誹謗・中傷・報復)であった」と決めつけています。
しかし、これも第三者委員会が明確に否定しています。
「元西播磨県民局長が本件文書を作成 配布した目的は、当時の県職員内部で話題になっていた齋藤知事や片山元副知事ら側近幹部職員の言動に対する不平不満や不信感を代弁し、反省すべき点を改めてもらい、風通しのよい県政になるようにとの願いを込めたものであったと考えることができる。(報告書P.133)
つまり、「不正の目的だった」と断定する根拠はどこにもありません。
県の側が“そう主張したい”だけの印象操作です。
⑤「第三者委員会の主張にも法的根拠がない」?
第三者委員会は「法的判断機関」ではないため、裁判所のような拘束力は持ちません。
しかし、その代わりに事実認定の中立性と証拠分析に基づいた報告をしています。
報告書では、複数の県幹部・文書関係者・外部専門家のヒアリングを踏まえ、
通報者保護法13条の観点から**「探索が行われた」との認定**を示しています。
つまり、「法的根拠がない」のではなく、法の趣旨に基づいた専門的認定なのです。
⑥「消費者庁のQ&Aも記事の主張を補強している」?
消費者庁の通報者の方への冒頭部分を読めば、不正な目的で無ければ保護されると記載されています。
「公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。」
つまり、「不正の目的」で無ければ保護義務が生じるのです。
「公益通報と認識していなかった」とする県側や東京ファクトチェック協会の記事の主張は、この原則に真っ向から反します。
公益通報とは何か ― 制度の本来の目的
公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
消費者庁の公式サイトでは、次のように説明されています。
「公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生 活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています」
(出典:消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要)
つまり、通報内容がすべて正しかったかどうかよりも、
“公益目的で通報した行為そのもの”を守ることがこの制度の柱です。
第三者委員会も報告書の中で、こう述べています。
「本件文書には数多くの真実と真実相当性のある事項が含まれており、「うそ八百」として無視することのできないもの、むしろ、県政に対する重要な指摘をも含むものと認められた。」
(兵庫県第三者委員会報告書よりP.150)
「デタラメ」と断じる主張の危うさ
東京ファクトチェック協会の記事が最も問題なのは、
公益通報という制度の理念を“通報者の人格攻撃”と混同している点です。
記事では、「匿名であり噂話の域を出ない」「真実相当性を欠く」といった理由で、
通報そのものを否定しています。
しかし、公益通報者保護法の本旨は、
「通報内容の正誤を裁くこと」ではなく、
「通報を理由に通報者を追及しないこと」にあります。
消費者庁の保護要件に関するQ&Aにも明記されています。
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。」
(出典:消費者庁保護要件に関するQ&A)
この制度を理解せず、「デタラメ」と断じるのは、
公益通報制度を根本から否定するに等しい態度です。
第三者委員会が指摘した“通報者保護”の視点
兵庫県が設置した第三者委員会は、
知事側の対応に次のような問題点を明確に指摘しています。
「本件文書の作成配布が3号通報として公益通報に該当する以上、かかる理由による通報者探索は、保護法1 1条4項及び指針第4の2の公益通報者保護の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第4の2(2)口が規定する「やむを得ない場合」に当たるということはできない。」
(兵庫県第三者委員会報告書P.136)
つまり、第三者委員会が問題視したのは「通報内容の真偽」ではなく、
「通報者を守るべき立場の知事が、探索を指示した行為」そのものなのです。
この視点こそが、東京ファクトチェック協会の記事には決定的に欠けています。
知事が取るべきだった対応とは
行政トップとしてあるべき行動は、
通報文書が出回った際に「内容の真偽よりも、まず通報者保護を徹底する」ことです。
仮に内容に誤りがあったとしても、
公益通報制度の信頼を守るためには、通報者の安全を優先する姿勢が求められます。
それを「デタラメ」と切り捨てることは、
制度全体を萎縮させ、将来の通報を妨げる結果につながります。
通報者を守ることは、行政への信頼を守ること
公益通報制度は、個人を守るだけの仕組みではありません。
行政や企業の信頼性を高め、
内部不正の早期発見を可能にする“社会の安全弁”です。
それを「デタラメ」と言い切る言説は、
組織に対して「通報すれば叩かれる」という恐怖を植えつけ、
結果的に不正を見過ごす社会を助長します。
まとめ:制度の精神を忘れてはいけない
東京ファクトチェック協会の記事が主張するように、
第三者委員会や専門家の指摘を一方的に「デタラメ」と断じることは、
法的にも倫理的にも軽率です。
公益通報制度は、通報の正確性を裁くためのものではなく、
「不正を恐れず声を上げる人を守るための制度」です。
兵庫県の事案をめぐる議論は、
まさに行政がこの原点に立ち返る機会であるべきです。